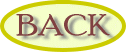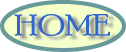| �N�� | ���� | �o�T | ������ | ���l |
| ���a15�N6��27�� | �a�c���쎀�� | 48 | ||
| ���a��\��N�� | �a�c����̘b���ł́A���a��\��N�ĂɓV�䗠���當���������Ă��āA���̗����ɕ��m�呠�����Ɍ�������A�M�d�ȕ����Ȃ̂ő厖�ɂ��Ă����悤�ɂƌ���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B���̌�A�a�c����̋߂��̊J�Ēq�Z����ɂ��������Ƃ������Ƃł����B�J�Ă���͍ŏ��͖����p�̎j�������āA�w�ыl���j�x�i���a��\�l�N�ҏW�����A��\�Z�N���s�j�Ɍf�ڂ���Ă��܂��ˁB | 9 | �É� | ���������ւ̃C���^�r���[ |
| ���a22�N8��(1947) | �X�����쌴�s�ыl������̘a�c���s�Ƃɉ����āA�^�钆�A�V�䂩��傫�ȋ����������Ă����B�V�䗠�ׂĂ݂�ƁA���̑��ɂ��Z����D�ה�������Œ݂���Ă���(�a�c�씪�Y��) | 47 | �a�c | |
| ���a23�N6��(1948) | �a�c�씪�Y�A���_�R�@���������B(���{���K�m�[�g�u���_�R�@�������@�vNo1���) | 47 | ���{ | |
| ���a��\�l�N | ����R�n���_�R�[�A�f�ˑ�t�߂ŒY�Ċ��z���A���R�ɂ����A���B���̒���T���������A��X�̕����A����A�얀�퓙�������A�����̒��ɑ����|�����ׂ����Ŋ�d�ɂ������A���œh�肩���߂��o��������A���̒����瑽���̏C���@�̎����Ƌ���������l�Ɋւ��鎑�����������ꂽ���̂��ƁA����ċ���܂��B | 1 | ���{ | |
| ���a��\�l�N | ���A����|���i�o�ǁj�Ƃ��������o�āA�����Ɍ��쌴�Ō��J�����̂ł����A��čs���Ă��̂܂ܕ�
���Ȃ��l�����܂������A�s���s���ɂȂ����╨������܂����B���ꂩ��a�c����͋M�d�Ȏ������U�킷��̂�����āA�����A��������Ɍ����邱�Ƃ��~�߂���
�����B����ȗ��A�����l�Ɂu�͂��A�ǂ����v�ƌ����Č�������A���A�Ɉē������肷�邱�Ƃ͂��Ȃ��悤�ɂȂ�܂����B����͎d�����Ȃ����Ƃł��B�����̂���
��m���Ă���l�͘a�c����̋C�����͂悭����܂��B ������l�̕������ォ�������U�삾�ƌ����l�����܂����A�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł��B�a�c����ɍ���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł���B�ǂ����獪���������āA�����������Ƃ����������̂��A�͂����莦���Ă�������A������ł����_�ł��܂��B�����A��������Ȃ����낤���A��������Ȃ����낤���Ƃ���������A���{���T����ł��傤���A�u���v�Ƌ����v���Ȃ�Č����āA�J�Ă���ⓡ�{����̗v���ɂ��킹�Ęa�c���������ȂǂƁA�悭����Ȃ��Ƃ������܂��ˁB |
9 | ���� | ���������ւ̃C���^�r���[ |
| ���a��\�l�N���� | ���������B���������Ă������ɋ��R�Ɏj������������l�̂��Ƃ��L����Ă���̂�����������ł��B�u�Z�ڎO���l�\�сA�l�̎O�{�͎����A�l�̎O�{�����āA��������Ȃ��낤�����̂��炢�A�������܂ň���ɕ��v�Ƃ����u�����́v�܂ł���������ł��B���{���T���Ă��N���m��Ȃ��������Ƃł��B����ŏ��a�\��N����������l�̂��Ƃ��������Ă��������Ăꂽ�̂ł��B�J�Ă���Ƃ͐e�ʂŕ�����w�ł͐�y��y�̒��ł�������B�u���������B���������̂��o�ė������v�Ƃ������Ƃōs������A�Ƃɂ����т����肵�܂����ˁB���A���������ꂽ�̂��A���a��\�l�N�����ł�
������A���̌�̂��Ƃł��ˁB �|�|������������A������ꂽ�̂ł����B �@���܂ł͍s���܂������A���Ă��܂���B �|�|�J�Ă���͓��A�ɓ���ꂽ�悤�ł��ˁB �@���������m��Ȃ��B���A�̔��ɏ����Ă����������̂��Ƃ͋����Ă��炢�܂����B�Ƃɂ����A�a�c�Ƃ͑T�@�ł������A�S���Ȃ����J�Ă���Ƙa�c����́u�t��v�̊ԕ��ł�������B |
9 | ���� | ���������ւ̃C���^�r���[ |
| ���a���l���N�N���� | �w�ыl���j�x�t�^�E�J�Ēq�Z�u�ː��O�j�[�T�v�u�����v | �J�� | ||
| ���a24�N (1949) |
�E�a�c���s���q�A����A�R�̂���ꏊ����A�ؔ�120���E���S�W�������@�B�i���m�呠�u���y�����N�W�^�v���j �E�a�c���s���q�A����R�f�ˑ�t�߂̓��A���A���s�ҁE������l�W�������B�i7���j�@�i�J�Ēq�Z�w�ыl���j�x�w������l�x���j ���w�������Z�S���S�x���Ƃ����i�a�c�씪�Y�j�ł́A���a23�N�ĂƂ���B |
47 | �a�c | �u���y�����N�W�^��E���j�v���m�呠�@���ʔN���@1948�`1949�N |
| ���a��\�ܔN������\��� | �������O��(����)���}�Z���������̂��߂ɗ��O���A���a��\�ܔN������\����ɍ��d�v�������Ƃ��čĎw�肳�ꂽ���̂ł���܂��i���O�O�����ً{��T��Y�W���̌��j�B���̎��A���}�Z���̗��O���āw�ыl���j�x�ҏS�ɋ��͂��Ă����a�c���́A�����̔ыl�������J���y�ђ��J�����A�J�Ēq�Z�t���X�A�h����ł���O�O�s�Ώꗷ�قɍ��}�Z����K�˂āA���@���̊Ӓ���˗����Ă���Ɖ]������������A���̎��͏��a��\�Z�N�ȑO�ɘa�c�����w�ыl���j�x�ҏS�ɐϋɓI�ɋ��͂��Ă��鎖��@���ɕ�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B | 1 | ���{ | |
| ���a��\�ܔN�\�ꌎ�L�� | ���j�l�Û{���w�����p�̌Õ�ᢌ��ɂ��āx | |||
| ���a25�N (1950) |
�O�O�s�������O��̍��d�v�������\���ɔ��������̂��ߍ��}�Z�����O�B�h����O�O�s�Ώꗷ�قɁA�����̒��J�ыl�����E�����E�J�Ēq�Z�Z�E�E�a�c�씪�Y���K�ˁA���@���̊Ӓ���˗��B���}�Z����蓐�i������������B�i7�����j | 47 | ||
| ���a���Z�h�K�N�c���� | �w�ыl���j�x�t�^�E�J�Ēq�Z�u�ː��O�j�[�T�v�ыl�����E���J�\���Y�u�����v | ���J | ||
| ���a26�N (1951) |
�J�Ēq�Z�A���s�Ҍ�����E�e�i1949�N�j�B�����i1951�N�j | 47 | �w�ыl���j�x�u�ː��O�j�[�T�v�E�E�E���s�҂Ƃ��̏@���@�J�Ēq�Z | |
| ���a26�N11���E12�� | �w��y�x�������Ɂu���g�V��̎ɗ����v�Ƒ肵�āA������苳�撷�́A����G�������ڂ����q�ׂ��Ă���̂� | 13 | ���� | |
| ���a�����p�C�����N�M | ���m�呠�w���y�j���ٕ����k�x�u�͂������v | 25 | ���m | |
| ���a27�N8��14�� | �M�ʂ̔Y�݂́A�����҂̘a�c�씪�Y�N�������̋M�d�Ȏ����������炳�܂ɒ��Ȃ����Ƃł����āA�N��I�ɂ����Ă��A�܂������Ƒ��w���ΏƂɂ��͂ƂȂ�ׂ��@��o���ꂽ�ؔ�̏����[�������ł��ʂƂ��납��s���l�܂�𗈂��Ă����Ԃł����āA�a�c�N�̐ϋɓI�ȉ����ӎu���̂���ł���B | 24 | �J�� | |
| ���a��\���Nᡖ��N�~���� | ���m�呠�w���y�j���ٕ����k�@���сx�u���тɂ��āv | ���m | ||
| ���a��\���Nᡖ��N���� | ���m�呠�w���y�j���ٕ����k�@���X�сx�u���X�тɂ��āv | ���m | ||
| ���a��\��ᡖ��N�������{ | ���m�呠�w���y�j���ٕ����k�x�u�����ɏ�����������v | 26 | ���� | |
| ���a��\�N��̌㔼 | �|�|�a�c����́u�E�C�v�Ƃ����@����������āA�u�����t�v�̈�
�������ƕ����Ă��܂��B�U��_�҂͂�������肻�����Ȃ����Ƃ��ƒ������Ă��܂����B �@�����Ȏt��̊W�������ǂ����͒m��܂��A�����t�͎t��̊W�����ׂ����Ɏ��܂�����ˁB����łˁA�a�c����͔ыl�̉w�̒ʂ�ɏ����Ȃ��� �����Ă܂��ĂˁA��y�@�̈ߒ��āA��ԍʼn���(�����t)�̈ߒ��āA�q��ł�������ł��B�߂͏@�K�Ō����Ă���܂�����A�u����A�����t�̈� ��������ȁv�Ǝ��͂����猩�Ă�������ł��B���ڂ͕����Ă���܂��A�t��̊W������Ō����t�̈ʂ�������ƊF����������Ă��܂����B �|�|����͂����̘b���ł��傤���B �������Ă��̂́A���A����o�ǂ╧�����o�āA��`�O�N��̂��Ƃł����珺�a��\�N��̌㔼���Ǝv���܂��B �|�|����������ꂽ�a�c�ƕ����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B �@�ĉ~���W�̂��̂������l�W�̂��̂ł��B �|�|�ʂ͂ǂ̂��炢�������̂ł��傤���B �@���̂ˁA�������Ƃ����̂ł��傤���^���X�̂悤�Ȃ��̂ɁA���̈ʂ́i������L���Ȃ���j���̂ɁA���ɂȂ������̂⊪�������̂������Ă���܂����B�a�c�� ��̘b�ł́A�����������Ă��܂��Ă���̂ŁA�ꖇ�ꖇ�����Ă���łȂ��ƌ������Ȃ��Ƃ������ƂŁA������l�̂��̂�T���Ă���ƌ����Ă��A�u������������ׁA������������ׁv�Ƃ��傢���傢�����ė��Ă���܂����B�����͎��������ƌ��Ă���͂��ł��B �|�|�a�c����̘b���ł́A�����A�������ʂ����Ă���Ƃ������Ƃő����̐l�����āA�� ���Ă����������ł��B�K���X�̏�ɒu���āA�����烉�C�g���Ƃ炵�āA��������ɖ͎ʂ���Ă����Ƃ������Ƃł����B����炪���������ɏo����Ă���悤�ł��B �@�����������Ƃ͂��邩���m��܂���B������l�j���������l�Ȃ��̂���������܂�������B |
9 | ���� | ���������ւ̃C���^�r���[ |
| ���a��\��N�\�l�� | �E�E�E�ыl���E�E�E�_�Ƙa�c���s����i�܌܁j�����j�씪�Y����i��Z�j�e�q�͏��a��\�l�N�������������̔ыl�R���ŒY�ėq�낤�Ƃ��ēy�����@��Ԃ����Ƃ��둊���傫���Ύ����A���@�̌��ʕ��A�_�����͂��ߕ���o�𗘗p�����Õ����Ȃǂ��o�y�����B�o�y�i�͖{�M�̌��n�@���ɂȂ���̂���S�����������̂Ƃ���Ă��邪�A���e�q�͏o�y�i�Əꏊ�����J���邱�Ƃ��ɒ[�ɋ��ۂ������߂��̐^�U���߂����ĊW�҂��狻����������Ă������A���̏o�y�i�̌��J���\����ߑO�\�����瓯����ōs��ꂽ�B | 29 | ||
| ���a30�N12��5�� | ���������w������l�x�����s | ���� | ||
| ���a�O�\��N | (�w���@�O���Ɩ����x�ɂ���)�f���炵���ł���B������ԍŏ��ɘa�c�����������l�W�����������̂͏��a�O�\��N�̂��Ƃł������A���������a�c���̂��̂��A�����A������l�̂��Ƃ�m��Ȃ������ł���B | 9 | ���� | ���������ւ̃C���^�r���[ |
| ���a�O�\��N�x���O�\��N�x | ���܂��܉E�̔������ꂽ��Õ��������������ꂩ�獶�L�ɂ����������l�Ɋւ���Â��������łĂ����̂ł���B�����������Ăы��ɐ������A���ʂ�������ł���B�J�ď�l�͂��̎������@��ɔ��\���ꂽ���A���͍X�Ɏ����𒆐S�Ɏ��̐��l���ȉ��L���邱�ƁT��������ł���B | 21 | ���� | 133�� |
| ���a�O�\��N�l����\�O�������\���� | �����m���́A�O�O�s�V�����������̖@�v�ɏ�����A��\�O���ɂ́A�J�R������l�̎��S�l�\����̖@�v�ɂ�����A�{���Ɉ�ꂽ�P�j�P���ɑ��āg������l�̐̂��Âтāh�Ƒ肵�āA�����ӂ�킹�A�܂ɂނ��ѓ�玂�q��Ȃ��ꂽ�B | 21 | ���� | |
| ���a�O�\��N�l���O�\�� | �����m���A��J�ď�l�Ɛe�����������߁A������K�ꂵ�ہA���L�̋�����l�̌Â�������q���v���A�����̂��܂�A���[�ɋA���Ă���A�A����������ގʒv���i����m���̖F���ɂ��ƎO�\�����j���㎛�Ŕ���m���䉺���͂��߁A��y�@�̏��哿�ɑ����Ă���B�i�������̈ꖇ��m�����璸���Ă���B�j | 21 | ���� | 133�� |
| ���a�O�\��N�܌� | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x�����E�������N�m���u�������́u������l�v�Ɋāv | |||
| ���a�O�\��N�����ܓ� | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x�����E�Ŕ���m���@��u�����v | |||
| ���a31�N 1956 |
���������i������~���Z�E�j�A�ыl����Z�E�J�Ēq�Z���A������l�W�����������Ă��炤�B | �u���y�j���ٕ����k�v���m�呠�i1956�N�j | ||
| ���a�O�\��N���U | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x���� | |||
| ���a�O�\��N���� | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x�����E�@��c������א�c���u�����v | |||
| ���a�O�\��N�ꌎ | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x�����E�X����@�c���S�\�N��������ǁE�H�������u�����v | |||
| ���a�Q�E��N������ | ���e���͋ɂ��ŋߘa�c�씪�Y���ɂ���Ĕ������ꂽ�M�d�ȌÕ����ł���B | 20 | ���� | |
| ���a�O�\��N�� | �w������l�̌����x�E�e | 9 | ���� | |
| ���ܔ� | ���m�呠���v |
50 | ���{ | |
| ���a�O�\�ܔN�ꌎ | �ĉ~�����������t�A�}���̐��ҁw������l�̌����x���� �w������l�̌����x�Řa�c�Ǝj�����Љ�B���������B���߂͘a�c����͉�������Ȃ������B�ыl�̑����(�J�Ēq�Z��)���a�c�Ǝj���̖����p�̒������Ɂu�����v�����āA�͂��Ƌ�������ł���B����܂ł͘a�c������m��Ȃ������B���ʂ̏�y�@�̑m�����m��Ȃ���������ł�����B������������ׂ܂�����B����͂���̂Ɏ��т��S������Ȃ������B����Ȏ���ł�������A�a�c�����������l���@�R��l�̒���q�������Ȃ�Ēm��Ȃ��������A�܂��Ă�w���@�O���Ɩ����x�̂��ƂȂm���Ă���͂����Ȃ��B�w�҂ł���������̂ł͂Ȃ��B�����������̂������o�Ă�����ł��B |
1/9 | ���{�^���� | |
| ���a35�N (1960) |
�w������l�̌����x���������i1960�N1���j | |||
| ���a�O�\�Z�N | ���{���K�A�a�c�씪�Y�Əo��B �|�|�|�|�| ���a�O�\�Z�N�̏H�A���ˎs�\���@�������C�t���Ώ�������A���蒬�����@�œ��@���Â����ċ���܂������A���x�a�@�ׂ̗肪����@�ł������W��A�@�c�@�R��l�̌���̓��̌�����ŁA������l���u���B�F��y���v����⌾�ɁA�@�c�̋�����@���ɓ��k�̒n�ɕz�����ꂽ���������܂����B �@���̌�̐e�a��ŁA�ƒn�Ìy�n���ɉ�����������l�̔O���O�ʂ̂��߂̌��S��`����Õ������A�ыl��̊J�Ēq�Z�t�̂��Ƃɕۑ�����Ă��鎖�ɘb���y�сA����ɂ���ĝ���@���c���~�t�A���������Y���A������ꎁ�A�����{���K�����K��A�a�c�씪�Y�������@���ꂽ�Õ����̐��X�A�K���_�[���ł̗l�Ȏ߉ދ�s���A�A�g���X�_���A�얀�퓙��q�ς���Ƌ��ɁA���̓����߂đ�ɉ��Ęa�c�씪�Y���ɏo���������̂ł����B �|�|�|�|�| �ȏ�q�ׂ܂����l�ɁA���Ƙa�c�씪�Y���Ƃ̍ŏ��̏o��͏��a�O�\�Z�N�̎��ł���܂��B�������A���̍��͂܂��w�������O�O�S���x�̑��݂�m��܂���ł����B |
1 | ���{ | |
| ���a�O�\�Z�N | ���Ƙa�c���̏o��͏��a�O�\�Z�N�̎��ł���ƑO��q�ׂ܂����B�������A���̌�A���x���a�c���Ɖ���Ď���������̌o�ߓ����܂������A���̍��͂܂��w�������O�O�S���x�̎��͘b���Ă���܂���ł����B�@�@�@�@ | 2 | ���{ | |
| ���a�O�\�Z�N����H | �J�Ď��́w������l�x���o�ł��鎖�ɂȂ��āA���̌��e�̒��ɓV�^����i���܂Ȃ��j�{�̎������o�ė��܂����̂ŁA���̐��͓��{�ł����A���i�K��j���V���i���܂Ȃ��j�Ƃ��瓡�{�Ƃɗ{�q�ɓ����ċ��鎖�A�������w���̍��A�V���Ƃ̑c�������c���{�l�ł��������A�R�����~�Ɖ]���ĎR���̏o���肪��ɂ��������A���~�̒��ɒ��̖��͔|����Ă��������ȂǁA���̐�c���V�^����{�ł��鎖��b���܂������A�a�c�����玄�ɓn���ꂽ�̂��g�V�^����ƊW�����h�ł����B�����ł��̌�A�������������̂��g�V�^����ƕ����h�Ȃ̂ł��B �@�ŏ��A���́g�V�^����ƕ����h�Ɓw�������O�O�S���x�Ƃ͑S���ʁX�̎����ƍl���ċ���܂����̂ŁA�k���V�Њ��́w�������O�O�S���x�ɂ������Ɂg�O�O�S���h�ƕ\��̂�����̂ɏ�����Ă��鎑���݂̂��l���Ɍf�ڂ������̂ł��B �����̎��Ƃɉ��Ă��A�c������c�͋{�l�ł������Ƃ����������킩�炸�A�ǂ̗l�ȋ{�l�ŁA�ǂ̗l�Ȏ��т��������̂����͑S���m���Ă��Ȃ��Ɖ]���L�l�ł��B�킸���ɐ��{�̓��Ƒ傫�ȗ邪��ӈ₳��ċ��邾���ł����B�����Ɂg�V�^����ƕ����h���o�ė����̂ł��B�����������g�̃��[�c�Ɋ֘A�̂��鎑���̏o���ł��̂ŁA�S�������ɂȂ��Ă��̌����Ɏ��|����������ł��B |
2 | ���{ | |
| ���a36�N�H 1961 |
����ێ�@�Z�E���c���~�A�h�k���������Y�E�������E���{���K�A���K�ˁA�Z�E�J�Ēq�Z�Ƙa�c�씪�Y�ɉ�B | 47 | ||
| ���a�O�\�Z�N����O�\���N�ɂ����� | �a�c�씪�Y���̏�����g�V�^����ƕ����h�g���|��֘A�����h������悤�ɂȂ�A����玑���̐���������i�߂Ă��鏊�� | 3 | ���{ | |
| ���a�O�\�Z�N���珺�a�O�\���N�ɂ����� | �����������Ă䂭�ƁA�����ɏ�����Ă��鎖���́A�c���̉Ɖ��~�̒n�`�ƑS�����v���邵�A���̑��̎����ł����������ƍ��v������̂����X����܂��̂ŁA���a�O�\�Z�N���珺�a�O�\���N�ɂ����Ắg�V�^����ƕ����h�̐��������ɑł����݂܂����B �@�����āA�g�V�^����ƕ��������Ă��邤���ɁA�����ƕ��s���Ĕѐύ��|�� �����ꑰ�֘A�̎���������l�ɂȂ�܂����B��ɔ����������ł����A�����\��N�i��l���Z�j�ɓV�^����{���k���A�������ɉ��K���ē쒩�n�̒��b�������[���q���̒������q��т̍��|��Ɍ䐬�K�������͓��R�̂��Ƃƍl�����܂��B |
2 | ���{ | |
| ���a�O�\���N�� | �g�V�^����ƕ����h�Ɓg���|�镶���h����ʂɎ��̏��֎������܂�܂����B | 2 | ���{ | |
| ���a�O�\���N | �g�������֘A�����h���o�ė����̂ł����A�ŏ��͂�����w�������O�O�S���x�̕\��̂Ȃ��f�ГI�Ȃ��̂���ł������A���܂őS���Ɖ]���ėǂ����A�s�҂̑����������������猩���������Ȃ����҂̑�����̎����������c���ċ������ׁA���ɂƂ��Ă͘a�c�������Q����S�Ă��A��ϋM�d�Ȑ��̎����ł����B �@�]���āA���̍��͓V�^����{�ꑰ�A���|�铡�����ꑰ�A�������ꑰ�̒�����������s���Đi�߂ċ���A�a�c���̌��쌴�s�ыl�ւ͑��ɂ��ʂ��āA�s���x�Ɉ������֘A�̎����̂Ȃ����ƂƁA�a�c���̎����̋M�d�Ȃ��Ɠ�������������A���Ɂw�������O�O�S���x�ƕ\��̂���������֘A����������l�ɂȂ����̂ł��B �@�������A�ꊪ�ڂ��珇���悭���Q���鎖�͂Ȃ����s���ł���A���������q�{���芪�q����ŁA�ŏ��͂��̑S�e��c�����邱�Ƃ��o���܂���ł������A�a�c������͖c��ȗʂ̎����Q�ł��鎖�͘b����ċ���܂����B |
3 | ���{ | |
| ���a�O���N | �w�������O�O�S���x�i�a�c���g���ʖ{�j�����߂Ď��̂��Ƃ֘a�c���ɂ���Ď��Q����܂������A�����͂��ꂪ�O�S�Z�\�������̗ʂł��邱�Ƃ�m��܂���ł����B�a�c���͌܁A�Z���i���j���炢�����Q���A��x�ɑ��
�Ɏ����ė���Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B������ꊪ�ڂ��珇���Ɏ����ė���Ƃ������Ƃ��Ȃ��A���s���̏�Ԃł��B �@��ɔ����������Ƃł����A�c��Ȑ��ʂł��̂ŁA��̕�����蓖�莟��Ɏ��Q�������̂ł���A�������a�c�����g�A���̍�����n���ł��鍂�|��̎��A�����ꑰ�̎��A�����ꑰ�̎����ɊS�������͂��߂��l�ŁA�ꉞ�������g�œǂݏI�������̂����̏��֎��������̗̂l�ł����B |
4 | ���{ | |
| ���a�O�\���N�O����\�ܓ� | �J�Ďt�͘a�c������̐V�����̒ɗ͂āA�����\�L�]�N�Ђ������������l�̌����ɖv���B�V��ɂ�������炸���a�O�\���N�O����\�ܓ��Ɏ����āA�Q�X�����т���������l�̓`�L�y�т��̏@�`�������A�E�e����܂����B���̌�A�a�c�씪�Y���́A�V�����̒����睐��@�W�̈ꏑ�����Q������@�Ɋ�i����āA�J�Ďt�̘J��o�łɑ��鉞�����𝐎�@�h�M�k�ɍ������܂����B �@������ĝ���@�ӔC�������{�K��i���̕��j�͈���A�ыl��ɊJ�Ďt��q�ˁA�J�Ďt�̐��U���������������̂܂ܖ����ꂳ���ɂ��̂тȂ��Ƃ��A�����������l�ɂ䂩��̐[�����X�̐l�B��������l�̌�⓿�𐢂ɔ��\�o���鎖�A�܂����a�l�\��N��������l���S�\�N�剓�����}����ɂ������āA�J�Ďt�́w������l�x���L�O�o�ŏo����̂��A��������O������̈����Ɉ˂���̂ł��낤�ƁA�o�Ŏ����̒�\���o���̂ł��B�J�Ēq�Z�w������l�x�����E��y��呍�{�R�m���@��ՁE�ݐM�G |
1 | ���{�^�� | |
| ���a�O�\���N�������� | ������l�̈�Ղ̈�ł��鐳���R���ꎛ�͈��͑咆�R�������Ƃ����Ă��邪�A���̐Ղ����͞���R�ƌĂ�ł���Ƃ̂��Ƃł���B���̎R�̓��A�̒�����ߔN�����̌Õ�������������ꂽ�̂ł���B����͏C�����Ɋւ��镶���������̂ł��邪�A���̒��ɋ�����l�Ɋւ�����̂��܂܂�Ă���̂ł���B�����̌Õ����̐^�U�ɂ��Ă͊w�E�ł͊����̋^�₪������Ă���悤�ł���B���͍��O�\���N�㌎�ɐX�s����̏��̌d���`�ɏ����̍ۂɁA����̐ێ�@�̒h�Ƃ�������l�̌����O���[�v���������Y����̗��K���āA���̌Õ����̈ꕔ�������Ă���������Ƃ�����B�����̌Õ����͌��쌴�s�ыl�i�����Â߁j�̘a�c�씪�Y��������R�̍f�˂̑�Ƃ������ŁA�Y�Ă̊����@���Ă�����ɓ��A���ق肠�āA���̒�����X�̌Õ����A����A����Ȃǂ������Ƃ̂��Ƃł���B�����̌Õ����ނ͍����쌴�s�̑�ɕۊǂ����A�Z�E�J�Ēq�Z�t�ɂ���Đ������������Ă���̂ł���B�O�L���������t�́u������l�̌����v�̒��ɂ����̐V�o�̌Õ������f�ނƂȂ��Ă���̂ł��邪�A�J�Ďt�͑��N�̌����ɂ��A���̐V�o�̌Õ����𒆐S�ɂ��āA�����т���������l�̓`�L�u������l�v�����s�����邱�ƂƂȂ����̂ł���B�{���̎����ƂȂ����V�o�̌Õ����͖{���̕t�^���Ɏ��^�����Ă���B�×��̓`���������L���Ďc���ꂽ�Ǝv���邱�ꓙ�̐V�o�Õ����ނ̎j�I���l�ɂ��Ă͊w�҂̔ᔻ�ɘւׂ��ł��邪�A���ꓙ�̌Õ����ނ��`����ʂ��č������ɏo��悤�ɂȂ������Ƃɂ͏Z��(hy���F���ӃJ�H)���ׂ��ł���B�]�����̍s�ւ�R�炩�ɂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ�����������l�̓����ɉ�����`�����A��̍����t�́u�������l�̌����v�ɉ��āA������̊J�Ďt�́u������l�v�ɉ��āA�i�X�Ɖ𖾂�����悤�ɂȂ������Ƃ͏@��ɂƂ��Ă����ꂵ�����Ƃł���B���a�l�\��N�ɂ͋�����l�̎��S�\�N�̉������}����̂ł���B�D�ӂ̋L�O�o�łƂ����ׂ��ł���B | 22 | �� | �u���a�Q�S�N�a�c�e�q�����̏ꏊ�Ɋւ��鏔���̋L���v�Q�� |
| ���a�O�\���N�@�Ă̈�� | �a�c�씪�Y���Ƌ��Ɏ��B������ƌĂ�ł���Ö����n�̉��@�ƍl�����鎛�@�ՂɎQ�w���܂����B���̎��A���߂Ęa�c���͎��B�ɐ���̓��A�\���A�������@��܂����B���̎��A�����ɒ�����ꂽ��ʂ̐����z���ƂȂ��ė���o���A���̗���̒��ɐ����̏������������ċ���܂����B�����O�O�ɏE���W�߂Ď���Ɏ����ċA��A�ꖇ���K���X�˂ɓ\���Ċ��������A�ǂ�Ō��܂������A�S�����Q���Ă��܂��܂����B �@�����ɏo�ė������ʂ̓��e�͈���Ɍo�ƈ������W�̎����Ȃ̂ł��B�@ �@���̏o���n���蒬�͈��������˂̒n�ł���A���̖{��̂������y�n�ł��̂ŁA�����������ɂ��Ă̌������n�߂��̂͑�w���̍��̏��a��\�ܔN������̎��ł����A���̍��͒Ìy�̗��j�͒Ìy�ˑc�Ìy�אM�ɂ���Ɖ]�����ŁA�X���̗��j���ꕶ����퍑����ȍ~�̋ߐ��j�Ɖ]���l�ȏŁA�Ñ㒆���̗��j�͑S���B���͌Ђ���L�l�ł����B �@�]���āA�����j�̔e�҈��������S�����j�̕\�ʂɏo�ė��邱�Ƃ͖����A���̎������R�����������f�ГI�ł��������A�������������̋���n�ł������̂Ŏ��̒��ɂ͑吳�l�N�i����܁j�\�����s�́w����鎏�x����G�����Ɖ]���{������܂����B�������A���̏����ː����ȍ~�̎��͂悭�킩��܂����A����ȑO�̎����ɂȂ�ƒf�ГI�Œ���̍���Ȃ��_�����X�����܂��B�����Ɉ������֘A�̕��������ꂽ�̂ł��B �@��ɏq�ׂ��V�^����{�ɂ��듡�����[�ɂ���A����ɖ{����u�������ꑰ�𗊂��ēs���痎�����тė������̂ł����B�����ꑰ���́A���܂ł̐��j�ɏo�ė��鎖�Ȃ��X���̗��j����k�����玺�����ɂ����Ă͈Í��̈łɕ�܂�ċ��������ł�����A�ېV�̎O�[�̈�l�Ƃ����g�������[�h�ł���㔼���͕s���Ƃ���ċ���܂��B �@���̗l�ȓV�^����{�A�������[�ꑰ�̊֘A�������o�������̂ɁA�̐S�v�̈����ꑰ�̕������Ȃ������̂ł��B�����Ɉ����ꑰ�֘A�������o�ė����̂ł��B �@�����A���͓V�^����{�A�����ꑰ�A�����ꑰ�̊W������܂łɒ����������A�m���Ă�������a�c���ɐ������܂����B�a�c�������̌�A���̏��֎��Q���Ă���l�ɂȂ����̂��w�������O�O�S���x�ł����B �@��ɔ������ꂽ�k���V�ДŁw�������O�O�S���x�⊪�́g�V�^����ƕ����ɂ��āh�̕��Łu�������̕ێ��Ҙa�c�씪�Y���Ǝ��̏o��͍������\�O�N�O�̏��a�O�\���N�̎��ł����B�v�Əq�ׂ܂������A�a�c���{�l�Ƃ̏o��͏��a�O�\�Z�N�̎��ł����A�w�������O�O�S���x�Ƃ̏o������a�O�\���N�̎��ł���A���a��\�ܔN������������̌������n�߂Ă��������̎��ɂƂ��Ắw�������O�O�S���x���a�c�씪�Y���ł���A������Ɂw�������O�O�S���x�Ƃ̏o��͏Ռ��I�Ȏ��ł�������ł��B �a�c����������l�W�������o�Ă���A�����͓V�^����ƕ����A���|�镶���i�����ꑰ�֘A�����j����͂ɂ��Ď����ė��ċ������̂ł����A���̌�́w�������O�O�S���x����Ƃ��Ď��������Q����l�ɂȂ�A�����w�������O�O�S���x�A�V�^����ƕ����A���|�镶�����݂��̊֘A�����鎖�ł���A���s���Đ�������������i�߂܂����B �@�����A�����̕����̌���������i�߂�ɏ]���āA�����ׂ����Ɏ��̒�����A�a�c���̌��쌴�s�ыl�A�\�O�s�Y���A���C�݈�сi�[�Y���j����Ìy�n���͉]���ɋy���A�X���S��A�H�c�n���A���n���A�X�ɂ͖k�C���씟�ْn�����珼�O�A��m���A�]���ɂ����Ēn�`�A�n���A�_�ЁA���t�A�`�����X�A������Ă��鎖���ƈ�v���鎖�����X�o�ė��܂����B���ꓙ�̎���a�c�����S�ċU�삵���Ƃďo��������̂ł͂���܂���B |
3 | ���{ | |
| ���a38�N (1963) |
���蒬�����R�ێ�@������l750�N�剓���L�O���ƂƂ��āw������l�x�����s����B�i�u������l�v�Ҏ[�ψ���ψ������{���K�j �E���{���K�A������l�������ɓV�^����{�W�L���̂��邱�Ƃ�m��A�씪�Y�Ɏ����̒����߂�B �E�{�W�����̒��Ɉ������W�����������Ă��邱�Ƃ�����A�������W�����������߂�B |
47 | �w������l�x�J�Ēq�Z�i1963�N9���j | |
| ���a�O�\��N�� | �J�Ēq�Z�w������l�x�����E��{�R���㎛�E�@��E�Ŕ��ً� | 23 | �Ŕ� | |
| ���a�O�\��N�㌎��\�ܓ� | �o�Ŕ��s���ꂽ�̂��w������l�x�ł���܂��B | 1 | ���{ | |
| ���a�O�\��N | �ނ���A���̍��a�c���͈�Ԍo�ϓI�ɋꂵ��ł������ŁA�����֏o�҂��ɏo�����ċ���A�w������l�x���o�ł��ꂽ���a�O�\��N�ɂ͓����ɍݏZ���ċ���A�ݏZ��ɏo�ł��ꂽ�w������l�x���������{��������ǂ����ڂ��ċ���܂��B | 1 | ���{ | |
| ���a�l�\�N���܂ł� | ��S���i���j�������Q����܂������A���̒��̈ꊪ�Ɂw�������O�O�S���x�͑S���ŎO�S�Z�\��������ƋL����ċ���A����ɂ���āA�͂��߂āw�������O�O�S���x�̑S�e���킩��������ł��B���̌�A���a�l�Z�N���܂łɖ��S�������a�c���ɂ���Ď��Q����܂����B | 4 | ���{ | |
| ���a�l�\�N�\�� | �ыl�̘a�c����֕p�ɂɒʂ��Ă��邤���ɍ��|��̊W�҂ł���ؑ������A�����ɐ����A���W���Y���A�R���厡���A������ꎁ�A�p�c�`�Y���A�����^�l�Y�����ƒm�荇���l�ɂȂ�A���a�l�\�N�\���ɑ���ڂ̉�������� | 3 | ���{ | |
| ���a40�N�� (1965) |
�a�c�씪�Y�A����ێ�@�W�ҍ��������Y�E�������E���{���K�A�Ɉē�����i����̌A�A�����̌A�j�B��������ˎՒf�n�܂ł��̐�͖����B�i���{���K�k�j ���w�������Z�S���S�x�i1987�N�j�̘a�c�씪�Y�L���u���a22�N���u4�l�ƂƂ��ɒ��R�A�R�̎R��̓��j�E�E�E�v�ɓY�t�̎ʐ^�͂��̎��̂��́B ����51�N���w�s�Y���j�����Ғ��x�O���r�A�ʐ^�́A����A�ł̓��{�B |
47 | ���{ | |
| ���a�l��N������ | �a�c���̒n���ŁA���|��̊֘A�������������ꂽ������A���|��ɊW�̂���l�X�A�����ؑ������A�p�c�`�Y���A���W���Y���A�����ɐ����A�R���厡���A�����^�l�Y���A���쒩�`���A������ꎁ�A���쐳�����A�a�c�씪�Y���A����Ɏ��������č��|��j�Օۑ�����������A���|���j����ׂɁA�y�n�̔����Ƌ��ɊW�����̐��������Ɏ��|���������̂ł����B���̎��ɏo�Ă����̂��w�p�c�Ɣ钠�x�Ȃ̂ł��B | 4 | ���{ | |
| ���a�l�\��N�O�� | �ђ˕���������Ƃ��č��|��j�Օۑ�������������̂ł����B | 3 | ���{ | |
| ���a44�N | ���{���K����Łu�p�c�Ɣ钠�v���o�Ă����B���̌��ɂ��Ċp�c��`���͖쑺�F�F���ւ̃n�K�L�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�O���@�ߓ���˗��̂��������@�����̏o�W��ɂ��āA���{����TEL�ɂĊm�F�v���܂������A�a�c�������̎�����蔭���������̂Ƃ̎��ł����B�����͐V�����Ɍf�ڂ���Ă���ʂ�A���{�������̂��̂ƍl���ċ���܂����̂ŁA�ӊO�Ȋ���v���ċ���܂��B��ϒx���Ȃ�܂��������܂ŁB���X |
10 | �p�c | |
| ���Z�� | �J�Ēq�Z�t�v | 40 | ���{ | |
| ���a�l�\�l�N�㌎ | �p�c�`�Y����瓡�����[���䑜���������ꂽ�ƕ�����A�j�Օۑ���̈ꓯ�ő傢�Ɋ���̂ł��� | 3 | ���{ | |
| ���a�l�\�l�N���珺�a�l�\���N�����܂ł̊� | ���̍��A���|��j�Ւn�̓y�����X�i�n�Ղł��邱�Ƃɖڂ�t�����y���Ǝ҂��j�Ւn�����ēy���̂�v�悪����Ƃ̏����A�j�Օۑ���ł͉�c�̌��ʁA�j�Ւn����邽�߂ɏ��a�l�\�l�N���珺�a�l�\���N�����܂ł̊ԂɁA�j�Ւn�̎�v������y�n���L�Ҍl���甃���グ�Ďj�Ղ̕ۑ����v�邱�Ƃɓw�͂��A���̌��ʁA���|��̒n�`���قڌ��^�̂܂܂̎p�Ŏc�������o�����킯�ł��B | 3 | ���{ | |
| ���a�l�\�ܔN�l����\�Z�� | �g���|��j�Օۑ���h���g���|��j�֕ی��h�ɉ��g����A���|��ɒ��ڊW�̂Ȃ��n���̐l�X����������ɂȂ�ɂ�ď���ω����ė��܂����B���Ƃ��Ă͏o���邾������������Ɏj�ւƂ��Ă̕ی�������������̂ł����A�n���̐l�B�́A������ό������D��Ɍ��т����������悤�Ȃ̂ł��B �@���|����ɂ͓������I����A�x�ߎ��ρA�����m�푈�̒����肪�ȑO���猚���ċ���܂��B���̈⑰�̕��X�̊�]�ŁA���|��̐�v�҂��܂߂����{�����˂������ق𐼊ېՒn�Ɍ��Ă����Ɖ]����]���o�ė����̂ł��B |
3 | ���{ | |
| ���a�l�\�Z�N�� | �w�G���הn�䍑�x�ܓɁA�g���ς̋U�앨�w�������O�O�S���x�����ɏo��܂Łh�Ƃ̕\��ŁA�j���[�X�\�[�X�͂��ׂē����Ƃ����A���悻�w�p�G���Ƃ͎v���ʓ��e�ŁA���U�L�����f�ڂ���Ă���B�w�������O�O�S���x�ɍł��[���g������҂̈�l�Ƃ��āA�����ɐ^���̗��j�A���������̂������𖾂炩�ɂ��Ă��������B �@�w�������O�O�S���x�����̌��Ɋւ��Ắw�G���הn�䍑�x�ܓ��Z�łɓ��쎵�䎁���q�ׂċ����� �u�g�a�c�ƕ����h�����ɏo��_�@�́A���a�l�\�Z�N�̎s�Y�����E���쎡�O�Y���̔��ӂɂȂ鑺�j�Ҏ[���Ƃɒ[����B���j�Ҏ[�ψ����̎R���p���Y�����j���̎��W�ɖz�����邤���ɘa�c�씪�Y���ƒm�荇���A���̉Ƒ��́w����M�d�Ȏj���x�����A�ʎj�҂ɐ旧���āA�����҂̊��s�ɓ��ݐ����̂ł���B���́w����M�d�Ȏj���x�Ƃ����̂��w�������O�O�S���x�������̂ł���B�v �Ɖ]�������{���̎����ł���B |
6 | ���{ | |
| ���a�l�Z�N | ���a�l�Z�N�Ɂw�������O�O�S���x���S���������| �| ���U�����ے肷��V�،� ���������a�l�Z�N�i��1�j�̔N�ŁA���͓����A�k�C���j�̕ҏW�ψ�������Ă܂��āA�����ŕ��������Ɏs�Y���ɍs������ł��B���̎��ɎR���p���Y�Ƃ����i�s�Y���j�j�ҏW�ψ�������܂� �āA���̐l���u���͍����A�a�c����̉Ƃ���w�������O�O�S���x�Ƃ����M�d�Ȏj������Ă�����ŁA���ꂩ�炢�낢�뒲�ׂđ��j�����҂����l���ł���܂��v�Ƃ����悤�Șb������܂��āA���̎��Ɏ��͌��{�������Ă��炢�܂����B�����炭��S������O�S�����炢���A�����������Z�Z���`�̒����A�����܁Z�Z���`���炢�̖̔��ɓ����Ă����Ǝv���܂����A����������Ă��炢�܂����B �@��������������Ă���������ɁA��ԍŏ��Ɋ������̂́A�܂��A��������̋L�^��������Ă���܂����A���̋L�^�͌Â����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���ꂩ��A�n������ȂɌÂ����̂ł͂Ȃ��B�������������̖������̂��̂��Ƃ����������܂����B �@����͉��̂��Ƃ����ƁA�������������̖����ɂ͂�肾�����@�B�D��̘a��������܂��āA���̘a�����g���Ă���Ƃ������Ƃł��B �@���ꂩ�珑�̂������ȍ~�̂��̂ł��낤�ƍl���܂��āA�w�������O�O�S���x�́A���e�͔��ɌÂ����Ƃ͏����Ă��邯��ǂ��A����͂���ȂɌÂ����̂ł͂Ȃ����낤�Ƃ����ӂ��Ȕ��f�����āA���̌�A���̖��͌����͂��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B �@ �|�|�w�������O�O�S���x�͎R���p���Y����̌䎩��Ō���ꂽ�̂ł����B �@ �@�s�Y���̑�����̒��ł��B �|�|���ɂ��ē�S������O�S�������̎��_�Ō���ꂽ�̂ł��ˁB �@�͂��B �|�|����͖����̖����̎��ɁA����������������ɏ����ꂽ���̂ƍl���Ă�낵���ł��傤���B �@�͂��B �|�|���Ƃ��A���ɂȂ��čŋߏ��������̂��Ƃ��A �@����A���������ӂ��ɂ͊����܂���B �|�|���������ӂ��ɂ͌����Ȃ������Ƃ������Ƃł��ˁB �@�͂��B �|�|���̎��A�ǂȂ������Ɉꏏ�Ɍ���ꂽ���͂������܂����B �@������̕ҏW���Ƃ����̂́A�Ȃɂ������ۂ̌W�̌��̕��ɂ���܂��āA�݂�Ȋ�����ׂĂ��܂�������A�����Řb���Ă��܂�������A���ʂȕҏW���Ƃ����`������Ă����悤�ɂ͎v���܂���ł������ǁB �|�|����ꂽ���ɂ́w�������O�O�S���x�Ƃ������O�������̕\���ɏ�����Ă����̂ł��傤���B �@������������Ă����Ǝv���܂��ˁB�ł���R����������̂悤�Ɍ����Ă���ꂽ�낤�Ǝv���܂����A�s���������w�������O�O�S���x�Ƃ����A�s�Y�Ɋւ���L�^���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����B �|�|�n�Ƃ��̖�肩�猩�Ă������吳�̂��̂ƌ����Ă��悢�̂ł��傤���B �@�܂��A�吳�̍��͂ǂ����B���͂�͂薾���̌�����낤�Ǝv���܂��B �|�|�܂���Ԉ���Ă����a�Ƃ����͗L�蓾�Ȃ��Ƃ������Ƃł������܂����B �@���͂܂��Ȃ��ł��傤�ˁB �|�|�悤����ɁA�������̕����ł���Ƃ������Ƃ́A�܂������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł������܂��ˁB �@�͂��B �|�|�ǂ����{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B |
13 | �i�c | |
| ���a�l�\�Z�N�̏H�� | �a�c�����甭�@�����̔�p���o���Ăق����Ɛ\���o�����ƁB �@���̘b�͑��ɂ���������ꂽ���Ƃ��Ȃ����A�]���Č�����o����͂Ȃ��B �@���̌܁`�Z�l�̂ЂƂ��A�܂����{�������z�o�������ƌ������Ƃ������Ă��Ȃ��B���̌��o�Ȃ�����ƌ����āA�a�c���Ƃ����������������ƌ������Ƃ������Ă��Ȃ��B �@�܂��A���ł͔��T���̔��@�����Ă��Ȃ�����A�a�c����Njy���鍪�����Ȃ��B�@ �w�������O�O�S���x�Ǝs�Y���W�҂����t�����ƌ������ƁB �@�w�������O�O�S���x�����߂Č����̂́A���a�l�\�Z�N�̏H���Ǝv���B�ꏊ�͎s�Y������̑������ł��B�����͈�����R�s�[����Ă��玟�̈�����͂�����̂ŁA�����̊Ԋu�͂��Ȃ��₳��Ă���B���̓s�x������A�S���ǂݐ炸�f�ГI�Ɍ��Ă����B �@���̋L���ł͍ŏ�����j���Ɂw�������O�O�S���x�Ə�����Ă����Ǝv���B ���T���Ɍ���x�o�����ӔC����ׁ̈A�w�O�O�S���x�����s�����ƌ������ƁB �@�����i�w�������O�O�S���x�j�͂���܂ł̓��{�j�ɏ�����Ȃ������A���{�������ɂ܂��ɂ߂ċM�d�Ǝv������e�������A�������ʂɌ��J���Đ��_�����N���A���̐^�U�̒����w�҂̌����ɂ䂾�˂�Ƌ��ɁA���{�������̐���̍���ɂ́A�������鍑�ۏ�ɉ��Ă��ꂩ��͐^�ɕ��a�ȍ��ێЉ� �����ׂ̈̐l���m����A�������@���ς��т���Ă��邱�Ɠ��𐢂Ɍ��`�������Ƃ����ړI���������B�ӔC���ꓙ�Ƃ́A�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��B �������̑��o�y�i�����b�B �@���Ƃ��Ĕ�@�̎����͂Ȃ����A���ɂ��������̑����@�ɂ��o�y�i�̂��Ƃ͑S�������Ă��Ȃ��B�]���āA�������o���҂��������ƌ����b�͑S���������Ȃ��B �m�ҏW���n �@���쎁�͎s�Y���������O���\��N���߂��Ă���A�����䌒�݂ł���B���a�l�Z�N�A�����A�C�ȗ��A���j�Ҏ[�ɂƂ肩����ꂽ�̂��c������蕟������Ⓜ����䓙�ɂ܂��`��������Ă������A�ڂ������Ƃ͓�ɕ�܂ꂽ�܂܂Ȃ̂ŁA�y�n�̌ØV���������ɂł��邾���L�^���c���Ă������������ׂƌ����B�̎R���p���Y�������E���Ƃ��Ē��������ɓ����点���̂��A���j�Ҏ[�̎n�܂�ŁA���Ȃ����āw�������O�O�S���x���q�ł���悤�ɂȂ�A���̖L�x�Ȏ�������u���Ă����̂��ܑ̂Ȃ��ƍl���A���j�����҂Ƃ��Ċ��s���邱�Ƃɓ��ݐ�ꂽ�̂ł���B �@���T���̂��߂Ɍ�����x�o�����ȂǂƂ����w�G���הn�䍑�x�̋L���́A���������̒����ł���B���̌���x�o�������Ȃ�A�L�^���c����Ă���͂��ł���B�c��̏��F���Ȃ�����̂悤�Ȏx�o���l�Ō��߂�����̂ł��Ȃ��B�w�G���הn�䍑�x�̋��U�L���͊w��Ƃ͖����A�S���̖��ӔC�ҏW�ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B |
12 | ���� | �u�Óc�j�w���v�Ɍf�ڂ��ꂽ�u����،��v�ɂ��āA���̔��쎁���g����Ƀj���A���X�̈Ⴄ�b�����Ă���B���s�Q�ƁB |
| ���a�S�U�N�̏H�� | ��������w�������O�O�S���x���a�c�씪�Y���̕M�ՂłȂ����Ƃ����l���������A�{���̂��̂��ǂ���������Ȃ�����ǂ��A�Ƃ��������s���āA���̐^�U�ɂ��Ă͊w�Ґ搶�ɔ��f���Ă��炨���Ǝv���A���N�����̈Ӗ���������s�ɓ��݂�������ł��B�����A�s�Y���j�����邽�߂ɘa�c�씪�Y����o�Ă��鎑���̃R�s�[�̂��߂ɐ��S���~�͎x�������Ǝv���܂��B �w�Óc�j�w���x�ɂ͕����ʼn�����ł�����ǁA�i�f�ڂ��ꂽ���̂́j�j���A���X�I�Ɉ���Ă��āA�����s���悭�܂Ƃ߂�ꂽ�Ƃ��������ł��B�����ǂ��A���͗��j�Ƃł��Ȃ�ł��Ȃ��̂ŁA����܂肱������Ă͂���܂���B�a�c�씪�Y�����A���낢�낢�Ƃ��������ȌÕ����Ă���Ƃ������Ƃ́A�܂��{���ł��傤�B�ǂ����炩�d���ꂽ���̂��Ă���Ƃ������܂����B�ނɂ͂���Ȃ��ƌ����Ɠ{�邩�猾����ł��B |
17 | ���� | 115�� |
| ���a48�N12��25�� | �w�ԗ͑��j�x���s | 7 | �u�������O�O�S���v�̈ꕔ�����p����A���ꂪ�s�Y���j�����҂̊��s���}���������R�ƌ�����B | |
| ���a48�N (1973) |
�a�c�씪�Y�A�s�Y�����}�_�ЂɁu�z�v�����B�����ҐR���l�Y�E�s�Y������ψ���̕��X�B | 47 | ||
| ���a�\�N�l�� | �s�Y���w�������O�O�S���x�͏㊪�����a�\�N�l���ɔ��s���� | 5 | ���{ | |
| ���a�T�O�N�`�T�Q�N (1975-1977) |
���{���K�a����́u�������O�O�S���v200�����̒������100�����s�Y���ɑ݂��o���B | 47 | �w�s�Y���j�����ҁx�㒆�����A�N�\�i1975�N10���`1977�N�j | |
| ���a�\��N�\�� | �g�����Ȃ�̉Ɓh���݊����A���݊W���Z�����o���� | 3 | ���{ | |
| ���a�\�O�N | �g���|��j�֕ی��h���Вc�@�l�Ƃ��Č܌�����t�Ō�����ψ����F���A�����\�O���ɂ́g�Вc�@�l���|��j�֕ی��h�Ƃ��Ė@���ǂɉ��Đݗ��o�L���I�����܂����B | 3 | ���{ | |
| ���a55�N9�� | �r�e�f�_�ЎГa���� | 31 | �a�c | |
| ���a55�N (1980) |
�Γ��R�_�ЎГa�����B�H�c��G���K�A�Γ��R�ɎQ�q�B�i9���j �E�a�c�씪�Y�A���̂��납��e���r�o���E�u���E�{�̎��M�����b��̐l�ƂȂ�B �@�e���r�o���F��̂���͂������iNHK����j �@������ƊC���R���L���iNHK�����j �@�݂��̂������X���i�L�l�}�����j |
47 | �w���|��j�������\�x �w�������ڈΉ����x �a�c�씪�Y�@�i�Ìy���[�j |
|
| ���a56�N (1981) |
���{���K�A�咰�ǂ̂��ߓ��@��p����B | 47 | ||
| ���a56�N�T��28�� | �a�c���s���� | 48 | ||
| ���a58�N���t | ���́A�Ìy���[�i�{�ЁE�X���O�O�s�j��\�̍������ꎁ����A��Ԃ�̌��e��n���ꂽ�B���ꂪ�A�u���������v�Q�A�܂��́A�u�a�c�ƕ����v�Ƃ̊ԐړI�ȏo��ł���A�����ł������B | 14 | �R�� | |
| ���a58�N6��24�� | �a�c�씪�Y�w�������ڈΉ����x�Ìy���[��芧�s�B | 14 | �R�� | |
| ���a58�N�`61�N (1983-1986) |
���{���K�A�v�ۉF��q�̗��K����i���{�W���Y�v�l�̈˗��ɂ��u���{�ƌn���v���쐬�B�@�C�ȑO���m�F�̂��߁j�B���{���K�A�a�c�씪�Y���Љ�B�a�c�씪�Y�A�v�ۉF��q���u���{�ƌn���v�����쌴�s���}���قɊB�i1986�N�j | 47 | �w�������O�O�S���x���ڒ��O�E���{���K��1�`6���i1983�N12���j �⊪�i1986�N12���@�k���V�Ёj �w�������Z�S���G���S�x�R��♉�ҁi1987�N7���@�Ìy���[�j |
|
| ���a58�N12���`���a61�N���� | ���ْ��O�A���{���K�ҁw�������O�O�S���x�k���V�Ђ�芧�s�B�S���� | 15 �^ 32 |
||
| ���� | �������A�a�c�씪�Y�����g�A�k���V�ДŁw�O�O�S���x�Z���ɕt���ꂽ�u�w�������O�O�S���x�̎j���ɂ��āv�ł́A�u�J�Ēq�Z���̕ҏW�Ŋ��s���ꂽ�w������l�x�̎������A�w�������O�O�S���x�̏�l�W�̂��̂��g�p�����̂ł��v�i�S�y�[�W�j�ƒf�����Ă���B | 35 | ���� | ���A�ȂǓy�����������l�W�̎j�����o�������Ƃ������a24�N�̔���杂Ƒ��e��Ȃ��L�q�ł���B |
| ���a59�N3��29�� | �ؑ������A���� | 28 | ||
| ���a60�N10��26�� | NHK�������ƊC���O���L���\�k�̊C�m�����A�X���A�\�O�Σ | 49 | ||
| ���a60�N12�� | �a�c�씪�Y�A�Ìy���[�E������\�Ɂw�������Z�S���G���x���e���������ށB | 14 | �R�� | |
| ���a�Z�\�N�\��� | �w�������Z�S���G���@�S�x�����@�a�c�씪�Y�u�w�������Z�S����v�x�ɂ��āv | 31 | �a�c | |
| ���a61�N4��10�� | �w�������Z�S���G���@�S�x�Ìy���[��芧�s�B | 14 | �R�� | |
| ���a62�N7��1�� | �a�c�씪�Y�w�m��ꂴ�铌�������������x���s/���������R�Ñ㒆����ՐU����s | |||
| ���a62�N7��1���`8��31�� | �u���{�E�����E�H�c�����W�v���쌴�s���}���� | 27 | ||
| ���a62�N7��20�� | �w�`�S�@�������Z�S���x�Ìy���[��芧�s�B | 14 | �R�� | |
| ���a62�N (1987) |
�a�c�씪�Y�A�u���{�E�����E�H�c�����W�v�J�ÁB�i7��1�`8��31�j �H�c��G�A���{�W���Y�v�ȗ��K�B�Γ��R�֎Q�q�B�i7��30���j |
47 | �w�m��ꂴ�铌�������������x�a�c�씪�Y�i1987�N7���@���������R�Ñ㒆����ՐU����j �w�`�S�������Z�S���S�x�R��♉�ҁi1987�N7���@�Ìy���[�j |
|
| ���a63�N (1988) |
�Óc���F�A�Γ��R�����n�����B | 47 | ||
| ���a64�N1���`����2�N9�� | �������X���w�������O�O�S���x�S�Z�����s | |||
| �������N5��12�� | �a�c�씪�Y�w�m��ꂴ�铌�������������x����Ŋ��s/�������X���s | |||
| �������N (1989) |
�a�c�씪�Y�A�ߐ�V���|�W�E���ɏo�ȁB�i9���j | 47 | �w�������O�O�S���x�S6���@���������R�j�Օۑ���ҁi1989�N�@�������X�j �w���쌴�s�Ɠ��k�Ñ㒆���j���x���R�j�Օۑ���E�a�c�씪�Y�i1989�N10���j �w�������Z�S�ꕔ�^�x�a�c�씪�Y�ҁE��i�������X�j |
|
| �������N11�� | �w�������Z�S�ꕔ�^���������撠�x�������X��芧�s | 14 | �R�� | |
| ����2�N (1990) |
�a�c�씪�Y�A�V���|�W�E�������쐬�B�i3���j �a�c�ƓV�䗠�ɂ������Ō�̈ꔠ�����J�B���{���K�A�����W���s�̂��߁A�ꕔ��a�c�씪�Y�����B�i4���j ���̓~�씪�Y�A�X�m�[���[�r���ʼnE�r���܁B |
47 | �w�������Z�S����v�x���������R�j�Օۑ���ҁi1990�N1���@�������X�j | |
| ����2�N4�� (1990) |
���c�����a��ȑ�w��E | 37 | ���c | p198 |
| ����2�N6��19�� (1990) |
�Óc���F�w�^���̓��k�����x���s�@�s�X���o�� | |||
| ����2�N8��4���`12�� | ����1990�N8��4���`12���̐X�������s�ɂ����āA���������a��ȑ�w�����j�������͑����̊w���̎��n�邱�Ƃ��o�����B | 36 | ���c | |
| ����3�N3��25�� | ���̒������ʂ͗������O�N�O����\�ܓ����́w���a��ȑ�w�I�v�x���܍��ɁA���u�H�c�ƕ����ɂ�����V�����v�i�Óc�E���c�����j�Ƃ��Čf�ڂ��ꂽ�B�܂��A�����ɂ͐٘_�u�k�C�̃��}���h�v���f�ڂ���Ă���B����ɁA���̌���a�c������͏������Ă��������J�j������w���ĂɊ��x�ɂ��킽���ėX������Ă����B�������͂�����R�s�[�ɂƂ����ł͂Ȃ��A����w�̒����쑢�����̋��͂āA�������ʐ^��d�q�������ʐ^���Ƃ�A����ɂ͕ԑ����̎��m�F�Ƃ����`�Řa�c���̕M�ՃT���v���������肵���̂ł���B | 37 | ���c | |
| ����3�N6��8�� | ���͓��{�Ȋw�j�w���i���E�}�g��w�j�ɂāA�������\���s�����B�\��́u���쎞��̓��{�ɓ`�������r���t�H���̉F���_�v�A���e�͘a�c�Ǝj���Q�Ɋ�Â��t�����X�̔����w�҃W�����W�����r���t�H���i�a�c�Ǝj���Q�ɂ�����u�g�ѐl���C�X�v�j�̉F���N���_�������O�N����A���łɓ��{�ɏЉ��Ă����Ƃ�����̂ł���B���̔��\�̌��ʂ͎S�邽����̂ł������B���̏o�Ȏ҂��A�a�c�Ǝj���Q�̉F���_���r���t�H����G���Y�}�X���_�[�E�B���̎���̂��̂Ƃ͎v���Ȃ��قnj���I�ł���A����l�̋U��Ƃ����v���Ȃ��Ƃ����w�E���������̂ł���B���̔��\�͂��܂��o�Ȃ��Ă���ꂽ�J�{�Ύ��̏��͂āA�悤�₭���E�����B�������A���ƂȂ��Ă͒J�{���ɑ���̂Ɠ��l�ɁA���̂����A�a�c�Ǝj���Q�ւ̋^�f��\�����ꂽ�o�Ȏ҂̕��ɂ����ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B | 38 | ���c | |
| ����3�N6��18�� | �Óc���F�w��B�����̗��j�w�x���s�@�s�X���o������𒀈ꌟ�����钆�ŁA�]���̐��]�ɔ����A���̒��Ɂu�U���̂��������v�̕З����o���ʂ��Ƃɋ������B�������A�F�G���g�̗��j�ς̒��ɂ́A�ߐ��̊w�҂Ƃ��Ă܂ʂ��������Ȃ������A�����̌���͑�������̂́A���̏��ʁE�����̒��ɂ́A��Ƃ��āu�݂�����A������j���ɔƒm��A���ɐ^���ƐM�����߂Ƃ���v�悤�ȉӏ��A���̈�Ђ��������������Ȃ������̂ł���B |
30 | �Óc | |
| ����3�N8��1�� | �s���Ñ�j�̉�ҁw�Ìy����Ђ炭�Ñ�x�V��Ђ�芧�s�B���̋U����͍������A�a�c�Ǝj���Q�̎j���I���l���w���ʂɔF�m�����ɂ́A�T�d�Ȏj���ᔻ�����肩�������K�v�����邾�낤�B���������������a��ȑ�w�����j������(�����E�Óc���F)�𒆐S�Ƃ��钲���̌��I�ł́A�]���̋U����̍����ɂ͂��Ƃ��Ƃ���������Ă���A�������Ă��̊����`�����������𗠕t����؋������X�ƏW�܂����v(�u�A���n�o�L�̌����Ƒ匳�_�M�K�v) |
39 | ���c | |
| ����3�N9��1�� | �u�Ñ�M���V���Օ��v�̏Ռ� �^����ɗ����Č�����i�߂Ă����������ɂƂ��ăV���b�L���O�ȕ��Ȃ��ꂽ�̂́A�V���|�W�E���u�הn�䍑�v�O��_���̒���̂��Ƃł���B�a�c�����珺�a��ȑ�w���ɑ����Ă��������J�j���̈�A�u�Ñ�M���V���Օ��v���Óc�����u����ȂǂŏЉ���Ƃ���A���u�҂̊Ԃ��A���ꂪ��g���Ɂw�M���V���E���[�}�_�b�x�i�u���t�B���`���E���퐶�q��j�̈����ʂ��ł���Ƃ����w�E���Ȃ��ꂽ�̂ł���B ���̒��u�҂̈�l�A����F�v���͕����O�N�㌎����t�w�s���̌Ñ�j���[�X�x�㎵���ɂāA���̖�����A�a�c�Ǝj���Q�̐M�ߐ��Ɋւ���^�O��\�����Ă���B |
41 | ���c�^���� | |
| ����3�N9�����납�� | �Óc���́A���������^����𖾂��邽�߂ɂ́A�܂��j���̑S���J�ƁA�ۊǏ̊m�����K�v�ł���Ƃ��āA���N�㌎���납��A�a�c���ɂ��������̎j�����J��]�ވ���ŁA�j���̎����ƂȂ肤��e�c�̂ւ̓����������������B | 42 | ���c | |
| ����4�N(1992) | ���{���K�ҁw�a�c�Ǝj���T�@���B���y�L�E�����j���y�L�E�N�Г��{�L�S�E�N�Г��{�j�����E�N�Г��{�G�L�S�x�k���V�Ђ�芧�s | |||
| ����4�N (1992) |
47 | �w�a�c�Ǝ����P�x���{���K�i1992�N8���@�k���V�Ёj | ||
| ����4�N8��8�� | �l���_�Ќ�_�̒����� | |||
| ����4�N10��5�� | �a�c�Ǝj���Q�̌����J����Ă���ʖ{�͖������ȍ~�̂��̂ł���A���̒��ɂ͏��ʎ҂ɂ����M��ҏW�̍��Ղ����邽�߁A���̋L�q�̂��ׂĂ��j���Ƃ��ĉL�ۂ݂ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B���ʎ��̉��M�Ȃǂ͖��Ԃ̑p���ɂ��肪���Ȃ��Ƃł���A������ȂċU�������ɂ���̂͑��v�ł��邪�A�j�������̍�������邱�Ƃ͔������Ȃ��B | 43 | ���c | |
| ����4�N10��21�� | �쑺�F�F���A�ʐ^���p�E�_�����ނ̌��ŐX�n�قɑ��Q���������̖����i�ׂ��N�����B�퍐�́w�������O�O�S���x�̋U��ҁE�a�c�씪�Y�Ȃ�тɁA���̒����̔Ō��ƂȂ����������X�i���Ђ́w�������O�O�S���x�̃e�L�X�g�����s���Ă���j�ł���B | 17 | 145�� | |
| ����5�N1���� | �Óc���͊w���l���ɂ��Đ�����������ɂ��āA�����Ґ�����q����ƌ������Ă����B�����N��\����t���Ńt�@�b�N�X�Ə����ɂđ��������Ȃɂ����āA�����Ґ�����q����̂Ȃ�A鰐W���Z�����̐��ۂ�a�c�Ǝj���Q�̐^��ȂǁA�����Əd�v�Ȗ�肪����͂����Ƃ����|�A��\����������ɑ���Ԏ��������������Ƃ͂Ȃ������B | 44 | ���c | |
| ����5�N3��22�� | �X�Õ���������ɂ��u�a�c�씪�Y���̏��ȋy�ѓ������ւ�����������ɑ���ӌ����v | 16 | ���̊Ԃ̏ڍׂȉߒ����u�u���_�ٔ��v�ߒ��ł̋U���_���v�Q�� | |
| ����5�N3��31�� | ���c�����A���a��ȑ�w���E�B | 40 | ���c | |
| ����5�N6��1�� | �uNHK�i�C�g�W���[�i���v | |||
| ����6�N | ���{���K�ҁw�a�c�Ǝ���2�@�N�Г��{�L�@�N�Г��{�I�@���V�{�j�T�x�k���V�Ђ�芧�s | 33 | ||
| ����6�N (1994) |
�w�a�c�Ǝ���2�x���{���K�i1994�N7���@�k���V�Ёj�@(hy���F�����͈��p���ł́u�o�Ŗ{�v�̍��ڂɂ�����A���̕\�̕ҏW��A���̗�ɕ\�L�j | 47 | ||
| ����7�N2��21�� | �X�n�ٔ����B | |||
| ����7�N (1995) |
���{���K�A�S�������̂��ߓ��@�B�@(hy���F�����͈��p���ł́u�o�Ŗ{�v�̍��ڂɂ�����A���̕\�̕ҏW��A���̗�ɕ\�L�j | 47 | ||
| ����9�N1��30�� | ��䍂�ٔ����B | |||
| ����9�N12��28�� | ���{�S���ɏ��ď��r�������ݍ�����Õ����ɂ͍X�ɊC���u�R�v�u�I���G���g�v�̌Î��ɂ��ӂ�ċ���܂��B | 11 | �a�c | |
| ����11�N1��26�� | 1999�N1��26���A�e���r�����́w�J�^�I�Ȃ�ł��� ��c�x�ɁA�u���쌴�s�̐_�傳��v�i�a�c�씪�Y�̂��Ɓj�Ɂu�Õ����v���������A�����ɋL���ꂽ�̔��@��p�Ƃ������Ƃ�130���~���o�������Ƃ��� �l�����o�ꂵ���B���������ۂɂ͔��@�͍s���邱�ƂȂ��A�u�_�傳��v�͑㉿�Ƃ��ĎՌ���y���n�����B���ԑg�ł́A���̓y�Ӓ肳�ꂽ�킯�����A���ʂ́u���y�Y�p�ɍ��ꂽ�͑��i�v�A�����l�i��1���~�������B������A���̐l�����x���ꂽ���Ƃւ̓���݂̋��z�ł���B | 45 | ���c�^�� | |
| ����11�N | �E�a�c�씪�Y���@�i�āj �E�a�c�씪�Y�����B�i1999�N9��28���j �E���{���K�E�|�c�Ўq�A�a�c�F�i�씪�Y���j�j�E�a�c�͎q�i�씪�Y�����j���A�u�a�c�ƕ����v��̏�����B�i12���j |
47 | ||
| ����11�N9��28�� | �a�c�씪�Y���A�����B�����r�ꎁ�́u���{���̌����i�[�u�������O�O�S���v�Ɋւ����l�@�[�v�ɂ��ƁA�u1999�N9��28���ɓˑR�a�������v�ƌ����B | 8 | ||
| ����11�N11�� | �Ȃ��A�a�c�씪�Y�̂��Ƃ��͂�����u�ܗ��̍��\�t�v�ƌĂl��������B�N���낤�A���{���K���̖��ł���A�����g�A�u�a�c�ƕ����v�̐^����_�҂ł���|�c�Ўq�����B���K��́A�a�c�씪�Y���g���\��O�h�ƕ]���Ă����B�����Ƀo����R�����̏�̎v�����Ńy���y�������B���O���́g�씪�Y�͉R�������Γ��R�͖{������h�Ƃ������Ă����B�Z���K�����\��O�Ƃ܂�Őߑ��̂Ȃ��씪�Y��m��Ȃ���w�������O�O�S���x���͂��߂Ƃ���a�c�ƕ����ɂ̂߂荞��ł������̂́A�a�c�씪�Y�̏���������̂ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă�������ł���B�g���l�甪�S�\�����h�ƋL�����a�c�ƕ�������������قǁA�a�c�씪�Y�͓V�˂ł����l�ł��Ȃ��B�܂��Ă�ܗ��̍��\�t�ɏ���������̂ł͂Ȃ��B�E�E�E�a�c�씪�Y�͑łĂ�����ł����̏o��s���̐l�ł��� |
46 | ���c�^�|�c | |
| ����12�N (2000) |
�E�a�c�Ƃ��q�i�씪�Y�����j���@��p�B�i�t�j �E�a�c�F���@�B�i�āj�މ@10���B �E���{���K�������@�B�i10���j |
47 | ||
| ����13�N (2001) |
�E�Γ��R�_�ЂɂāA���{���K�E���{���L�i���K���j�j�B�|�c�Ўq�A�a�c�F�E�a�c�͎q��蕶����B���{���K��։^�ԁi9���j �E���{���K���@�B�i10�����{�j �E�Óc���F�A�a�c�ƁE�Γ��R�_�В����Ɓu�a�c�ƕ����v�m�F�̂��ߗ��K�B���{���K���@���̂��߁A�|�c�����s�B |
47 | ||
| ����14�N (2002) |
�a�c�F���@�A�����B�i9��27���j | 47 | ||
| ����15�N (hy���F17�N�̌�B�ȉ��J�艺��) (2005) |
�E���{���K�A�u�a�c�Ǝ���3�v�k���V�Ђ֓��e�B�i8���j �E�u�a�c�Ǝ���3�v1��ڍZ���r���A���{���K�����B�i10��21���j �E�|�c�Ўq�A�Z���K�̎d�����p���B |
47 | ||
| ����17�N10��21�� | ���{���K���A�����B���N75 | 34 | �� | |
| ����18�N (2006) |
�E�w�a�c�Ǝ���3�x�����B�i2���j �E���{���K�ƍ��~�L�������ɂɎ��[����Ă��������ނ̐������ɁA�ꌩ���Ċ������{���A�Ǝv���鏬���q��������B�����ɓ��ɂ��������������܂߂Ďʐ^�E�R�s�[���Óc���F�֑���B�i5���j �E�����q�Z�~�i�[�n�E�X�؍݂̌Óc�̂��Ƃ֏����q�E�V���ƕ��������܂ގ��������R�O�_�]��͂���B�i11��10���j �E���~�L�������ɂɕۊǂ���Ă��������ނ̒�����A�ߐ������ƍl��������̐��_��lj����B����B�i11��25���j |
47 | �w�a�c�Ǝ����R�x���{���K�ҁi2006�N2��1���@�k���V�Ёj | |
| ����19�N (2007) |
�E�Γ��R�_�ЂŎ���������̐������ɁA�v���ӏ��Ƃ��ă`�F�b�N���Ă����������q�P���̂��邱�Ƃ��v���o���A����B�i2��1���j �E�G���w�Ȃ������x�����B�i6���j �E�w�a�c�Ǝ���4�x�����B�i7���j |
47 | �w�a�c�Ǝ���4�x���{���K�ҁi2007�N7��10���@�k���V�Ёj |
���u�������O�O�S���v���̂��̂ɂ��ẮA�u���S�l�\���]�v�ƋL����Ă���i�����ꑰ�V�̎����r�v�j�E�E�E�Óc���F�u���k�̐^���|�a�c�ƕ����T�ρv�w�V�E�Ñ�w�x��1�W38��/1995�N�B
���u�a�c�ƕ����v�Q�̑S�̂ɂ��ẮA�u���l�甪�S�\�����ɑ��ʂȂ�v�i�u�k�l���v��\���A�L�����j�E�E�E����B
| 1 | �Óc�j�w���1995�N2��26���@No.5�u�a�c�ƕ����Ƃ̏o��i1�j�v | ���{ |
| 2 | �Óc�j�w���1995�N4��26���@No.6�@�a�c�ƕ����Ƃ̏o��i2�j | ���{ |
| 3 | �Óc�j�w���1995�N6��25���@No.7�@�a�c�ƕ����Ƃ̏o��i3�j | ���{ |
| 4 | �Óc�j�w���1995�N8��15���@No.8�@�a�c�ƕ����Ƃ̏o��i4�j�@�w�p�c�Ɣ钠�x�͎ʂ̂������� | ���{ |
| 5 | �Óc�j�w���@1995�N10��30���@No.10�@�a�c�ƕ����Ƃ̏o��i5�j�@�R���V���@�����Ɓw�������O�O�S���x�̈�v | ���{ |
| 6 | �Óc�j�w���@1994�N12��26���@No.4�@�w�������O�O�S���x�����̂������� | ���{ |
| 7 | �ԗ͑����ꊧ�w�ԗ͑��j�x | |
| 8 | ���{���̌����i�[�u�������O�O�S���v�Ɋւ����l�@�[�@���{���ۋ���w��@1999�N11��7���@��10����i���j���s�E���u�Б�w | ���� |
| 9 | �Óc�j�w���@1995�N6��25���@No.7 �C���^�r���[ �a�c�Ɓu������l�j���v�����̂������� | �������� |
| 10 | �w���j�ǖ{�x���a45�N�V�t���卆�u���W�킪��킪���@���j�j���[�X�v�@�w�G���הn�䍑�x52��31�� | |
| 11 | �Óc�j�w��� 1997�N12��28���@No.23 �u���فu�U��v�ٔ����i�ɂ悹�� �U���_���L�[���[�h�ɂ����ҒB�Ɉꌾ�v | �a�c |
| 12 | �Óc�j�w���@1995�N4��26���@No.6�@�w�������O�O�S���x�����̐^�� | �X���E�s�Y���������@���쎡�O�Y |
| 13 | �Óc�j�w���@1996�N10��15���@No.16�@���a�l�Z�N�Ɂw�������O�O�S���x���S���������| �| ���U�����ے肷��V�،� | �i�c�x�q�i���O���j�ҏW�ψ��j |
| 14 | �w�G���הn�䍑�x55���u�w���������x�Ƃ̑����ƌ��ʁv | �R��♉� |
| 15 | �w���܂����ȓ��k�l�x258��/�{�̐X | |
| 16 | �����@�w�G���הn�䍑�x51��18�Ł` | |
| 17 | �S�e�Ёw���{�j����Ȃ��x | �X���E�s�Y���������@���쎡�O�Y |
| 18 | �u�T�����F�v���a27�N8��14���u�R���^���ыl�R�̔閧�@���߂Ė���H�R���̊J�c�@���m�s�ҏI����̒n�H�@�N�ɑ����鍑��Ձv | |
| 19 | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x208�� | |
| 20 | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x288�� | |
| 21 | ���������w�}���̐��ҁ@�����O���̎n�c�@������l�̌����x133�� | |
| 22 | �J�Ēq�Z�w������l�x�u�����v | ��y��呍�{�R�m���@��Ձ@�ݐM�G |
| 23 | �J�Ēq�Z�w������l�x�u�����v | ��{�R���㎛�E�@��@�Ŕ��ً� |
| 24 | �w�T�����F�x���a27�N8��14���� | |
| 25 | ���m�呠�w���y�j���ٕ����k�x�u�͂������v | ���m�呠 |
| 26 | ���m�呠�w���y�j���ٕ����k�x�u�����ɏ�����������v | ������ |
| 27 | �w�G���הn�䍑�x52�������O���r�A | |
| 28 | �w�G���הn�䍑�x52��121�� | ���쎵�� |
| 29 | ��������@���a��\��N�\�l���u�ܔN�O�A�a�c�e�q�������v | |
| 30 | �Óc���F�w��B�����̗��j�w�x���s�@�s�X���o�Ł@426�� | �Óc���F |
| 31 | �w�������Z�S���G���@�S�x�����@�a�c�씪�Y�u�w�������Z�S����v�x�ɂ��āv | �a�c�씪�Y |
| 32 | ���{���T�w�������O�O�S���u�U���v�̏ؖ��v����6�N1��15�����Ŋ��s�@2�Ł` | ���{���T |
| 33 | �w�V�E�Ñ�w�x��1�W�@�u�������O�O�S���Ƃ́@�a�c�ƕ������������v | �É�B�� |
| 34 | �Éꎖ���ǒ��̗������O���L ��39�b�@2005/10/25 �́E���{���K����̂��� | �É�B�� |
| 35 | �w�G���הn�䍑�x52��123�ŁA���쎵��u���`�g�a�c�ƕ����h�̎j���I���l�ɂ��āv | ���쎵�� |
| 36 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x12��/1995�N5��25��/��]�Њ� | ���c�� |
| 37 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x218�� | ���c�� |
| 38 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x220�� | ���c�� |
| 39 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x221�`2�� | ���c�� |
| 40 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x227�� | ���c�� |
| 41 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x225�� | ���c�� |
| 42 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x225�`6�� | ���c�� |
| 43 | ���j�}�K�W�����Ɂw�k���̊y���݂��̂��̉����x�f�ځu���{�̃A�g�����e�B�X[�\�O��]�v | ���c�� |
| 44 | ���c���w���z�̒Ìy�����@�w�������O�O�S���@�̖��{�x227�� | ���c�� |
| 45 | ���c���u�w�������O�O�S���x�ߔN�̓����i2005�N���ӂ肩�����āj�v�o�T�w�G���הn�䍑 93��2006�N10���x | ���c�� |
| 46 | ����@�o�T�w�k�������x��20���@�|�c�Ўq�u�a�c�ƕ����͘a�c�씪�Y�̏������U���ł͂Ȃ��\��B���{�@�C�`�����߂����ā\�v | ���c���^�|�c��q |
| 47 | �u������[���E�O]�O�S���@���ɏo���A���̊������{�I�v | �Óc���F�E�|�c�Ўq |
| 48 | �w���{�j����Ȃ��I�x89�� | ������ | 49 | �w���{�j����Ȃ��I�x224-225�� | ������ | 50 | �w���ς̓��k�����@���j���䑢����l�����xp86 | ���{���T |
���Q�l�T�C�g�F���c���u�u�H�c�F�G�v�Ƃ͉��҂��H�v���́u���e�Ƃ̊����H�v1998�N10��
��#45��o�T�w���{�j����Ȃ��I�x�`����Ƃ��Ă��������ɕt���A2022/1/27�w�G���הn�䍑�x�֕ύX�B