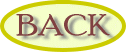
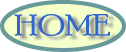
古田武彦さんを悼む以上出典)古田史学の会編『古代に真実を求めて 古田史学論集第十九集 追悼特集 古田武彦は死なず』19-20ページ/2016年3月25日/初版第一刷発行。
学校法人旭学園理事長、考古学者 高島忠平
「『邪馬台国』はなかった」。古田武彦さんのこのフレーズは、私にとってショックだった。古田さんは、一九六九年に史学雑誌(注1)、七一年に単行本(注2)を出され、現存する 『三国志』「魏志倭人伝」のすべてに「邪馬臺(台)国」ではなく「邪馬壱国」とあり、邪馬壱国はあっても邪馬台国はないと主張したのである。
魏志倭人伝を中心に独自の文献考証を行い、邪馬壱国は現在の博多湾岸地域にあったとされた。在野の研究者の一説であるにしても、邪馬臺(台)国と当然のように理解して、近畿(畿内)か九州かを軸に各説を戦わせていた論争に大きな波紋を投じた。後に三種の神器も博多湾岸の弥生文化にみられると考古学的に自説を補強された。
当時、私は奈良国立文化財研究所に在籍していて、所内の研究会で邪馬台国九州説を主張し、先輩研究者たちにこてんばんに批判された。負けん気が強い私は考古学界を圧倒する邪馬台国近畿説に対抗できる九州説を構築しようと考えをめぐらせていた。
当然、私は邪馬台国(ヤマタイコク)と疑わず、私の九州説を厳しく批判した先輩たちもヤマタイコクであった。
考古学アカデミズムは古田説を無視するか、関心を示そうとはしなかった。古代史研究者からは、邪馬壱国の「壱」は「臺」の誤記で、やはり「邪馬台国」と読むべきだと反論もあった。これには 『日本書紀』が語る日本古代国家生成の主体とされる、奈良の「ヤマト」が考古学・古代史研究者の先入観(注3)としてあったことは否めない。
太宰府天満宮に伝来する 『三国志』など中国の歴史書を書写した九世紀の「翰苑」(注4)(中国の最古の木刻本「三国志」(注5)よりも古い)には、「伊都に至る。又南して邪馬臺国(注6)に至る」とあり、邪馬壱国を「邪馬台国」と読んでいる(注7)。しかし、邪馬壱国はまったく否定されるものではなく、「卑弥呼の都するところ」として、その可能性は検討されるべきだろう(注8)。 古田説は、古代史に関心がある市民や、歴史学とは別分野の研究者には説得力を持っていた。今もって人気があり、数年前に福岡県が主催した「邪馬台国」シンポジウムで、聴衆に最も多く支持されたのが「邪馬台国?」福岡市説であった。
古田さんはさらに「多元的古代史観」を提唱され、古代の「九州王朝」の存在を主張された(注9)。日本書紀や考古学・古代史研究者の大勢にある 「一元的なヤマト王権による列島の支配・統一」への対極の古代史観であった。
私は多元的古代史観に共感している(注10)。古田さんの描く九州王朝説をそのままは受け入れられないが(注11)、「地域史観」を持っている。私も列島各地に弥生時代から古墳時代にかけてツクシ・キビ・ヤマト・イヅモ・ケヌといった独自に王権が生成される状況を見てとっているからである。古田さんは、既成の歴史学に対して、他にも多くの問題・課題を提唱され、「古田史学」を確立された。
古田さんは発掘されて間もない吉野ヶ里遺跡を訪れ、一書を出されている(注12)。私も邪馬台国のフォーラムに呼ばれたことがある。自説は確固として、激しく主張されるが、他説には謙虚に耳を傾けておられた(注13)姿が印象的であった。
古田さんは、もともとは思想史が専門で、親鷲の研究で知られている。既成の日本仏教に反旗をひるがえし、仏教に革命をもたらした親鷲と古田さんの間には、共通して常識、定説、既成の権威に対する絶えない疑問と反抗心(注14)があったように思う。冥界で出会った2人はどんな論争をしているのだろうか。
ご冥福を祈ります。(「西日本新聞」 二〇一五年十一月四日朝刊より転載)
私のインタビュー記事の題として「吉野ヶ里は邪馬台国だ」〈週刊文春4月13日号〉とあったのは、編集部のワーク。それを“うけて”わたしの説が「吉野ヶ里=邪馬台国」説であるかのように紹介したものもあった。〈月間ASAHI創刊号、佐原真氏〉しかし、件の『週刊文春』1989年4月13日号では、古田氏自身以下のように書いている。
「ああ、やっぱりそうであったか。そうでしょう。そうでなきゃおかしい」「倭国の中心部である」と言えば、それが「邪馬台国」であると受け止められたとしても特段不思議なことではない。古田氏自身が第1書から何度も主張してきた「邪馬壹国=博多湾岸とその周辺山地」説との齟齬を指摘された故の弁解であるかは知りようがないが、安本美典氏からはこの件について鋭い批判が出ている。
そういう「ついに出たか」という驚きだったのです」
『こうした点からも、この一帯が倭国の中心部であるとの感を深くしました』