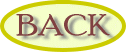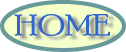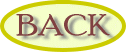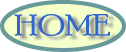『季節 通巻第十二号 特集 古田古代史学の諸相』倉田卓次・古田武彦対談
古代史学と証明責任
2022年2月、『季節 通巻第十二号 特集 古田古代史学の諸相』 p102からの倉田卓次・古田武彦両氏による対談「古代史学と証明責任」を読んで気になったことを幾つかツイートした。それらを取りまとめて1頁を作成し公開することとした。
『季節 通巻第十二号 特集 古田古代史学の諸相』
「古代史学と証明責任」倉田卓次・古田武彦 p110
古田「中国史書の書き方は、中心国との国交を書くのであって傍国との国交を書くのではないと、これが大原則でしてね・・・。」
古田氏は『失われた九州王朝』p301で何と書いているか?
午後7:00 · 2022年2月21日
『隋書』煬帝紀大業四年と同六年の「倭」「倭国」遣使を取り上げ、p304ではこの二度の遣使を
「倭国遣使」が「俀国」とは異なった、天皇家側の使者であったことをしめすものである。
と述べています。
午後7:03 · 2022年2月21日
では煬帝紀に「俀国」からの遣使記事があるのか?ありません!古田氏は『季節』の中でなんと言われたか?
古田「中国史書の書き方は、中心国との国交を書くのであって傍国との国交を書くのではないと、これが大原則でしてね・・・。」
明らかな矛盾!
午後7:06 · 2022年2月21日
『隋書』のどこに「中心国」則ち九州王朝=俀国「との国交」が書かれてあるのか?
第2書から『季節』まで15年。そんな昔のことは〝忘れちまった〟のか?
午後7:07 · 2022年2月21日
第2書せ302で大業六年倭国遣使と俀国伝の「此の後遂に絶つ」とを取り上げ、
すなわち、この「倭国」は「俀国」ではない。―これが史料のしめす冷厳な事実である。
と断じます。しかし―
(hy注)せ302はp302の変換ミス。
午後9:54 · 2022年2月21日
古田「中国史書の書き方は、中心国との国交を書くのであって傍国との国交を書くのではないと、これが大原則でしてね・・・。」
という後の発言は自身の構築した仮説内での重要な衝突を招いています。『隋書』煬帝紀に一切出てこない「俀国」。この件にかかる衝突に気が付かなかったの?それとも、、、
午後9:58 · 2022年2月21日
この「此の後遂に絶つ」については『古代は沈黙せず』p243から
第五篇 古典研究の根本問題 千歳竜彦氏に寄せて
という段を設け、「其後遂絶」に類似する表記を拾い出した「隋書国交表」なる詳細な検証をされています。
午後10:09 · 2022年2月21日
大変な作業だとは思いますが、『古代は沈黙せず』の刊行が1988/6/10。前掲『季節』は同年8/15発行。相矛盾する発言が、ほぼ同じタイミングで行われていたことになります。
午後10:17 · 2022年2月21日
この「千歳竜彦氏に寄せて」の中では俀と倭の違いについても『史記』から宣公倭の例を持ち出して論じていますが、その内容は理解に苦しむものです。あるいは『北史』の俀に対して『南史』が倭を用いていることについても氏なりの解釈を施しますが、到底受け入れられません。
午後10:30 · 2022年2月21日
『南史』倭国伝【倭國,其先所出及所在,事詳北史】
この【事詳北史】という書き方は高句麗伝、新羅伝、河南伝も同じ。
古田氏の俀と倭は別物(九州王朝とヤマト)という主張はこうやって挙例しているだけでバカバカしくなってきます。
午後10:33 · 2022年2月21日
結局、古田氏の「中国史書の書き方は、中心国との国交を書くのであって傍国との国交を書くのではないと、これが大原則でしてね・・・。」などという発言は、何らかの法則性みたいなものを自身が把握しているかのようなポーズにすぎません。実際は逆。煬帝紀に俀国が出てこないことは無視!
午後10:41 · 2022年2月21日
九州王朝説をよく理解していない人にとっては重箱の隅突き、些末なあげつらいと思えるかも知れませんが、これは重要な点。古田氏のステートメントに従えば、煬帝紀に出現しない俀国は「傍国」と言っているに等しい。そして古田氏が畿内の王朝と想定した倭こそ「中心国」ということになってしまう。
午前10:16 · 2022年2月22日
既に昭和50年、薮田嘉一郎氏が古田氏に対して指摘した通り、俀も倭も同じもの。古田氏が『古代は沈黙せず』に掲げた「隋書国交表」なる作業結果は無意味。ここで古田氏と対談している倉田卓治氏にしても、大方の古田説シンパと同様、『失われた九州王朝』をきちんと読み咀嚼していたのか甚だ疑問。
午前10:22 · 2022年2月22日
推古紀に小野妹子遣使先が「大唐」と書かれてあることを以て古田氏は妹子の二度の遣使を想定しています。倉田氏との対談でも「二度」遣使説。しかし推古紀で隋への遣使を「大唐」と書いているのは他にも大業十年(614)推古22年「上君御田耜、矢田部造を大唐に遣わす」のケースが。この件については?
午前10:34 · 2022年2月22日
拙ブログ関連記事
古田氏曰く「『日本書紀』から見る限り、大和政権が隋と国交を結んだ形跡はない」
午前10:38 · 2022年2月22日
倉田氏との対談では当然のごとく高表仁も取り上げます。憶測の羅列ですね。
拙ブログ関連記事では「孫引きになるが」と前置きしてあります。後に『季節』を入手しましたが、その箇所を確認しておきます。p111末尾の3行からp112冒頭の1行目。
午前10:51 · 2022年2月22日
その引用箇所の直前を拙ブログに投稿しました。
古田氏曰く「どこにしろ倭人の一部とあちらが考えているところ」
午前11:10 · 2022年2月22日
結局は「大和政権の可能性がいちばん高い」と言いつつ、なぜ、そのような曖昧な表現をしたのか?理解に苦しみます。
俀と倭は別物だ!という自分のアイデアに振り回されているわけです。数日前にもツイートしました。
中国からの使いが九州王朝の都を訪れたという自前の記録があるのか?ありません。
それどころか小野妹子の遣使を記したらしき九州年号まであるとか!
めっけ!RT というか、ここでは「野妹子」なので、畿内ヤマトの小野妹子とは別人の九州王朝の「野妹子」さんが入隋したんでしょうか?
hyena_no_papa
>あらら~『如是院年代記』には光充(他では光元)三年(607)に「七月野妹子入隋」と。「九州年号」って畿内ヤマトの事績を記すために存在したんでしょうか?光充六年三月「高麗貢曇徵法定二比丘」もほぼ同内容で推古紀18年3月に見えてます。なにこれ?
#壬申大乱
午後4:15 · 2021年5月20日
午後6:31 · 2022年1月10日
午後11:41 · 2022年2月15日
九州王朝説支持の皆さんは、九州王朝説はある!と思い込んでいるから、裴世清や高表仁が九州王朝を訪れたイメージを描けるのかも知れませんが、九州王朝側にはそのような記録は全くありません。
午前11:20 · 2022年2月22日
それどころか九州年号の中(如是院年代記)には、「野妹子」の遣隋という記事まであります。もちろんその年次は『隋書』『書紀』と合致しています。
古田氏の云う裴世清の二度の遣使(十二年のズレ説)など全く裏付けがありません。
午前11:23 · 2022年2月22日
『季節』p112に高宗による泰山の封禅に言及して、
これは『冊府元亀』外臣部に出ている記事です。
と。いやいや、それは新旧『唐書』劉仁軌伝に出ている記事ですよ!
午前11:37 · 2022年2月22日
同頁
この倭人というのがはたして九州王朝なのか、あるいは大義名分上は九州王朝の配下に入っていながら独力で中国に使いを送っていた大和政権なのかということもあるわけです。
「独力で中国に使いを送っていた」?ヤマト政権はいつからそんなにエラクなった?九州王朝は「中心国」じゃ?
午前11:49 · 2022年2月22日
古田氏はかつて安本氏に反論するに
以上のような三国志の表記様式の検査を実地に行わず、「『道のり』である可能性」といった“筆先きの処理”ですまそうとされたところに、反論としては一種の“手抜き”があったのではないか。そう惜しまれます。
と書いたことがありました(東アジアの古代文化17p139)。
午後1:01 · 2022年2月22日
しかし、『季節』の倉田氏との対談での古田氏の発言は、まさしく“筆先きの処理”以外の何物でもありません。前言に不都合が見つかれば表現を曖昧にして糊塗しようとする。いったい俀と倭との峻別はどうなったのか?
午後1:03 · 2022年2月22日
『季節』の巻末に執筆者紹介が載っていましたので、倉田卓次氏の部分を引用します。
倉田卓次 一九二二年生まれ。東京大学法学部卒業。元佐賀地・家裁所長、東京高裁判事。公証人。⇨
午後11:07 · 2022年2月22日
『民事交通訴訟の課題』(日本評論社)、『民事実務と証明論』(同)、『裁判官の書斎』(勁草書房)、『裁判官の戦後史』(筑摩書房)、『ローゼンベルク証明責任論』(判例タイムズ社)、『要件事実の証明責任』(西神田編集室)など著書・訳書・監修書・論文多数。⇦
午後11:08 · 2022年2月22日
学歴、経歴をみても愚生からみてはるか雲の上の人です。頭脳明晰であることは誰も疑う人などいないと思います。
古田氏との対談の一部を引用してみます。同書p104
午後11:11 · 2022年2月22日
倉田 私が裁判官だった関係で申しますと、ちょうど裁判官が証人尋問なり書証なりを読んで、どういう心証を得られるかというのと同じ具合に古田さんのお説を拝読していますと、いちばん説得力を感じましたのは、やはり邪馬壹(一)国説、『魏志倭人伝』の読み方のところなんです。⇨
午後11:11 · 2022年2月22日
古田さんが『三国志』の中の壹と臺という文字の用例をすべて調べあげたということが圧倒的な説得力を持ったことは当たり前だと思うのですが、これをやられると反証がむつかしい。
この関係資料を全部調査するという立証方法については、私、一つ印象深く憶えている事件がありましてね。〈以下略〉⇦
午後11:11 · 2022年2月22日
対談の日付が書かれてないようですが、発行の1988年頃なのでしょう。古田氏が『史学雑誌』七八-九に「邪馬壹国」を発表したs44.9から20年近くの歳月を経ています。その間の論争について倉田氏はご存じないのでしょう。
午後11:17 · 2022年2月22日
拙サイト「「邪馬臺国」か「邪馬壹国」か「邪馬壹国」論争一覧」
これら論争の経緯を倉田氏が具に吟味すれば、古田氏の邪馬壹国説に「圧倒的な説得力」など感じなかったのではないか?
午後11:20 · 2022年2月22日
倉田氏は同頁の中程でご自身の裁判官経験から「その事故に該当する車両が一つもないということがはっきり出てきたわけです」と書いています。これと古田氏の臺・壹全数検査とを対比して共感したのかも知れません。しかし―
午後11:23 · 2022年2月22日
倉田氏が、より広く漢籍上の該当表記にまで視野を広げて閲すれば、宋代に至るまで「邪馬壹」なる表記が「一つもないということ」に気が付かれたのではないか?
裁判でも時間の経過は重要な要素なのかも知れませんが、漢籍の場合は何百年にも亘ります。
午後11:26 · 2022年2月22日
その間の語句の変遷を追っていかねば真相に迫ることは出来ないと考えられます。
ともあれ知能の塊のような裁判官にあっても、その知能を発揮する環境が違えば誤った判断を持ってしまう恐れを感じます。
午後11:28 · 2022年2月22日
倉田氏が「一つもないということ」と理解したのは古田氏の第1書を読んでのことでしょう。しかし、白崎昭一郎氏の指摘する孫聖壹のケースは盧弼の考証の通り臺の誤と考えられますし、白崎氏の『東アジアの中の邪馬臺国』を読めば、古田氏の反論が不成立であることは明白でしょう。
午後11:39 · 2022年2月22日
古田・倉田対談で言及される裴世清が「二度来ている」件。その根拠の一つに裴世清がヤマトを訪れた時の官位が鴻艫寺の掌客(推古紀)で『隋書』の文林郎とは違うというのがありますが、池田温氏によれば唐初(618)以降、従五品上主客郎中に進んでいますので、倭国再訪時の鴻艫寺掌客はなさそうですね。
午前11:23 · 2022年2月23日
関連RT
引用ツイート
hyena_no_papa
@hyena_no
· 2021年6月19日
思い出したことがあるので、第四章に戻ります。p217で、池田温氏の「裴世清と高表仁」を引いていますが、同稿によれば裴世清は618年以降、従五品上主客郎中に進んでおり、古田氏の言われるように「12年のずれ」を想定すると、620年の裴世清は、逆に八品~九品に官位を落としての来訪ということに。
このスレッドを表示
午前11:23 · 2022年2月23日
関連RT
引用ツイート
hyena_no_papa
@hyena_no
· 2021年6月19日
そして正規の外交官僚タル「鴻艫寺の掌客」に任用されたのである。
池田氏によると618年以降、従五品上の主客郎中に進んでますよね。618年とは唐朝の成立年。「降格」してません。「降格」というのは、古田氏の「12年のずれ」説に基づくと、という解釈なので、事実の裏付けはナシ。
このスレッドを表示
午前11:24 · 2022年2月23日
古田氏が「12年のずれ」などという奇矯な説を案出したからと言って九州王朝の史書が出現して裴世清訪問の記録が浮かび上がるわけではありません。薄弱な根拠に基づいて我田引水の解釈をするのは歴史に対する冒涜ではないかという気さえします。
午前11:45 · 2022年2月23日
『季節』p110から古田氏の文を先に引きましたが、p107でも同様なことを述べています。
正史にはその時点時点の代表である王者だけを書くのが通常のルールですから。
そういうことでいいますと、隋の場合、隋が多利思北孤(私は彼を九州王朝の王者と考えるわけですが)と国交を結びますね。⇨
午後2:20 · 2022年2月23日
同時に近畿の政権にも使者を送っていたとしても、それは本来、正史には書くべきではないわけで、正史には九州王朝との交渉が記されるわけです。⇦
「正史には書くべきではない」?煬帝紀の倭、倭国は?
午後2:22 · 2022年2月23日
古田氏の文を読んでいると、いかにも理路整然と論述しているかのように感じられるのかも知れませんが、一皮めくれば前言との矛盾が顔を出します。
午後2:24 · 2022年2月23日