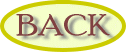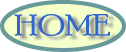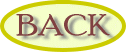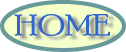「二つの百済」
tokyoblog氏の「二つの百済」について
2019-10-22 (Tue)
最近遭遇したサイトだが、この「古代史俯瞰 by tokyoblog」の質とボリュームがスゴイ!到底全体像を短期間で窺うことは不可能だろうが、先日来長々とお邪魔してきた青松光晴さんの「日本古代史つれづれブログ」にも引用されていた「
二つの百済」という項目が非常に興味深く、引きずり込まれてしまった。
青松光晴さんのブログに名無しさんがコメントを寄せているが、その中で、
「括地志輯校巻四蛮夷東夷」
百済国の西南渤海中に大島十五所あり。皆、邑落に人ありて居す。百済に属す」
上記の一文、西暦641年のものです。百済滅亡が660年です。さて、渤海が西南に見える所はどこでしょう。それは遼東半島西岸の北部域。朝鮮半島から渤海は見えないと思います。
と書いている。『括地志』は掲示板時代でもなかなか出てこない史料だ。この引文は『史記』夏本紀に引用されたもので、同じ『括地志』でも『史記』五帝本紀に引用されたものには「渤」が無い。
a.『史記』五帝本紀
括地志云:「百濟國西南海中有大島十五所,皆置邑,有人居,屬百濟。」
b.『史記』夏本紀
括地志云:「百濟國西南渤海中有大島十五所,皆邑落,有人居,屬百濟。」
さて、こういう場合bの「渤」を衍字と見るか、aの闕字と見るか即断はできないだろう。渤海の西南には「大島十五所」と言えそうな島々は見えない。一方、通常の認識通りの位置で百済をみると、たしかにある程度の大きさの島々がある。なので、「渤」を衍字と見たほうが良さそうにも思えるが、問題は「二つの百済」にも引かれているように、『宋書』『梁書』『通典』には百済が遼西郡あたりを領有していたとの記述がある。この記載に注目すれば「百濟國西南渤海」の「西南渤海」が俄然活きてくる。
この『括地志』だが、百済の記事に続いて引用されている部分は、
又倭國西南大海中島居凡百餘小國,在京南萬三千五百里。
であり、どこから出てきてのか分からないが極めて怪しい情報であることは確かだ。案ずるに、「倭國西南」がどうもおかしいのではないか。「百餘小國」といえば『晋書』や『後漢書』が想起されるが、いずれも「西南」などの字句は無い。それともこの倭國を「九州王朝」と解釈して、「西南大海中島居凡百餘小國」を南西諸島とするか。古田氏はどこかでこの箇所を取り上げているんだろうか?
話を「二つの百済」に戻すが、この件について手元の書籍中に何らか言及したものがないか探してみた所、井上秀雄『古代朝鮮』86ページに、
『宋書』百済国伝に百済が遼西郡を支配したという一見奇妙な記事に、唐代以来中国の学者たちはその解明に苦しんできた。
とある。
「唐代以来中国の学者たち」が「苦しんできた」という問題ならば、この私が謎解きできなくても当然のことだ!と非常に安心した。
さて、この問題について快刀乱麻の如く謎解きをしてくれた傑物はその後いたのかどうか、、、
朝鮮半島の古代史は倭の古代史より難しそうだ。非力な私がのこのこと出ていくべきフィールドでは無かろう。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その2―
2019-10-22 (Tue)
古代史俯瞰 by tokyoblog「二つの百済」に以下の一節がある。
中国の史書「通典百済伝」に、「660年の百済滅亡後、長城付近(遼西東部の百済郡)の残留民は段々と数が少なくなり、気力も尽きて突厥とか靺鞨族に投降し、百済郡太守扶余崇は、滅亡した百済(熊津、扶余)に帰ることが出来ないで、あちこちうろうろし、遂には滅んでしまった」とあります。
いつものように原文を確認する。
『通典』辺防一百済
【其舊地沒於新羅,城傍餘眾後漸寡弱,散投突厥及靺鞨。其主夫餘崇竟不敢還舊國,土地盡沒於新羅、靺鞨,夫餘氏君長遂絕。】
となっている。これは「中國哲學書電子化計劃」「武英殿版」「無刊記本」いずれも同文で、『東アジア民族史2 正史東夷伝』百済では「城の周辺の〔百済の〕遺民は」と原文に沿って訳してある。いずれも「城」であり、「長城」とはなっていない。
なのでtokyoblog氏が原文の「城」を「長城」と訳したのはどうなのか?と疑問も湧くが、『宋書』『梁書』『通典』には百済が遼西郡あたりを領有していたとの記述があるので、「城」を「長城」と訳したのは逆に文意を適切に解釈したのではないか、という見方もできる。漢文を読んでいると意味が通じる場合は複数字の単語を一字で表すことはまま見かけるからだ。
半島西南部の百済の残留民が「突厥とか靺鞨族に投降し」というのは位置関係から言ってたしかに無理がある。
謎。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その3―
2019-10-22 (Tue)
今日午前中、『括地志』から2例を引いた。
a.『史記』五帝本紀
括地志云:「百濟國西南海中有大島十五所,皆置邑,有人居,屬百濟。」
b.『史記』夏本紀
括地志云:「百濟國西南渤海中有大島十五所,皆邑落,有人居,屬百濟。」
あと、『翰苑』百済条にも『括地志』が引かれているのであわせて記しておく。
c.『翰苑』百済
括地志曰〈中略〉「又國南海中有大島十五所皆置城邑有人居之」
「西南」が「南」、「渤海」が「海」。『翰苑』の文字の乱れは甚だしいので軽々に当否を言うことはできない。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その4―
2019-11-04 (Mon)
10/29にteacup談話室に白石南花さんあての投稿をしたので、それを再掲しておく。
白石南花さん!質問が、、、 投稿者:hyena_no_papa 投稿日:2019年10月29日(火)23時52分56秒
お忙しいところ申し訳ありませんm(_ _)m 朝鮮半島にお詳しい白石南花さんにお尋ねするのが手っ取り早いと思い、ご質問させていただきます。
最近「古代史俯瞰 by tokyoblog」というサイトに遭遇しまして、その中の「二つの百済」を読んで脳みそが停止してしまいました、、、
白石南花さん自身のサイトにも書かれてありますように、昔から百済は伯済国を中心として国家が形成されたのだと教科書的に捉えていました。
しかし、既にご存知かと思いますが『宋書』には【百濟國,本與高驪?在遼東之東千餘里,其後高驪略有遼東,百濟略有遼西。百濟所治,謂之晉平郡晉平縣。】という記述が見えます。これは「百済が遼西郡を支配した」と読み取れるのではないでしょうか?
それで手元の本を探っていたら、井上秀雄『古代朝鮮』86ページに、
『宋書』百済国伝に百済が遼西郡を支配したという一見奇妙な記事に、唐代以来中国の学者たちはその解明に苦しんできた。
とありました。
これは何らかの誤情報に基づくものなのでしょうか?それとも「古代史俯瞰 by tokyoblog」氏の言われる通り「二つの百済」という理解をすべきなのか?
『通典』辺防一百済には【其舊地沒於新羅,城傍餘眾後漸寡弱,散投突厥及靺鞨。其主夫餘崇竟不敢還舊國,土地盡沒於新羅、靺鞨,夫餘氏君長遂?。】とあり、「散投突厥及靺鞨」は「突厥とか靺鞨族に投降し」という意味でしょう。
半島西南部の百済の残留民が「突厥とか靺鞨族に投降し」というのは位置関係から言ってたしかに無理があるように思えます。
もし白石南花さんがご自身のサイトの中でこの件について言及している部分がありましたら、勉強させていただきたくご案内よろしくお願い申し上げますm(_ _)m
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その5―
2019-11-04 (Mon)
書棚の朝鮮関係の書籍をパラパラとめくってみるが、この「二つの百済」に関する記述は井上秀雄『古代朝鮮』以外目に止まらなかった。
そうしているうちにひょっと思いついた。『東アジアの古代文化』のなかに関連記事がないか?
『東アジアの古代文化』の最終137号には創刊号からの主な記事の一覧が載っている。ページを捲っていくと、あった!1996夏・88号に坂田隆氏の「遼西百済と南韓百済」という一文が。
とりあえず一通り読んで見る。きちんと史料に基づいて述べてあり、私自身の乏しい知見に照らして見る限りでは無理筋とは見えない。
146ページで言うに、
私は、〝六世紀初頭以前においては、「百済」という名の国は二つ存在する〟と考える。〝六世紀初頭以前においては、日本史書に登場する百済は、一部の例外を除いて、中国史書に登場する百済とは別の国だ〟ということである。中国史書の百済と日本史書の百済とでは、所在地・国力・対高句麗敗戦年代・南遷年代・王名・系譜・在位年代、すべて異なっているのだから、〝百済は二つある〟とせざるをえないのである。
また、147ページでは、
(1)遼西百済は次のような国である。
①中国史書に登場する六世紀初頭以前の百済は遼西百済である。
とも言う。
この坂田論文の当否を云々するには、私の力が不足していることは紛れもない。ただ、興味深いということだけは言えそうだ。
読後、ひとつだけ思いついたことがある。それは、他ならぬ『宋書』「倭国伝」倭王武の上表文中に出てくる「百済」である。
【臣雖下愚,忝胤先緒,驅率所統,歸崇天極,道逕百濟,裝治船舫,而句驪無道,圖欲見吞,掠抄邊隸,虔劉不已,每致稽滯,以失良風】
ここでの「百済」は文の流れから見て倭に近い方の「百済」と見たほうがいいのだろう。この上表は順帝昇明二年で西紀478年。坂田氏の「中国史書に登場する六世紀初頭以前の百済は遼西百済である」という主張とは相容れない恐れもある。
この上表文は倭王武によるものだから、ここでの「百済」が半島南西部の「百済」と解釈することも無論可能とは思う。
それにしても、この「二つの百済」というのは難問だ。下手をすると〝倭国と日本国は違う!〟という九州王朝説的見方にドリンク剤を提供する可能性無きにしもあらず、、、かも。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その6―
2019-11-04 (Mon)
前述の『東アジアの古代文化』1996夏・88号坂田隆氏の「遼西百済と南韓百済」は主に『古事記』『日本書紀』や『日本書紀』所引「百済新撰」「百済記」を含めた〝日本史書〟と、中国正史や『通典』『資治通鑑』などの〝中国史書〟に基づいて述べられているが、かの「好太王碑文」は用いられていない。
この「好太王碑文」にも【百殘新羅舊是屬民由來朝貢而倭以耒卯年來渡[海]破百殘■■新羅以為臣民】と「百済」の別称「百残」が見えていて、この文を解釈するに、ここでの「百残=百済」は半島南西部にある「百済」以外考えられない。
辛卯年は391年で、坂田氏の所説によれば「南韓百済」ということになる。
さて、では当時の遼西百済はどうなっていたのか?坂田氏の所論から見てみると、『梁職貢図』の【晋末、駒麗略有遼東、楽浪亦有遼西晋平県】という文を引き、また『晋書』「簡文帝紀」によれば東晋は372年百済王餘句に楽浪太守を領させているという。つまり、『職貢図』の【楽浪亦有遼西晋平県】という記述の実態は、百済が遼西郡を領有しているという意味になるとする。
「好太王碑文」の辛卯年はまさしくこの「晋末」にあたり、「好太王碑文」や倭王武の上表文中の百済と、遼西郡を領有している百済との両者を史実として受け入れようとするならば、この時代確かに「二つの百済」が存在したということにしかならないのではないか?
紛れもなく難問である。
hy注)「耒卯年」の「耒」は「辛」の異体字であるとされる。『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』末松保和「好太王碑文研究の流れ ―水谷悌二郎氏の研究を中心として―」211ページ。「耒 辛カ。來の形なり辛字の異体と認むべし」とある。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その7―
2019-11-04 (Mon)
さて、4世紀代の百済についての金石文で忘れてならないのが、石上神宮伝来の七支刀である。もっともこの銘文も解読するに諸説あり、当然のごとく未だその読み方が定まっていない。
その中で、問題となるのが年号、百済、そして倭王である。年号は東晋の泰和(太和)とする説が有力のようで、その四年は369年になる。これまた「二つの百済」と関わりそうな年次ではある。
「百済」は〝百濨〟とみる説が多数のよう。ただし「済」の異体字とみる説も棄てきれないか。
「倭王」は異論はなさそうだが、それに続く「旨」が諸説見解の分かれるところ。
hy注)参考文献:『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』渡辺公子「七支刀銘文の解釈をめぐって」
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その8―
2019-11-04 (Mon)
「僑郡」
『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』によれば、僑郡・僑県は、
中国で,東晋 (→晋) 以後,華北から江南に集団移住したもののために仮においた郡と県。西晋の永嘉の乱ののち,華北の人々が大量に江南に移住したが,その際郡や県の民衆が集団で移住することも多かった。東晋以後その移住先に原住地の名称を残した郡や県をかりにおき,長官を任命した。そうした移住者は最初税役を負担しなかったようであるが,のち税だけを負担し,さらに東晋末になると僑郡,僑県の整理 (→土断 ) が行われ,徭役も負担させられるようになった。しかし北来の官吏層に対しては,そのまま僑州や僑郡を基準とした九品官人法が行われた。
とある。「僑」は「故郷を離れて他の土地に住む」の意。
『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』窪添慶文「楽浪郡と帯方郡の推移」には、この「僑郡」という言葉が出てくる。
その41ページにはかなり参考になりそうな記述が見える。
楽浪郡の滅亡に際し、遼東の人張統なる人物が居り楽浪・帯方二郡に拠って高句麗の攻撃を防いでいたが、楽浪の人王遵の説得により共に民千余家を率いて当時遼東・遼西に勢力を扶植していた鮮卑の慕容廆(ぼようかい)に帰した。廆はその千余家をもって楽浪郡を新たに設置し張統を太守、王遵を参軍事に任じたという(『資治通鑑』巻88)。当時中国に数多くみられるようになってきた僑郡(きょうぐん)を形成したわけである。
僑郡県の特色は同一行政区画(州・郡・県)内に居住していた住民が逃亡・移住した新地域で集団形成の中核となることにあり、まったく名目的なものも後代には存在するが、多くは幾ばくかの実体を有している。『通鑑』巻96咸康四年条の胡三省注によれは楽浪僑郡は隋の遼西郡柳城県の界にあったという。後の竜城で、現在の遼寧市朝陽市近辺である。『通鑑』の同年条に朝鮮令孫泳(昌黎の人)が趙軍を防いでいた時大姓王清らが趙に内応しようとして斬られたとあるから、属県として朝鮮県もおかれていたらしい。大姓王清とはもと楽浪郡に居住していた者であろう。楽浪太守鞠彭(きくほう)の名も見えるが、これは東萊の人である。
どうやらほんの少しだが、「二つの百済」の正体が見えてきたような気がする。気のせいかも知れないが、、、(^^;)
hy注)咸康四年はAD338。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その9―
2019-11-04 (Mon)
井上秀雄『古代朝鮮』から一節を先に引いたが、その直前の箇所が井上氏の所見を詳しく書いているので、長くなるが引用する。85-86ページ。
『宋書』と百済の〝遼西支配〟
宋は百済ときわめて緊密な関係にあったにもかかわらず、『宋書』(中国南朝宋の歴史を記した正史で南梁の沈約が四八八年に編纂したもの)東夷百済国伝には、次のような奇妙な記事がある。
百済国はもと高句麗とともに遼東郡の郡庁のある襄平(現在の中国の遼陽地方)の東一千余里のところにあった。その後高句麗はほぼ遼東郡を支配し、百済は遼西郡をほぼ支配した。このとき百済が根拠地としたところは晋平郡の晋平県である。
百済は馬韓の一国であった伯済国から興り、周囲の馬韓の諸小国を統合して大国になったと考えることと、この百済の遼西郡支配とが地理的にも遠距離で、両者を一つにして考えることがはなはだ困難である。このような疑問はすでに『梁書』(中国の南朝梁の歴史書。唐の姚思廉が六二九年に勅命で編纂したもの)から出ている。『梁書』は百済の本拠を馬韓におき、東晋時代に遼西・晋平二郡を領有して百済郡としたとある。『梁書』の見解がかなり穏当で史実に近いと思われるが、なお若干補足する必要がある。
東晋末期は遼東・遼西地方が政治的に混乱していた。鮮卑族の慕容氏ははじめこの地方を基盤として華北に侵略した。前燕が三七〇年に前奏に滅ぼされてからは、高句麗が遼東地方を支配した。百済は高句麗の広開土王(在位三九一~四一二)・長寿王(在位四二三~四九一)の圧迫に苦しんだが、中国の南朝宋の冊封を受け、南朝鮮諸国と連合して高句麗と対立した。おそらくその一時期に、遼西方面と政治的な連携ないしはその一部を支配したのではないかと思われる。百済は東晋や宋との国交を海上交通で結んでおり、当時東アジアでもっとも進んだ海上交通国であった。そのため近肖古王代(在位三四六~三七五)から日本との国交が始まったといわれてきた。しかしこれは次に述べるように、若干の問題を含んでいる。当時の百済にとって、日本は国際社会の末端で、さしたる関心もなかったはずである。百済は三七七年に北方の前秦にも朝貢しており、北方の遼西方面に強い関心を抱いていた。前燕の崩壊にともなう遼東・遼西地方の政治的混乱期に百済が三七一年の対高句麗戦の大勝の余勢をかって一時的にしろ遼西郡を侵略することは、じゅうぶん可能性のあることである。さらに可能性の強い考え方をすれば、南朝宋では高句麗に対抗するものとして百済を高く評価している。高句麗が北朝の魏や燕と結んでいるのを牽制する意味でも、百済の遼西郡侵略を誇張して取りあげる必要があったのでなかろうか。
朝鮮史の専門家としての穏当さを維持するに、ギリギリの見解なのだろう。86ページの最後の行では次のように締めくくる。
日本史の研究者が百済の遼西侵略記事を頭から誤伝としてしりぞけ、大和朝廷との関係は間違いないと考えることには基本的な検討が必要であろう。
tokyoblog氏も「南斉書では北魏が数十万騎で百済を攻めたとあるが、渡海作戦を行ったような記述は無い。百済が朝鮮半島南西部にあったとすると陸路でも海路でもかなり困難な作戦だ。そればかりでなく、北魏と百済の間には高句麗が有り、高句麗の向こう側に数十万騎を送るのは不可能ではないか?」と述べて疑問を呈しているし、先に引用した坂田隆氏もこの490年の百済による大規模な北魏侵略軍を撃破していることを特に取り上げる(p138)。
坂田氏は言う。146ページ。
私は、〝六世紀初頭以前においては、「百済」という名の国は二つ存在する〟と考える。
上掲の490年の北魏軍撃破は、まさに遼西百済のことを述べていることになる、、、というのがtokyoblog氏、そして坂田隆氏の主張ということになる。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その10―
2019-11-04 (Mon)
さて、百済の遼西郡支配のソースは『宋書』百済国伝であることはtokyoblog氏の提示しているところだが、再度原文を掲示しておく。
【百濟國,本與高驪俱在遼東之東千餘里,其後高驪略有遼東,百濟略有遼西。百濟所治,謂之晉平郡晉平縣。義熙十二年,以百濟王餘映為使持節、都督百濟諸軍事、鎮東將軍、百濟王。】
『梁書』にも類似の文が見える。
【其國本與句驪在遼東之東,晉世句驪既略有遼東, 百濟亦據有遼西、晉平二郡地矣,自置 百濟郡。】
『宋書』の記事からすると、百済の遼西支配は義煕十二年の前のように捉えることができる。義煕十二年はAD416である。
先に、『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』窪添慶文「楽浪郡と帯方郡の推移」から引用したが、その中の以下の部分が真相に迫る一歩となりそうなので以下に再度引用する。
楽浪郡の滅亡に際し、遼東の人張統なる人物が居り楽浪・帯方二郡に拠って高句麗の攻撃を防いでいたが、楽浪の人王遵の説得により共に民千余家を率いて当時遼東・遼西に勢力を扶植していた鮮卑の慕容廆(ぼようかい)に帰した。廆はその千余家をもって楽浪郡を新たに設置し張統を太守、王遵を参軍事に任じたという(『資治通鑑』巻88)。当時中国に数多くみられるようになってきた僑郡(きょうぐん)を形成したわけである。
義煕十二年以前に、『宋書』の言うような【高驪略有遼東,百濟略有遼西】という事象を求めるとすれば、上掲引文こそそれに当たるのではないかと思うのだが・・・。
ただし、この遼西百済の人々とは、扶餘系、韓人そして楽浪に渡来していた漢人などの混合であり、南朝劉宋に通じるに当たって、それらの人々のいずれかの所伝が劉宋へ伝えられた結果、かの『宋書』百済伝のごとき記述となったのではないか?というのが、ここまでのところの私の仮の答えである。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その11―
2019-11-06 (Wed)
『晋書』「武帝紀」に東夷諸国が盛んに西晋朝に遣使していることは、割合多くの人が言及している。その期間は咸寧二年(276)から元康元年(291)の間で、「馬韓伝」には8件の来献記事が見えている。『東アジア民族史1』212ページより転載。末松保和『新羅史の諸問題』(東洋文庫)よりの再転載。
| 年次 |
(西暦) |
帝紀 |
馬韓伝 |
| 咸寧二年 |
(276) |
二月東夷八国帰化 |
|
| 七月東夷十七国内附 |
|
| 咸寧三年 |
(277) |
是歳東夷三国内附 |
(馬韓)来 |
| 咸寧四年 |
(278) |
三月東夷六国来献 |
(馬韓)諸内附 |
| 是歳東夷九国内附 |
|
| 太康元年 |
(280) |
六月東夷十国帰化 |
馬韓遣使入貢方物 |
| 七月東夷二十国朝献 |
|
| 太康二年 |
(281) |
三月東夷五国朝献 |
馬韓主遣使入貢方物 |
| 六月東夷五国内附 |
|
| 太康三年 |
(282) |
九月東夷二十九国帰化 |
|
| 太康七年 |
(286) |
八月東夷十一国内附 |
馬韓至 |
| 是歳馬韓等十一国遣使来献 |
|
| 太康八年 |
(287) |
八月東夷二国内附 |
馬韓至 |
| 太康九年 |
(288) |
九月東夷七国詣校尉内附 |
|
| 太康十年 |
(289) |
五月東夷十一国内附 |
馬韓至 |
| 是歳東夷絶遠三十余国来献 |
|
| 太煕元年 |
(290) |
二月東夷七国朝貢 |
馬韓詣東夷校尉何龕上獻 |
| 元康元年 |
(291) |
是歳東夷十七国詣校尉内附 |
|
『晋起居注』に武帝泰始二年(266)倭女王の遣使があったことが記されているが、それから10年後からいきなり東夷諸国の朝献が続く。この件について、『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』窪添慶文「楽浪郡と帯方郡の推移」40ページで以下のように解説している。
泰始十年(二七四)晋は幽州を分けて平州を置き、楽浪・帯方・玄菟・昌黎・遼東の五郡を属せしめた。その直後から「東夷」諸国の晋への朝貢回数が急激に増える。翌々咸寧二年(二七六)二回、同三年に一回、同四年に二回、太康元年(二八〇)二回、同二年二回、同三年一回、同七年二回、同八・九年一回ずつ、同十年二回、太煕元年(二九〇)・元康元年(二九一)一回ずつとほとんど毎年のように朝貢記事が続く。この期間における他国の朝貢数と比べると扶南・林邑等東南アジア諸国が五回、大宛等西域諸国三回、匈奴・鮮卑等二回……となって異常に「東夷」諸国が多い。これは平州が置かれて「東夷」の朝貢をとりしきったことに原因があるのでもなく、呉を太康元年(二八〇)に併合したことにより形勢を観望していた諸国が一斉に晋に靡いたからでもないであろう。「東夷」諸国(中心をなしたのは韓であったらしい――馬韓が加わっていたことが判明するものだけで八回、辰韓は三回)が争って朝貢する事情が別にあったに違いない。憶測ではあるがそれはこれら諸国において国家統一への動きが顕著となってきたことによるのであって、各国がその主導権をとるため自らの権威の裏づけを晋に求めた――具体的には官爵の授与――ことではなかったろうか。
連年のごとく朝献を励んだ東夷諸国ではあったが、313年には楽浪郡が高句麗によって滅び、3年後には西晋朝すら滅ぶ。晋室はなんとか南渡して建康を都に東晋として成立するものの、河北は以後、五胡十六国の大混乱時代に入る。上掲「これら諸国において国家統一への動きが顕著となってきた」というのはまさしくその通りかと思う。我が国における前方後円墳を象徴とする古墳文化の全国伝播や倭王武の上表文はそのことを裏付けるものと見るのが妥当である。
北魏によって河北が統一されるまでの約1世紀余の期間、東夷諸国で起きたことの中には複雑奇異な事象もあったのではないか。「二つの百済」という現象も、そのうちの一つなのかもしれない。
どうやら北燕・南燕・後燕などという鮮卑系勢力が難問解決の鍵を握っているのではないかという気がしてきた。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その12―
2019-11-06 (Wed)
本日午前の投稿で、「どうやら北燕・南燕・後燕などという鮮卑系勢力が難問解決の鍵を握っているのではないかという気がしてきた。」と書いたが、『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』大庭脩「三・四世紀における東アジア諸族の動向」では、まさしく魏晋王朝及びそれ以降の中国と東夷諸国の関係、特に「燕」について突っ込んだ論説が展開される。
とにかく大庭氏の論述は詳細に亘るので、素人が飲み込んで消化するのは極めて困難である。
しかし、大庭氏も文中用いられている『謎の四世紀』が、単に倭国内のみの問題ではなく、東アジア全体の問題として捉えなくてはならないのだろうということだけは、薄々感じることができる。
河北を一時的に統一した前秦がその勢いを駆って南下し東晋と激突した淝水の戦いでは前秦は大敗北を喫する。その結果として東晋は山東半島を回復するが、そのことが後の倭王賛の東晋への遣使にもつながるのだろう。
ということは、「二つの百済」の謎を解くには、倭の五王までも視野に入れなければならないということなのか。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その13―
2019-11-07 (Thu)
『南斉書』に言う、北魏孝文帝の太和十四年(490)の北魏による百済攻撃とそれを百済が撃破したことは坂田隆氏とtokyoblog氏ともに指摘しているところだが、このあたりのことを『北魏書』に尋ねてみると、どうも疑わしく思えてくる。
帝紀を見ると、五世紀後半から六世紀にかけて、高句麗は極めて頻繁に北魏と通交している。490年の前後もほとんど連年のごとくである。
もし仮に遼西百済なるものがあり、『南斉書』の言うように【騎数十万】なる大軍が遼西百済を襲ったとしたら、その上その【騎数十万】が百済のために破れたとしたら、いかにして高句麗がこの時期に北魏と通交することが出来たのだろうかという疑問は当然湧く。
数十万という軍勢は、あの赤壁の際の魏の軍勢と同レベルと言えるかも知れない。魏の場合は国家の命運をかけて呉蜀連合軍と激突したのであるから相当の勢力であったことは確かだろう。しかし、北魏からしてみれば遼西百済など【騎数十万】を差し向けるほどの勢力でもあるまい。
『魏書』百済伝によれば、【(延興)五年,使安等從東萊浮海,賜餘慶璽書,褒其誠節。安等至海濱,遇風飄蕩,竟不達而還】とあり、顕祖の遣わした使者は山東半島の東萊から船出しているのだから、475年時点でこの使者の向かった先は当然遼西百済ではなく南韓百済である。
それに先立って顕祖が百濟の使者の帰国に際しての詔書にも百済が北魏と隣接しているかのような表現はなく、逆に僻遠であることや高句麗が北魏と百済との間を遮っているとさえ言う。
これらの文脈を見るに、到底490年時点で北魏が【騎数十万】を派遣せねばならないほどの遼西百済なるものが存在したとは考えにくい。
『南斉書』の伝えるこの件は虚構である可能性が大きいと考えるのが至当と言えよう。
先に「古代史俯瞰 by tokyoblog 「二つの百済」―その10―」で書いた如く、もし遼西百済なるものが存在するとしたら、4世紀初頭の楽浪郡や西晋の滅亡から、5世紀初頭義煕十二年までのおおよそ一世紀の間のことではないか。
そしてそのことを解明するキーワードは〝僑郡〟や〝北燕・南燕・後燕などという鮮卑系勢力〟ということになるのかも知れない。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その14―
2019-11-07 (Thu)
坂田隆氏が「遼西百済と南韓百済」で引用されているが、『晋書』卷一百九載記第九 慕容皝伝に以下のようにある。年次は東晋成帝の咸康七年(341)のこと。
【皝記室參軍封裕諫曰〈中略〉句麗、百濟及宇文、段部之人,皆兵勢所徙,非如中國慕義而至,咸有思歸之心。今戶垂十萬,狹湊都城,恐方將為國家深害】
坂田氏の意訳をそのまま借用すれば、
わが国(前燕)にいる高句麗・百済・宇文・段部の人は、みなわが国の兵士がその軍勢によって移住させた者たちです。わが国を中国と仰ぎその義を慕って参集したのではありません。みな帰郷を思う心を持っています。今、その戸数も十万になんなんとし、首都龍城にひしめき集まっています。おそらくはわが国にとって深い害になるでしょう。
である。
前燕といえば東は遼東から西は一時黄河下流全域まで版図を広げている。その首都であった龍城には前燕によって移住させられた高句麗・百済・宇文・段部の人々が「ひしめき合って」いるというのである。その前燕もAD370には滅ぶ。以後、この地域には後燕(384-408)、南燕(398-410)、北燕(409-436)という国々が勃興するが、それらの概ね鮮卑系の国々の実態がどうであったのか。興廃の空白期間に、高句麗や百済の移住民たちはどのような状態だったのか。
『宋書』「百済国伝」【百濟國,本與高驪俱在遼東之東千餘里,其後高驪略有遼東,百濟略有遼西。百濟所治,謂之晉平郡晉平縣】
『梁書』「百済伝」【其國本與句驪在遼東之東,晉世句驪既略有遼東,百濟亦據有遼西、晉平二郡地矣,自置百濟郡】
なる記述は4世紀から5世紀初頭にかけての遼西で起きた鮮卑系諸国の興亡と混乱の中で生じた、ある種の歴史事象なのかも知れない。
中国正史により深くこの事象についての記述を求めるとすれば、おそらくは『北史』がもっとも真相に近いのではないかと思えるが、この途もまた相当に険しそうだ。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その15―
2019-11-08 (Fri)
非力な身体に鞭打って四苦八苦山を上り詰めたら、頂上には既に何人もの先客がいて、登山の猛者たちが記念写真を撮ったり談笑したりしていた、、、
そんな気分だ。Wikiwand晋平郡
https://www.wikiwand.com/ja/%E6%99%8B%E5%B9%B3%E9%83%A1#/CITEREF%E5%AE%AE%E8%84%872013
「遼西百済」について詳細に解説してある(@_@;)
それでも、井上秀雄氏の「前燕の崩壊にともなう遼東・遼西地方の政治的混乱期に百済が三七一年の対高句麗戦の大勝の余勢をかって一時的にしろ遼西郡を侵略することは、じゅうぶん可能性のあることである」という所見を引いてあるのは、自分の着眼点もあながち専門家の目線と激しく乖離しているということでもないのかな?と少し気分が安らいだ。
こういう場面に出くわすことは、古代史をやっていればたまにあることで、そんな場合の慰めの言葉を用意してあるというのは精神衛生上も有益だ。
往々にして、わたしたちは、みずから考え、また、これを組み合わせることによって、さまざまに苦労を重ね、長い年月を費やして、ようやく作り上げてある真理やある見解が、ふと手にしたある書物のなかに、そっくりできあがっているのを見つけて、がっかりすることがあるとしても、やはり、みずから考えて獲得した真理なり見解は、ただ読んで知ったものにくらべると、百倍以上も価値があります。なぜなら、このようにして初めて、それらのものは、わたしたちの思想の全体系のうちに、たいせつな部分として、また活動的な四肢として入りきたり、これと完全に緊密に結合し、それらの根拠と結論もすっかり理解されて、わたしたちの全思考法の色彩と色調と極印とを有するものとなりますし、それらのものの必要が感ぜられたときに、ちょうどおりよくやってきたので、したがって、堅固な位置を占め二度と消え去ることはないからです。このような意味で、つぎに掲げるゲーテの詩句は、完全に適用されるし、さらに説明されもするでしょう。 「おまえが おまえの先祖から 受け継いだものを おまえのものとするためには さらに それを獲得せにゃならん」(『ファウスト』第一部)
ショウペンハウエル『みずから考えること』(角川文庫版27-28頁)より
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その16―
2019-11-11 (Mon)
五世紀後半においては、遼西百済などなかったという根拠を『北魏書』から拾ってみようと思う。
延興二年,百済王餘慶が初めて遣使した際の上表文
1.【臣建國東極,豺狼隔路】臣は東の果に国を建てましたが豺狼(高句麗)が道を隔てて
→北魏と百済の間に高句麗が存在していた。
2.【投舫波阻,搜徑玄津】餘禮や張茂等を遣わすのに船は波に阻まれ、遠い港を探す
→百済と北魏は地続きで隣接していない。海路遣使した。
3.【梟斬釗首。自爾已來,莫敢南顧】高句麗王釗の首を斬った。以来敢えて南を顧みることがない
→百済は高句麗の南にあった。
4.【臣西界小石山北國海中見屍十餘】臣の西界にある小石山の北の國海中に
→遼西の北に海はない。
5.【長蛇隔路,以沉于海】長蛇(高句麗)が道を隔て、以て海に沈めた
→魏と百済との間には高句麗があり、百済へは海路で行く。
顕祖の詔書その他
6.【其僻遠,冒險朝獻】その僻遠、険を冒して朝見した
→国境を接し、『南斉書』の言うように【騎数十万】なる大軍が遼西百済を襲っているのに「僻遠」というか?
7.【卿在東隅】百済は東の果てに
→遼西百済の東には高句麗があるのだから、「東隅」はヘン。
8.【不遠山海】山海を遠きとせず
→北魏と遼西百済は接していたはず。
9.【(邵)安等至高句麗,璉稱昔與餘慶有讎,不令東過,安等於是皆還】顕祖の使者邵安を百済の使者の帰国に添えたが、高句麗が通過することを拒んだ
→百済は高句麗を経なければ行けないところにある。
10.【(延興)五年,使安等從東萊浮海】(475)邵安を東萊から船出して百済の餘慶に璽書をもたせた
→東萊(山東半島)から船出するのは遼西百済ではありえない。
『魏書』百済国伝における上表文と詔書の内容をみる限り、ここでの百済は遼西百済ではありえない。『南斉書』に見える【是歲(490),魏虜又發騎數十萬攻百濟,入其界,牟大遣將沙法名、贊首流、解禮昆、木干那率眾襲擊虜軍,大破之。】というのは甚だ疑わしい。人名まで列記しているがおおよそ史実とは言えないだろう。
百済は東晋代以降、567年北斉に朝貢するまでの約200年間、北朝に遣使したのは472年の1回のみである。この頃は勿論、高句麗の南下に押されて百済は『北魏書』に記す上表文中にある如く【財殫力竭,轉自孱踧】(財力は尽き力も尽きて、自ら窮弱に転じている)という状態であろうから、かねてより通交のある南朝に加えて北魏の力も借りて高句麗の南下を押し留めようとする意図があったのかも知れない。
その一方で北魏に対して高句麗のことを【或南通劉氏,或北約蠕蠕】(或いは南は劉宋に通じ、或いは北は蠕蠕と約し)と悪し様に言いつつ、自身はせっせと劉宋に貢献してきたことは口に出してはいない。
しかし、北魏の顕祖は百済の遣使を多としながらも、高句麗は長年遣使を続けている一方、【卿使命始通】と百済が今回初めて通交してきたことを指摘し、高句麗討伐という百済の求めに理がないことをやんわりと指摘している。
国の存続の瀬戸際で、このような外交手段を取ること自体はじゅうぶんありうるとこだろう。針小棒大な表現を用いても、やむを得ないとは言える。高句麗の場合は南北朝の間、北朝南朝いずれにも遣使していたのと比べ、百済が専ら南朝への通交に偏ったことが国家の窮地を招き衰運の道を辿った一つの理由なのかも知れない。
こうして『北魏書』の記載するところに沿って5世紀における百済を取り巻く情勢を見てみると、遼西百済が存在し、しかも数十万という北魏の騎兵を打ち破ったなどとする『南斉書』「百済伝」永明八年(490)の記述は到底信じうるものではないと言えそうである。ただ、『資治通鑑』にはこの二年前の北魏と百済の衝突の記事(永明六年 魏遣兵擊百濟,為百濟所敗。)があるので、この情報のソースがいずれにあるかが気になるところではある。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その17―
2019-11-11 (Mon)
連載のタイトルを変更した。「古代史俯瞰 by tokyoblog 「二つの百済」」というのはtokyoblog氏のサイトの名前そのまんまなので、この投稿から「tokyoblog氏の「二つの百済」について」と改題し、この変更は過去に遡って施した。
【是歲(490),魏虜又發騎數十萬攻百濟,入其界,牟大遣將沙法名、贊首流、解禮昆、木干那率眾襲擊虜軍,大破之。】
さて、何気なく『南斉書』「百済伝」の上記記事を引用してきたが、「漢籍電子文献」で前後の文を確認すべく検索すると、ナナナんと、「高麗伝」中の文として表示される!
少し目を凝らして文章を追っていくと、【高璉年百餘歲卒。隆昌元年,以高麗王樂浪公高雲為使持節、散騎常侍、都督營平二州諸軍事、征東大將軍、高麗王、樂浪公。】と確かに高句麗についての記述なのだが、少し下段に行くと、百済王牟都・牟大の話になっており、【制詔行都督百濟諸軍事、鎮東大將軍百濟王牟大】と牟大叙任の記事になっている!
よくよく見ると、「漢籍電子文献」では、
(校)原闕[建武三年原闕 此下缺一頁,脫高麗傳之下半篇,百濟傳之上半篇,各本同。原本每頁十八行,每行十八字。按元龜九百六十八:「明帝建武三年,高麗王、樂浪公遣使貢獻。」明帝紀不載,當亦為高麗傳缺頁中佚文。又建康實錄南齊高麗傳有:「其官位加(?)長史、司馬、參軍之屬。拜]
と校注が見えている。また、
則申一腳,坐則跪,行則走,以為恭敬。國有銀山,採為貨,並人參貂皮。重中國綵纈,丈夫衣之。亦重虎皮。」疑亦南齊書高麗傳缺頁中佚文也。又元龜九百六十三:「齊高帝建元二年三月,百濟王牟都遣使貢獻。詔曰:『寶命維新,澤被絕域。牟都世藩東表,守職遐外,可即授使持節都督百濟諸軍事、鎮東大將軍。』」當亦為百濟傳缺頁中佚文。
と、他伝の竄入を疑っている。
私の場合は『東アジア民族史Ⅰ正史東夷伝』であらまし眺め、原文は「漢籍電子文献」から引き、また細かい字句の検査は「百衲本」を開いているが、「漢籍電子文献」は底本が「宋大字本」と明記してあり、『東アジア民族史』では、
凡例(抜粋)
テキストは、汲古閣本を中心とし、百衲本・武英殿本・南監本を参照した。朝鮮史編集会編『朝鮮史』第一編第三巻・別録によるところが大きい。
と明記してある。
つまり、「汲古閣本」では闕文が無い!ということなんだろう。最初に「漢籍電子文献」から入っていたら、この【魏虜又發騎數十萬攻百濟】という記事を『南斉書』「高麗伝」中の文だと誤認していたかも知れない。
クワバラクワバラ、、、
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その18―
2019-11-11 (Mon)
「漢籍電子文献」の『南斉書』が「宋大字本」を底本としていると明記してあるので、手元の「百衲本」を開いてみると、これも「宋蜀大字本」とある。
なので、さっそくその「原闕」の箇所を開いてみた。

「漢籍電子文献」では、校注に続いて、【則申一腳,坐則跪,行則走,以為恭敬。國有銀山,採為貨,並人參貂皮。重中國綵纈,丈夫衣之。亦重虎皮。」疑亦南齊書高麗傳缺頁中佚文也。又元龜九百六十三:「齊高帝建元二年三月,百濟王牟都遣使貢獻。詔曰:『寶命維新,澤被絕域。牟都世藩東表,守職遐外,可即授使持節都督百濟諸軍事、鎮東大將軍。』」當亦為百濟傳缺頁中佚文。】と本文と同じサイズのフォントで表示されているが、上掲画像を見るに、次葉は【報功勞勤】に始まる。
つまり、校注に続く「佚文」二条は「宋大字本」にある文字ではなく、校注の続きなのではないか?
遠くから「天誅君大先生」の〝原典に当たるべし〟という教えが聞こえてくるようだ。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その18―
(hy注:その18がダブっているがそのままにしておく)
2019-11-12 (Tue)
昨夜の投稿で、
つまり、「汲古閣本」では闕文が無い!ということなんだろう。最初に「漢籍電子文献」から入っていたら、この【魏虜又發騎數十萬攻百濟】という記事を『南斉書』「高麗伝」中の文だと誤認していたかも知れない。
と書いたが、これはチョンボ!
『東アジア民族史1正史東夷伝』「高麗国伝」132ページで、
明帝の建武三年(四九六)(以下、原文を闕いている)[九]。
として、注[九]が以下の通り詳しく解説してある。
[九] 次の百済国伝にかけて、三二〇字前後欠落。本伝の佚文とみられるものに『冊府元亀』巻九六八(朝貢)の「明帝の建武三年、高麗王・楽浪公が使者を遣わして貢献した」という記事と、唐の許嵩の撰になる『建康実録』の「〔高句麗の〕官には長史・司馬・参軍などの官も加えている。跪拝するときは一脚を伸ばし、坐るときはひざまずき、行くときは小走りし、それで恭敬〔の礼〕をなしている。国には銀山があって、採掘して貨財としている。人参・貂皮もある。また中国の絞り染を貴重がり、丈夫はこれを着ている。また虎の皮も尊重する」(南斉高麗伝)という記事とがある。後者の一部は『翰苑』巻三〇高麗条の注に『斉書』として引用されているので、その佚文であることが明らかである。
なお参考までに記すと、『三国史記』の四九六年(文咨王五年)の記事に「斉の皇帝は〔高句麗〕王を進号して車騎将軍とした」とあり、少なくとも現存の史料中では独自の記事で、『梁書』武帝紀(本書一四三頁注三三)の記述から、史実と認められる。
そして、同書219ページ『南斉書』「百済国伝」冒頭では、
〈これより前は原文が欠けている〉
功績に報い、忠勤を労い……。〈以下略〉
とあるので、『南斉書』「高句麗国伝」から「百済国伝」にかけての闕文は、やはり「汲古閣本」においても「百衲本」と同様であるということのよう。
とんだ早とちりでお恥ずかしい限りだ。これが掲示板時代だったら一昼夜を隔てずにツッコミが入っていたのかも知れない。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その19―
2019-11-12 (Tue)
白石南花さんの「夫餘崇」というタイトルの投稿(「談話室」@2019年10月31日(木)11時12分35秒)に以下の文があって、頭に引っかかっていたが、今、ようやくわかった。
https://6247.teacup.com/toshifjjp/bbs?page=17&
この夫餘崇と言うのは、旧唐書の扶餘隆の事ではないでしょうか
この「崇」は「隆」を忌諱したものなんですね。かつて「魏代訪議の探求」という自分のページをまとめた時、以下のように書きました。
『史記』 魏臺訪議_____高堂崇對曰聞之先師物無也故事也言__無復所能於事者也(注ⅶ) 「凶奴伝」索隠注(注ⅲ)
ⅶ)「高堂隆」を「高堂崇」とするのは、唐・玄宗皇帝の諱・隆基を忌諱したもの。「隆」と「崇」は音は違うが、どちらも「高い」という意味をもっている。Yahoo!掲示板「邪馬台国論争が好きな人集まれ!!」#46592を参照のこと。
http://hyenanopapa.obunko.com/gidaihougi.html
んで、#46592はかの「天誅君大先生」の投稿で、以下の通り。
「闕」と「臺」(補足)@2006/7/22 9:59
補足しておきましょう。
この逸話は通典にもっと詳しく載っているのです。
>尚書曹訪云:「官僚終卒、依礼各有制。至於其間、令長以下、通言物故、不知物故之名本所依出。」高堂崇曰:「聞之先師、物、無也。故、事也。言無復能於事者也。」(注:避諱で崇←隆)
質問したのは尚書曹であって皇帝ではない。
「魏臺訪議」という書物には、高堂隆の受けた質疑が収録されているが、皇帝の下問もあれば小役人から聞かれて答えたことも書いてある。
史記集解では「高堂隆答魏朝訪曰」となっており、魏臺=魏朝。
つまり「魏臺」は魏の公務全般を包含するのです。
「天子そのもの」などというのは、中国史への無知無理解のかたまりです。
まあなんとスローなことかと白石南花さんの失笑を買いそうですが、、、(・_・;)
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その20―
2019-11-13 (Wed)
白石南花さんの「夫餘崇」について思いついたことを前投稿で書いたが、その後で重要なことに気が付いた。
『東アジア民族史2正史東夷伝』286ページ、「扶餘崇」に注して以下の通りある。
『旧唐書』『新唐書』の各百済国伝には扶除隆の孫として敬の名は見えるが、崇についての記述はない。なお、嘉靖本・宋本は崇を「其主」と記すが、武英武英殿本は「其王」に作る。
え――――――――っ!
同書『通典』「百済伝」を担当した人は、「夫餘崇」が「扶除隆」の忌諱によるものだと気が付かなかった!? 「天誅君大先生」や白石南花さんが気が付いたというのに、、、!?
同書『1』の方は、各書訳出者の氏名をそれぞれ担当箇所の末尾に明記してある。井上秀雄氏とか山尾幸久氏とか、、、ところが『2』の方には書いてない!よく見ると、冒頭凡例に執筆担当が書かれてある。百済伝は坂元義種氏という、、、
この方も大家。あまり些細なことには気が回らなかったのだろうか、、、
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その21―
2019-11-13 (Wed)
tokyoblog氏の「二つの百済」について自分なりの考えをつらつら書いているが、これまで長い間、朝鮮半島問題について疎かにしてきたツケか、なかなか進まない。
とりあえずは『南斉書』「百済伝」の【是歲(490),魏虜又發騎數十萬攻百濟,入其界,牟大遣將沙法名、贊首流、解禮昆、木干那率眾襲擊虜軍,大破之。】については、どうも疑わしい、、、というところまで来たとは思うが、ささやかな一歩でしかない。
問題点は多いが、次はtokyoblog氏の以下の記述について考えてみたい。
百済が滅亡する以前の古い時代で、百済と高句麗の力関係が拮抗していた時代に、百済は、高句麗領域を飛び越えて、遼西の晋平郡晋平県(現在の朝陽と北京の間付近)に百済郡を設置して、後方から高句麗を牽制していた時代があります。
中国の史書「通典百済伝」に、「660年の百済滅亡後、長城付近(遼西東部の百済郡)の残留民は段々と数が少なくなり、気力も尽きて突厥とか靺鞨族に投降し、百済郡太守扶余崇は、滅亡した百済(熊津、扶余)に帰ることが出来ないで、あちこちうろうろし、遂には滅んでしまった」とあります。
http://tokyox.matrix.jp/wordpress/%E4%BA%8C%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%99%BE%E6%B8%88/
文脈的にみると、上掲引文の前半で遼西百済について言及し、続いて「通典百済伝」を引いているのだから、遼西百済という理解に資するものとして引用したものと見ていいのだろう。
では、『通典』「百済伝」から当該箇所を引く。
國西南人島居者十五所,皆有城邑。
後魏孝文遣眾征破之。後其王牟大為高句麗所破,衰弱累年,遷居南韓地。隋文開皇初,其王夫餘昌遣使貢方物,拜為帶方郡公、百濟王。大唐武德、貞觀中,頻遣使朝貢。顯慶五年,遣蘇定方討平之。舊有五部,分統三十七郡、二百城、七十六萬戶,至是以其地分置熊津、馬韓、東明等五都督府,仍以其酋渠為都督府刺史。其舊地沒於新羅,城傍餘眾後漸寡弱,散投突厥及靺鞨。其主夫餘崇竟不敢還舊國,土地盡沒於新羅、靺鞨,夫餘氏君長遂絕。
【國西南人島居者十五所】とあるから、この時点で遼西百済について述べてあるものとは考えにくい。次に【後魏孝文遣眾征破之】が謎の記述。【後其王牟大為高句麗所破】とある。これは高句麗の攻撃による漢城陥落と熊津への遷都のことを指すのだろうが、それは475年前後のことだから、【後魏孝文遣眾征破之】の記述が490年のこととすると時期が前後してしまう。坂田隆氏もこのあたりについて触れていたようだが、新たな問題点となるのだろうか。
『通典』の記事に戻る。顯慶五年(660)、百済は唐が遣わした蘇定方によって討たれて平定されてしまう。それに続く記述の内、【其舊地沒於新羅】とあるから、ここで述べられている百済は遼西百済ではありえないことになる。問題の【城傍餘眾】。tokyoblog氏はこれを「長城」と解釈しているが、前文からの流れを汲むとこの「城」を「長城」と解釈するのは難しそうだ。ただ、【散投突厥及靺鞨】とあるのが確かに引っかかる。また、【土地盡沒於新羅、靺鞨】と、ここにも「靺鞨」が出てきて、理解が更に苦しくなる。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その22―
2019-11-14 (Thu)
「二つの百済」の件でいろいろ検索している途中で、オモシロイサイトを見つけた。
社会学研究家・暁美焔(Xiao Meiyan)氏の 「虚構の楽浪郡平壌説」
http://lelang.sites-hosting.com/naklang/rakurou.html
その見出しを抜粋してみると、
1. 中国史書が示す楽浪郡、帯方郡の場所
1.1 楽浪郡の場所は遼東
1.2 帯方郡の場所も遼東
1.3 後世の認識でも楽浪郡の場所は遼東
2.1. 倭国は朝鮮半島国家
2.2. 馬韓、百済は遼東半島国家
2.3. 古朝鮮は遼東国家
3. 破綻している楽浪郡平壌説
4. 虚構の古代史と決別せよ
これだけ眺めても結構訴求力ありそう。
同氏には別に「邪馬台国論争の真相と正当化の概念が無い日本社会」というページもある。
http://lelang.sites-hosting.com/naklang/shinsou.html
このページの中程に邪馬台国と楽浪郡の位置を示した図が2枚掲げてあるが、邪馬台国が韓半島南端付近に示してある。これまで邪馬台国をここに比定した論者はいなかったかも、、、だとしたら新説としての位置は尊重されねば、、、
ページの下の方に、推奨として山形明郷氏の『卑弥呼は公孫氏』が紹介してある。ああ、あの山形氏か!
韓国学会でも恐らくは否定的に見られているのだろうが、この「虚構の楽浪郡平壌説」に対して、ご苦労さまにも批判の記事を書いている方がいらっしゃった!
「虚構の楽浪郡遼東説」
第1話
https://ameblo.jp/teras0118/entry-12094682024.html
第2話
https://ameblo.jp/teras0118/entry-12095031146.html
第3話
https://ameblo.jp/teras0118/entry-12095074207.html
第4話
https://ameblo.jp/teras0118/entry-12095140664.html
せっかく遭遇したサイトなので、備忘録として書き留めておく。
hy注)この「虚構の楽浪郡遼東説」を書いている方は寺坂国之さんという方で、かなりハイレベルな方とお見受けしますが、「女王国への道~奴国と女王国(8)」を覗いてみると、以下のような一節がありました。
この女王国への行程については、私が師として最も尊敬している『「邪馬台国」はなかった』の著者・古田武彦先生の行程論を一部参考にさせていただくことにします。
うーむ、ここはひとつ「二つの百済」から外れて脱線してみるところか?
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その23―
2019-11-14 (Thu)
『騎馬民族史1正史北狄伝』『魏書』「勿吉伝」を眺めていたら、百済が出てきた。「漢籍電子文献」から、まず原文を引き、拙読を加えてみる。
『北魏書』勿吉伝
去延興中,遣使乙力支朝獻。太和初,又貢馬五百匹。 乙力支稱:初發其國,乘船泝難河西上,至太𣳅河,沉船於水,南出陸行,渡洛孤水,從契丹西界達和龍。自云其國先破高句麗十落,密共百濟謀從水道并力取高句麗,遣乙力支奉使大國,請其可否。詔敕三國同是藩附,宜共和順,勿相侵擾。 乙力支乃還。從其來道,取得本船,汎達其國。九年,復遣使侯尼支朝獻。明年復入貢。
去る延興中(471-476),乙力支を遣使し朝獻す。太和(477-499)初,又馬五百匹を貢ず。 乙力支は「初め其國を發し,乘船し難河を泝りて西上し,太𣳅河に至る,船を水に沈め,南に出でて陸行し,洛孤水を渡る,契丹の西界より和龍に達す」と稱す。自ら云ふ其の國は先ず高句麗の十落を破り,密かに百濟と共に水道より并力して高句麗を取るを謀る,乙力支を遣はして大國(北魏)に奉使して,其の可否を請ふ。詔敕するに三國は同じく是藩附(属国)にして,宜しく共に和順し,相侵擾すること勿かれと。乙力支は乃ち還る。其の來し道より,本の船を取得し,汎(うか)んで其の國に達す。九年,復(また)侯尼支を遣使して朝獻す。明年復入貢す。
延興中:『冊府元亀』巻969外臣部朝貢二によれば、延興五年(475)10月に勿吉朝献のことが見える。
太和初:『冊府元亀』外臣部朝貢二によれば、太和二年(478)八月に勿吉朝献のことが見える。
以上、『騎馬民族史1正史北狄伝』345ページの注5注6による。
勿吉が百済と并力して高句麗を攻めようとしていると。勿吉と百済って高句麗を挟んでかなり離れている。ここに見えるような事実があったのか?
10/29にteacup談話室に白石南花さんあての投稿をした中で、『通典』辺防一百済の「突厥とか靺鞨族に投降し」という箇所を引いたが、ここに「靺鞨族」が出てくる。百済滅亡に際して「城傍餘眾後漸寡弱,散投突厥及靺鞨」とあるが、半島南西部の百済と、中国東北部辺りと思しき靺鞨=勿吉とがその時はなかなか結びつけて考えられなかった。しかし、上掲『北魏書』「勿吉伝」をみると、勿吉と百済とは何らかの連絡があったのでは?とも勘ぐりたくなる。
迷路はどんどん複雑になっていくような予感が、、、(@_@;)
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その24―
2019-11-16 (Sat)
『騎馬民族史1正史北狄伝』を開いたついでに『北魏書』「蠕蠕伝」を読んでみた。長い!それに詳細だ!
百衲本で開いてみると『北魏書』「蠕蠕伝」はざっと半葉9行18格を数え、おおよそ21葉半あるので、全体の文字数にして約7,000文字。『魏志』「倭人伝」の3倍半の分量があることになる。
しかも、冒頭に始祖伝説が僅かに語られるだけで、あとはほぼ北朝との関係記事で埋め尽くされている。『魏志』「倭人伝」に土風記事がかなり多いのとは違う。大量に年次と人名・地名が出てくる。
北魏孝明帝正光二年、蠕蠕の阿那瓌(あなかい)へ粛宗から贈られた品目は、卑弥呼への下賜品を思わせるが、ボリュームがその比ではない。ここまで詳細な記録が残っているというのは、次の王朝が禅譲を受けたからなのか、その辺りのことは知らない。
烏桓、鮮卑も含めた北狄伝を調べようとするのは、一介の素人には無理だ。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その25―
2019-11-16 (Sat)
『旧唐書』北狄靺鞨に以下のようにある。
【靺鞨,蓋肅慎之地,後魏謂之勿吉,在京師東北六千餘里。東至於海,西接突厥,南界高麗,北鄰室韋。】
『旧唐書』によれば、靺鞨は突厥と接している。ならば、『通典』の【散投突厥及靺鞨】も両国が併記してあることについては理解できる。ただ、それでも百済が突厥及靺鞨とは高句麗を挟んでいることには違いがない。
『旧唐書』東夷百済国には以下の記事も見える。
【(永徽)六年(655),新羅王金春秋又表稱百濟與高麗、靺鞨侵其北界,已沒三十餘城。顯慶五年,命左衞大將軍蘇定方統兵討之,大破其國。】
この「百濟與高麗、靺鞨侵其北界」のうち、百済・高句麗についてはいいが、「靺鞨」がどうしても理解できない。百済と高麗による新羅侵攻に靺鞨もその軍を加担させていたということなのか。
『旧唐書』東夷高麗にはまた、
【高麗者,出自扶餘之別種也。其國都於平壤城,即漢樂浪郡之故地,在京師東五千一百里。東渡海至於新羅,西北渡遼水至于營州,南渡海至于百濟,北至靺鞨。】
ともある。新羅は高麗から「東渡海」というのは、一体当時の地理観はどうなってるの?と頭をかしげたくなる。
『新唐書』でも、【地東跨海距新羅】という。
『旧唐書』『新唐書』における高麗、百済、新羅そして靺鞨の位置関係はかなりあやふやだ。
上述の「百濟與高麗、靺鞨侵其北界」について調べると、『新唐書』黑水靺鞨の以下の記事がなにやら参考になりそうだ。
【武德五年(622),渠長阿固郎始來。太宗貞觀二年(628),乃臣附,所獻有常,以其地為燕州。帝伐高麗,其北部反,與高麗合。高惠真等率眾援安市,每戰,靺鞨常居前。帝破安市,執惠真,收靺鞨兵三千餘,悉坑之。】
「帝伐高麗」というのは7世紀中葉の太宗による高句麗征討のことだろうから、その際、靺鞨の北部は却って高句麗と合一した。つまり、靺鞨と高句麗は時に応じて連携したということなのか。
ここまで調べてきたが、もう頭の中が麻のごとく乱れに乱れ、、、
ノーミソに休養を与えねばオーバーヒートしそうだ、、、
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その26―
2019-11-16 (Sat)
今度は芮芮(ぜいぜい、ぜつぜつ)について。『北魏書』では蠕蠕(ぜんぜん)と記す。
『宋書』芮芮伝によれば、
【芮芮一號大檀,又號檀檀,亦匈奴別種。自西路通京師,三萬餘里。】
とある。
そして『南斉書』芮芮伝では、劉宋昇明二年(478)、当時国政を補佐していた太祖(斉の蕭道成=しょうどうせい。当時は宋の宰相)は驍騎将軍の王洪軌を芮芮に派遣して期日を定めて共に北魏を伐とうと申し入れる。
翌斉の建元元年(479)、芮芮の主は三十万騎を動員して南下し、北魏内に侵入したという。この時は北魏が守備を固めたので交戦はなかった。
永明元年(483)王洪軌が京師(建康)に戻ってくる。帰路について『南斉書』は【經途三萬餘里】と書く。『宋書』と一致する。
つまり、芮芮は南朝と組んで北魏を伐とうとしたというわけだ。
『南斉書』芮芮伝によると、今度は丁零胡が南下してきたため、芮芮は南下し、その侵攻に対して北魏孝文帝は数十万騎を派遣したが寒気のため人馬の死亡が多数に上ったという(以上『騎馬民族史1正史北狄伝』より要約抜粋)。
ここで言いたいことは、南北から北魏を討つために南朝の使者は芮芮へ「三萬餘里」を経て旅したということ。
そして、芮芮や北魏の騎馬軍団は「三十万」とか「数十万」とかいう規模であった、ということ。
これらの数字は一体信じられるのだろうか?
2019-11-07(18:41) に「tokyoblog氏の「二つの百済」について―その13―」の中で、
北魏からしてみれば遼西百済など【騎数十万】を差し向けるほどの勢力でもあるまい
と書いたが、「遼西百済」相手としては言えても、北魏が実際に「騎数十万」を動かせるのかも知れないとは、「芮芮伝」をみれば言えるのかも知れない。
とりあえず、この辺りで文章を一旦切らないと、話がどんどん脈絡を失いそうだ。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その27―
2019-11-18 (Mon)
2019-11-07(23:49) 投稿の「tokyoblog氏の「二つの百済」について―その14―」で、
中国正史により深くこの事象についての記述を求めるとすれば、おそらくは『北史』がもっとも真相に近いのではないかと思えるが、この途もまた相当に険しそうだ。
と書いたが、ペケなので訂正する。
三﨑良章氏の『五胡十六国 中国史上の民族大移動』という本を図書館から借りてきて読んでいるが、その第二章に以下のように解説してある。
第一節 『晋書』と『魏書』と『十六国春秋』
五胡十六国時代を考える際、最も重要な史料は『晋書』と『魏書』、そして『十六国春秋』である。
具体的に言うと、『晋書』百三十巻のうち、最後の三十巻を占める「載記」、『魏書』の巻九五・九六・九七・九九の計四巻、そして佚文を集めるなどした湯球『十六国春秋輯補』である。
道のりがますます遠く・険しくなってゆく。
思えば、11/3の白石南花さんのコメントに、
晋書載記にはその後の百済新羅がどのような状況だったかわかる話があります。
咸康七年の記述に
句麗、百濟及宇文、段部之人,皆兵勢所徙,非如中國慕義而至,咸有思歸之心。
百済の兵が連れてこられています。
これは北燕と高句麗の戦争の結果連れられてきた人々でしょう。
つまり百済は高句麗と共に戦っています。
また太元四年と思われる記述に
分遣使者徵兵於鮮卑、烏丸、高句麗、百濟及薛羅、休忍等諸國,並不從。
薛羅は恐らく新羅でしょう。
つまり実際はどうかはともかく、半島南部を徴兵対象としてみています。
これは四世紀に入ると半島は高句麗の影響下にあり、北燕に対する敗北で北朝のテリトリーとしてみなされていたのでしょう。
とあるが、大きなヒントを下さっていたことにようやく気が付いた。
どうしよう、、、鮮卑の海で遭難しそうだ、、、
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その28―
2019-11-21 (Thu)
三﨑良章『五胡十六国 中国史上の民族大移動』を読んだ。その190-192ページで、
僑州郡県
南下してきた流民に対し、東晋では集団をそのまとまりを保ったまま、僑州・僑郡・僑県という北帰を前提とする仮の行政区画を設けて受け入れ、流民の把握と税役徴収を図った。そのために江南に華北の社会が再生され、その結果西晋の貴族制も維持されていったのである。こうした僑州郡県は「十六国」でも設置された。前燕では『晋書』慕容廆載記に、
「ときに洛陽・長安の二京が陥落し、幽州・冀州は没落した。慕容廆は刑政が立派で、懐を虚しくして人々を引き納れたので、流亡の士庶は、多く子供を背負ってこれに帰した。廆は郡を立てて流人を統治した。すなわち冀州の人で冀陽郡を作り、豫州の人で成州郡を作り、青州の人で営丘郡を作り、并州の人で唐国郡を作った。そして賢才を推挙し、庶政を委ねた。」
とあるように、東晋の僑郡に相当するような名称の郡を置いて流民を定住させた。また前涼でも『晋書』地理志に、
「永寧中、張軌は涼州刺史となり、武威に鎮した。そして上表して、秦州・雍州から流移した人を合して、姑臧の西北に武興郡を置き、武興・大城・烏支・襄武・晏然・新鄣・平狄・司監等の県を置いた。また西平郡の一部を分けて晋興郡を置き、晋興・枹罕・永固・臨津・臨鄣・広昌・大夏・遂興・罕唐・左南等の県を置いた。」
とあり、河西回廊や湟河・黄河本流流域に流民のための郡県を新設したのである。こうして移住した人々のなかから前燕は漢人知識人を積極的に起用し、また前涼では「多士」と称されるような名族・知識層が形成されるのである。
また後趙では塢を陥落させると、懐柔・安堵のために塢主に官職を与えたり、部衆を軍士として利用し、あるいは農耕に従事させた。こうした政策は後趙の勢力拡大につながったといえよう。
僑州郡県の設置にせよ、塢集団の活用にせよ、「五胡」諸国は漢族をその政権内に取り込んで経済基盤構築に活用し、あるいは政治機構確立に利用したのである。
と延べ、また、203ページでは、
こうした漢人知識人を積極的に活用する方策は前燕でも行なわれた。前燕は前趙・後趙と異なり、遼東・遼西で支配を確立していく過程で、中原の混乱を逃れてきた漢人士人を政権に組み入れた。そのなかには昌黎太守裴巍(はいぎ)や東夷校尉封釈の子で幽州参軍の封抽など、西晋の地方官経験者やその子孫である漢人の有力者が含まれていた。そして前燕も彼らを謀主・股肱などという地位に処遇したのである。
とも述べる。
2019-11-04(19:13)の投稿「tokyoblog氏の「二つの百済」について―その8―」の中で、『東アジア世界における日本古代史講座3 倭国の形成と古文献』窪添慶文「楽浪郡と帯方郡の推移」から「僑郡」についての解説を引いたが、三﨑良章氏の該書はより詳しく「僑州郡県」について解説してあり、思い過ごしかも知れないが、どうも「遼西百済」というものについて、また少し步をすすめることが出来たのかも知れない。問題解決の核心は〝漢人〟が握っていると見て間違いないだろう。
ただ、やはり『晋書』「慕容廆載記」については、より詳しく調べないといけないのだろう。道の険しさはちっとも改善されないし、峰の高さはより高くなってきたように映る。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その29―
2019-11-28 (Thu)
少し調べ物をするために、一二冊本を読んでいると、乍ち1週間が過ぎてしまう。
泊勝美氏の『古代九州の新羅王国』を久しぶりに読み返した。例の『隋書』「裴清の道行き文」中の「秦王国」のことが頭に浮かんだからである。同書は序章として「謎の秦王国」と掲げてあるとおり、この「秦王国」について考究したもので、非常に重い。
その一節に以下の通りある。78-79ページ、
ところで、この弓月君の渡来説話は、全体として、漢氏の渡来説話と非常によく似ている。
漢氏については、『日本書紀』は応神二〇年九月の条に、
倭漢直(やまとのあやのあたい)の祖阿知使主、其の子都加使主、並びに己(おの)が党類(ともがら)十七県を率いて来帰(もうけ)り。
と、あり、『新撰姓氏録』の逸文(「坂上系図」)は、意訳すると、
「阿智王は応神天皇の時に、本国(中国)の乱を避けて、母と妻子と母弟および七姓の漢人らを連れて帰化したが、その時、彼は自分の本郷の人民が離散して高麗・百済・新羅などの国にひろがっているから、使を遣わして召し寄せてもらえれば幸いだと上奏した。天皇はすぐ使いを遣わした。その結果、次の仁徳天皇の代になって、それらの人民が村落をあげて随って来た。その子孫が高向村主(たかむこのすぐり)をはじめとする数多くの村主姓の氏である」と、あるのである。
これだけ酷似している以上は、漢氏か秦氏のどちらか一方が他方のまねをした、と考えるのが常識というものであろう。
おそらく、秦氏の方がまねをしたのであろうと思われる。なぜなら、漢氏がまねをしたとすると、実際には漢氏は秦氏よりも発展し、勢力をもつようになったのに、それにもかかわらず、率いた人民の数を秦氏の一二〇県に対して、一七県という少ない数にとどめたのはおかしいし、また、渡来の年代も秦氏より前にもっていきそうなものだからである。
漢氏の渡来説話も、もちろん疑わしいわけであるが、秦氏はその漢氏と張り合おうとする対抗意識から、前記のような伝承を創作したということができるであろう。
『新撰姓氏録』はもとより、『記紀』での渡来説話が果たしてどれほどの史実性があるのか不明であり、額面通り受け止めるのは恐らく正しくないのだろうとは思う。しかし、、、
「応神天皇の時に、本国(中国)の乱を避けて」という部分について考えてみれば、仮にこれが史実ではなく後代の創作であったとしても、恐らくは4世紀頃と思われる応神天皇の時代に中国が乱れていたという点は、紛れもなく歴史的事実である。漢氏や秦氏の渡来が中国での乱世に結びつけて語られるということは、五胡十六国の大混乱による人民の流移は海を隔てた倭列島まで実際に及んでいたと考えても大過無いのだろう。
特に、「tokyoblog氏の「二つの百済」について―その28―」で引用した三﨑良章氏の『五胡十六国 中国史上の民族大移動』中の「僑州郡県」の具体的事例と、上掲の秦氏・漢氏の渡来説話とが〝似ている〟と感じるのはそれほど飛躍した認識とも言えないのではないか。特に「県」という文字。あるいは7世紀以降の半島よりの渡来民が日本各地に居処を与えられて「郡」を称したという事実。
倭あるいは日本の古代史を中国を中心とする東アジア史と結び付けずに解き明かそうとすることは、懐かしい言葉を用いて言えば〝ナンセンス!〟の一語に尽きるのではないだろうか。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その30―
2020-01-19 (Sun)
あちこち寄り道をしていると、すぐに一月二月が経ってしまう。
調べ物の途中で、〝僑郡県〟に関する記述に出くわしたので、いつもながらの釋読を試みた。
『隋書』卷二十四 食貨志 晉
【晉自中原喪亂,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,並謂之僑人。皆取舊壤之名,僑立郡縣,往往散居,無有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑濕,無有蓄積之資。諸蠻陬俚洞,霑沐王化者,各隨輕重,收其[貝炎]物,以裨國用。又嶺外酋帥,因生口翡翠明珠犀象之饒,雄於郷曲者,朝廷多因而署之,以收其利。歷宋、齊、梁、陳,皆因而不改。其軍國所須雜物,隨土所出,臨時折課市取,乃無恒法定令。列州郡縣,制其任土所出,以為徵賦。】
拙読「晉の中原を喪亂(注1の②)しより,元帝(東晋初代皇帝司馬睿)は江左(長江下流南岸)に寓居(仮ずまい)し,百姓(多くの人民、多くの役人)の自(みずか)ら拔けて南に奔(はし)る者は,並びに之を僑人(=故郷を離れて他の土地に住む人)と謂(い)ふ。皆、舊壤(=以前の土地、出身地)の名を取りて,郡縣を僑立(=仮に建てる)し,往往(=あちこち)散居して,土著(=土着)を有(たも)つは無し。而(しこう)して江南の俗は,火耕水耨(注2),土地卑濕(ひしつ=土地が低く、湿気の多いこと),蓄積の資を有(たも)つこ無し。諸(もろもろ)の蠻陬(ばんすう=えびすの地)俚洞(りどう=南方の蛮族のことか)の,霑沐(てんもく=恵みを与える)王化は,各(おのおの)輕重に隨(したが)ひ,其の[貝炎]物(注3,注4)を收め,以て國用(=国の費用)を裨(おぎな)ふ。又、嶺外(=指五嶺(注5)以南地區)の酋帥(集団の中心となる者。また、蛮人のかしら)は,生口(牛馬の類の家畜)翡翠明珠犀象の饒(じょう=豊か)なるに因りて,郷曲(きょうきょく=片田舎)に雄(まさ)る者を,朝廷は多とし因而(これによりて)之を署(しる)し,以て其の利を收む。宋、齊、梁、陳を歷(へ)て,皆、因而(これによりて)改めず。其の軍國の雜物を須(もち)ひる所,出る所の土に隨(したが)ひ,臨時(=時に応じて)折課市取(語義未詳),乃(すなは)ち恒法定令(=定まった法令)無し。州郡縣は列(おしなべ)て,其の任を出づる所の土に制(さだ)め,以て徵賦(=徴税)を為す。」
注1.喪亂:①人が死んだり争乱が起こったりして、世が乱れる。②国土をうしない、人民が離散する。
注2.火耕水耨:水耕の後、水を田に入れて稲を植え、雑草を刈り取って、育てる農法。
注3.[貝炎](たん):金銭で罰を免れる。罪を償う。また、そのための金銭。
注4.[貝炎]物:指南方少数民族向朝廷輸納的貨物。南方の少数民族が朝廷へ向けて納める貨物を指す。by「漢典」
注5.五嶺:中国江西省と広東省との境にある山脈中の大庾、始安、臨賀、桂陽、掲陽の五つの峰。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その31―
2020-01-21 (Tue)
試しに、「漢籍電子文献」で「僑立」を検索してみた。数字は左が「筆数」で右が「命中」。多分、「筆数」とはヒットした条文の数で、「命中」が出現する字句の数ではなかろうか、、、なんてとりあえずは解釈してみる。
1 宋書 (梁)沈約撰;楊家駱主編 底本:宋元明三朝遞修本 17 67
2 晉書 (唐)房玄齡等撰;楊家駱主編 底本:金陵書局本 7 16
3 南齊書 (梁)蕭子顯撰;楊家駱主編 底本:宋大字本 4 5
4 隋書 (唐)魏徵等撰;楊家駱主編 底本:宋刻遞修本 4 4
5 舊唐書 (後晉)劉昫撰;楊家駱主編 底本:清懼盈齋刻本 2 3
6 南史 (唐)李延壽撰;楊家駱主編 底本:元大德本 2 2
7 北史 (唐)李延壽撰;楊家駱主編 底本:元大德本 1 1
8 清史稿 趙爾巽等撰;楊家駱校 底本:關外二次本 1 1
『宋書』の「命中」67が目立つ。続いて『晋書』だが、これらはいずれも南北朝対立の前半期に当たる。胡族の侵入で華北が大混乱に陥り、その混乱から逃れようとする民衆の大移動が発生したことは、最近読んだ関連書籍からも明らか。
いや、そもそも晋朝自体について【晋江左僑立】と明記されているくらいだから、国というか王朝というか、そんなものまで「僑立」されてしまう時代だったということ。
こんにちの中国では春節に延べ三十億人が大移動するという。千数百年昔の南北朝時代にも生死をかけた悲惨な民族大移動が延々と繰り返されていたが、このたった一文字「僑」からも、それが窺えるのではないだろうか。
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その32―
2020-01-21 (Tue)
検索の途上、ビンゴ!というサイトに遭遇した。「東晋南朝僑流人口的輸出與輪入」。
http://www.iqh.net.cn/info.asp?column_id=3839
本文・注を合わせて約4万文字位ある。訳すなどとても無理。なので、初めの方をチラチラと眺めていたら、興味深い一節が目に止まった。
【又所謂“僑”,主要指西晋永嘉亂後不斷南徙的北方官民】
現代語に拙訳を試みれば、「又、いわゆる“僑”は、主に西晋の永嘉の乱のあと、絶え間なく南へうつって来た北方の官民のことである」。
非常にわかりやすい説明。
そう言えば、昔、学校の英語の先生が仰っていた。英語が上達したいならば、英英辞典を読むといい、、、と。なるほど!漢文でも同じなんだァ、、、
tokyoblog氏の「二つの百済」について―その33―
2020-01-21 (Tue)
試しに、【又所謂“僑”,主要指西晋永嘉亂後不斷南徙的北方官民】の部分を、Google翻訳にかけてみると、
いわゆる「海外の中国人」とは、主に、西陣王朝の永家の反乱の後、南に移動し続けた北部の役人と民間人を指します。
と翻訳される。まあ、意味は通じるが、このままコピペして先生に提出したら叱られるだろうなぁ、、、
Googleのページ翻訳は、少し違っていて、
西J時代の永嘉以降、南に移住してきた北部の役人と民間人を指し
となって、〝なんじゃらほいっ〟という状態、、、(+_+)
河内春人氏『倭の五王 王位継承と五世紀の東アジア』から
2020-04-08 (Wed)
河内春人『倭の五王 王位継承と五世紀の東アジア』221頁
そうした情勢下で四九〇年に北魏が百済を攻撃した。海を越えて襲来したことになるが、中国が百済を直接攻撃するのはきわめて異例である。
これはかつて「tokyoblog氏の「二つの百済」について」という連載をこのブログに書いた中で出てくる話だ。「その16―2019-11-11 (Mon)」で以下のように書いたが、北魏の「騎數十萬」が「海を越えて襲来した」というのは、いくらなんでもあり得ないだろう。
『南斉書』に見える【是歲(490),魏虜又發騎數十萬攻百濟,入其界,牟大遣將沙法名、贊首流、解禮昆、木干那率眾襲擊虜軍,大破之。】というのは甚だ疑わしい。
と書いたとおりだ。
158-159頁。
慣用表現が生んだ〝記憶の改竄〟
要するに上表文の「東征」「西服」は当時の慣用表現である。古墳時代に戦争の痕跡が見えないという考古学の指摘をふまえると、それを歴史事実として理解すべきではない。しかし、過去にあった出来事であるかのように外交上の修辞として上表文に記されたはずのそれは、いつしか倭国の歴史として意識されるようになる。
そして、それは倭王権による列島統一における武力討伐の歴史としてのちに記憶されるようになる。上表文では宋皇帝のために行ったとする東西征討が、武以降に中国との外交が途絶することによって宋皇帝という存在が消え、倭王権自身のための東西征討へと論理がすり替わっていく。その過程で話にリアリティを持たせるための肉付けが加わって伝承が形成される。それがヤマトタケル伝承と呼ばれるものなのではないか。
これまで武力討伐という史実が、上表文の記載と記・紀の伝承にそれぞれかたちを変えて記されたと思われてきた。しかし、むしろ逆であり、中国の表現規範が上表文に取り込まれて伝承化し、史実として捉えられるようになったのである。いわば記憶の改緩か生じたといえる。
上表文は当時の情勢を知るうえでの貴重な史料であることほ間違いない。ただし、そもそも史実を正確に記すことを目的としていない。その点に気を付ける必要がある。
倭王武の上表文「東征」「西服」からヤマトタケル伝承が生まれた、とする考え。こういう考え方は嫌いではないが?もある。そんなことで詳細なヤマトタケルや景行の伝説が『記紀』『風土記』に残るのか?国内史料との突合を行わなければ軽々には言えまい。古墳についての考古学的知見に影響されているが、156頁で下垣仁志氏の所説「古墳時代に列島社会で大きな戦争は確認できない」を引くが、文献解釈に援用するというのは軽率ではないか?