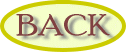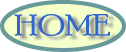一、『三国志校勘記』は稿本七冊,其の中で定本は四冊,参考本は三冊にして,参考本を原始校記と為し,定本は参考本自(よ)り来たる。参考本と定本は均(ひと)しく宋本と殿本の対校を以てし,詳(くは)しく異同を列す。原始校記は又他本十種を参考にし,行間に夾注し,定本は多く未だ過ちて録せず。此次*の整理は仍(なほ)定本を尊用すと雖(いへど)も,但し参考本中に定本の各条を舎棄*有る,及び批語に関(かかは)り有る所は均しく予(あらかじ)め収入せり。原始校記は間(まま)殿本を以て底本と為し、宋本を校本と為すの有るは,今概ね互ひに倒を行ふ。
二、衲史(百衲本二十四史)『三国志』の底本として用ふる所は南宋紹煕建本と為し,『魏志』前三巻は紹興本を以て配補す(以上「宋」と簡称す)。対校本は清乾隆武英殿本と為す(「殿」と簡称す)。参考本に晋抄本①,大字宋本②(「大宋」と簡称す),宋補本③(「宋補」と簡称す),另宋本④(「另宋」と簡称す),元本(「元」と簡称す),明南監本(「南」と簡称す),明北監本(「北」と簡称す),明毛氏汲古閣本(「汲」と簡称す),清汪氏校本⑤(「汪」と簡称す),清孔継涵校本(「孔」と簡称す)有り。
三、原始校記は毎巻均しく三部分,当(まさ)に是(これ)初校、復校、三校として得る所,今依次(=順次)合併して一と為す。
四、原校記の摘句*偶(たまたま)錯誤有らば,今影印本に拠りて改正す。
五、原稿の上下闌*外及び行間に批語有るは,係りて張菊老*、汪仲谷、蔣仲茀三先生の手に出で,凡(およ)そ異文の是非と関り有るは均しく備注闌に録入す。因(ちな)みに校記は張菊老其の成を総(すべ)るに由(よ)りて,故に標識姓名を復さず。批語の一条に止(とど)まらざるは,○を加へ隔開す。
六、原始校記の下闌外に張菊老の手批「修」、「補」、「刪」有るは,影印本衲史『三国志』に已(すで)に照改を経(ふ)。又原(もと)未批修として実は修する者,原(もと)批修として実は未だ修せざる者有るは,均しく備注闌に於て注明す。
七、校勘記は共に四千六百有五条を出校し、一千三百三十七条を修字す。
八、校勘記定本は前(もと)漏修誤修字表の原(はじめ)に有するも,今は校勘記末に附す。
九、原校記中、晋抄本(又称古写本)と宋本の異文に未出校の漏れ有るは,今『校史随筆』に拠り補充し、並びに影印晋抄本に拠り(中華書局標点本『三国志』巻首を見よ)訂正す。
附注:
①晋抄本は即ち張菊老『校史随筆』云ふ所の古写本にして,一九二四年新彊鄯善県にて出土在り。『呉志』八十行と為す。
②疑ふらくは即ち傅沅叔所蔵の影写宋刻大字本なり。『蔵園群書経眼録』云:「此の本の行款*と蜀大字本『史記』とは正に同じにして,疑ふらくは即ち蜀本従(よ)り出ず。」又云ふ:「遍(あまねく)各家蔵目を考ふるに,九行本を以て著録するは無し。」惟(おも)ふに蔵園存巻の欠巻一(よ)り八は,而るに『三国志校勘記』大字本『魏志』巻三に却って見へ,沅叔自(よ)り借るに非ざる似(ごと)し。菊老の拠る所は当(まさ)に另*一残宋本に係る。
③呉書校勘記末を見よ。菊老は『涵芬楼燼余書録』に於て曽(かつ)て云ふ:「適園張氏の有す呉志残本二冊は,均しく補版甚だしく多し。」即ち適園蔵本の似(ごと)し。
④另宋本は何本と為すか確かに指す能はず。
⑤汪校本は何人の所校と為すか考を待つ。