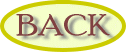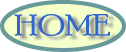〈書き下し文〉
太平御覧ハ宋ノ一大著作ト爲ス。其ノ引ク所ノ經史圖書ハ凡(オホヨ)ソ、一千六百九十種。今傳ハラ不(ザ)ル者、十之七八。或ヒハ古籍自(ヨ)リ輯(アツ)ムト謂ヒ、或ヒハ類書ヨリ原出スト謂フ。之ヲ要スルニ徴引スルコト賅博ニシテ多ク前言往行ヲ識(シル)シ、洵(マコト)ニ珍トスルニ足ル也。今行フ所者(ハ)、明代ノ活字本有リ、錫邑(現・無錫市)刻本有リ。其ノ從(ヨ)リテ出ズル所ノ周堂序ニ謂フ、其ノ祖曾(カツ)テ故本ヲ得、黄正色ノ序ニ則チ謂フ、薛登甲ノ善本ヲ校スル所ニ據リテ繕寫シ刻ニ付ス。然リテ胡應麟ハ其ノ姓名顚倒セルヲ世代(代々)ノ魯魚學者ノ病ナリト譏(ソシ)ル焉(ヤ)。明ノ文淵閣ノ書目ハ、一部一百三十册、一部一百册ヲ存シ、均シク殘缺ナリ。其ノ後蘇人朱文游・周錫瓚・黄丕烈・汪士鐘家ニ於テ散出遞入ス。最後ニ湖州ノ陸心源ノ僅カニ三百六十餘巻ノ存スルヲ所得スルトコロト爲スモ、今已ニ東瀛ニ流入シ、岩崎氏靜嘉堂中ノ物ト爲ス矣。先ニ是レ、阮文達・何元錫ハ各(オノオノ)黄氏ニ就(ヨ)リテ所藏ノ文淵閣殘本ヲ假シテ藏セル諸ノ篋衍(書物を入れた箱)ヲ謄校(写して較べる)ス。嘉慶ノ間、常熟ノ張若雲ハ何氏本ニ據リ、歙ノ鮑崇城ハ阮氏本ニ據リテ次第ニ梓行(出版)ス。張氏ノ刊成ハ未ダ幾(イクバク)モ板ノ燬存スルコトナク、書ノ星鳳(美しいもの)ノ如ク傳フル者ハ稀ニシテ、唯ダ鮑氏刻本ノミ。
歳ハ戊辰、余ハ日本ヘ赴キ書ヲ訪ネ、先(マ)ヅ靜嘉堂文庫ニ至リテ陸氏ヨリ所得セシ本ヲ觀ルニ、其ノ文淵閣印ハ燦然トシテ目ニ溢レ、琳琅(美しい詩文などの例え)ハ架ニ滿ツ。且ツ己ノ國ニ於ヒテ干巻スルガ如ク增得シテ、之ヲ欣羨(歓び)者ト爲シテ置(ヤ)マ不(ズ)。嗣(ツ)ヒデ復タ帝室圖書寮・京都東福寺ニ於ヒテ宋蜀刻本ヲ見ルコトヲ獲ル。各(オノオノ)殘佚有ルト雖モ、然ルニ陸氏ヨリノ所得ト視(クラ)ベ贏(マサ)レリト爲ス。因リテ乞ヒテ假(借)リテ影印ス。主タル者(ハ)慨然允諾、凡(オホヨ)ソ目録十五巻正書九百四十五巻ヲ得ル。又靜嘉堂文庫ニ於ヒテ補巻セシ第四十二至六十一、第一百十七至一百二十五ノ此ノ二十九巻者(ハ)均シク半葉十三行ニシテ蜀刻於(ト)
同ジ。惟(タ)ダ板心ニ刻工ノ姓名無ク、且ツ毎行悉(コトゴト)ク二十二字ニシテ、蜀刻與(ト)之(コ)レ偶(タマタマ)盈縮(伸縮)ノ有ル者(ハ)不同ニシテ、即チ在前ハ之(コレ)建寧刊本カト疑フ。蜀本ノ巻首ニ小引シテ謂フニ、建寧ノ刊スル所ハ舛(マスマ)ス誤ノ甚(ハナハ)ダ多ク、李廷允ハ跋ニ亦タ三萬八千餘字ヲ釐正(改正)スト言フ。今二刻ヲ以テ鮑本與(ト)校スルニ、各(オノオノ)脱誤有リト雖モ、然リテ阮文達ノ序ニ鮑刻ヲ「古書ノ文義ノ深奥ナルコト後世與(ト)ハ、不同ナルコト判然タリ。淺學ノ者ハ見テ誤ト為シ、而シテ之ヲ改メ知ラ不(ザ)ル所ヲ改ムル者(ハ)反(カヘ)ッテ誤ナリ矣。或ヒハ其ノ間、實ニ宋本ノ脱誤有ル者(ハ)但ダ一字ヲモ改動シテ、即チ宋本之眞ノ存スル能(アタ)ハ不(ザ)ラシメ、重ネテ後世於(ニ)見ルコト能(アタ)ハ不(ザ)ラ使(シ)ム」ト明言ス。此ニ據リテ言ヲ爲セバ、是ノ宋本ハ即チ脱誤ノ有ルモ、未ダ嘗(カツ)テ其ノ聲價(価)ヲ損ハズ、且ツ未ダ必ズシモ脱誤ト爲スヲ眞トハセズ也。
今再ビ數例ヲ舉グルヲ請ヒテ、以テ宋刻之今本於(ニ)勝ルヲ證ス。
職官部ノ金紫光禄大夫門、宋刻ノ引ク『干寶晉記』『三國典略』二則ヲ鮑本ハ則チ左傳成上ヲ引キテ曰ク「衞侯使孫良夫來聘且尋盟公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉也其位在三公下卿孫子之於衞也位爲上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也」ノ九十八字ノ下ニ接ゲテ「入落授金紫光禄大夫」云云〈見ヨ巻第二百四十三第五葉〉。前後渺(カスカ)ニ相渉セ不(ズ)シテ張本ト同ジクシ、但ダ注ノ上下ニ脱文有ルヲ疑フ。
兵部機略門ノ引ク『後漢書』第十六則ノ「岑彭將兵三萬餘人」云云トイフ凡ソ一百三十七字〈見ヨ巻第二百八十四第五葉〉ヲ鮑張二本ハ全テ脱ス。
妖異部ノ精門ニ引ク『易』『禮記』『唐書』『管子』『列異傅』又『捜神記』二則ノ適成(ちょうどなる)セル一葉〈見ヨ巻第八百八十六第四葉〉ヲ鮑張二本ハ全テ缺ク。
獸部ノ馬門ニ引ク『周禮』夏官上「馬及行則以任齊其行若有馬訟則聽之禁原蠶者」並ビニ注ニ又引ク『論語』『周書』『韓詩外傳』『尚書大傳』『太公六韜』『禮斗威儀』『春秋考異郵』『春秋説題辭』凡十則及ビ「淮南子曰八九七十二」九字〈見ヨ巻第八百九十三第六葉〉ヲ鮑本ハ全テ脱シ、且ツ『淮南子』ノ三字ヲ易(カ)ヘテ、『家語』張本ト同ジク爲シ、更ニ十餘字少ナシ。
即チ此ノ數事ニ之ヲ觀ルニ彌(イヨイヨ)宋本之信ズ可キヲ覺ユ。
日本ノ文久紀元ハ當(マサ)ニ我國ノ咸豐十一年ニシテ、喜多邨直寛(喜多村直寛)ハ宋寫本ヲ影スルヲ以テ聚珍版ノ印行ヲ用(オコナ)フヲ嘗(ココロミ)ル。其ノ鮑本於(ニ)優(マサ)ル者(ハ)、則チ板心ニ刻工姓名ヲ記ス所、均シク蜀本與(ト)相ヒ合フ。且ツ上文ニ舉グル所ノ四事ハ一ノ脱誤モ無ク、宋刻而シテ外ニ此ノ本ヲ斷推ス。是ニ於テ取リテ、以テ影本二十六巻之闕書ヲ、覆寫ヲ經、又活版ヲ用ヒテ補フ。詞句ノ訛謬ハ自(オノズ)カラ免レ不ル所ナレド、然シテ以テ鮑張二本ヲ校ス。
道部ノ尸解門ニ彼ハ且(マ)タ「太微經曰諸尸解者按四極眞科云一百四十年乃得神中眞官於是始得飛華蓋乘輦龍登太極遊九宮也」四十二字ヲ缺ク〈見ヨ巻第六百六十四第八葉〉。
方術部占星門ノ末節、「元衡亦遷吉甫」ノ下、又「先一年以元衡生月卒元衡後一年以吉甫」ノ十七字ヲ脱ス〈見ヨ巻第七百三十三第四葉〉。
巫門ノ離騒ニ曰ク、「欲從靈氛之吉占兮」ノ節、又注ノ十八字ヲ脱ス〈見ヨ巻第七百三十五第四葉〉。
惟(オモ)フニ祝門ノ『韓詩外傳』ニ曰ク「齊桓公至海丘」ノ節ノ「盍復祝乎」ノ下「封人曰使吾君好學而不惡問賢者在側諫者得入桓公曰善哉祝乎」ナル二十七字、「此言乃夫前二言之上也臣聞」ノ下「子得罪於父母可因姑姊妹而謝也父乃赦之臣得罪於君可因便僻之左右而謝也君乃赦之昔」ナル三十八字〈見ヨ巻第七百三十六第三葉〉、「史記曰楚大發兵如齊」ノ節ノ注ニ有ル二十七字〈見ヨ巻第七百三十六第四葉〉ハ、張本ニ存リテ而シテ鮑本ハ猶ホ脱ス。
疾病部ノ總敍疾病門ニ引ク『禮記』『左傳』『春秋』「穀梁傳」「公羊傳」『國語』『論語』『史記』『漢書』ニ有ル注ノ二十三條ヲ鮑本ハ全テ脱シ、張本ハ僅カニ其ノ二ヲ存ス〈見ヨ巻第七百三十八第一二三葉〉。
是レ則チ此ク建蜀二本ニ逮(オヨ)バ不ルトモ、抑(ソレハソウト)シテ猶ホ吾國ノ時本之上於(ニ)出(イズ)ルモノ也。蜀本ノ原缺セル巻第二十一、第六百五十六至六百六十五、第七百二十四至七百三十八ハ皆全巻、又目録及ビ巻第四、第三十八、第一百一十、第一百三十、第一百四十、第一百六十六、第四百六十四、第五百三、第五百七十一、第六百九十、第七百五十七、第九百五十二ノ凡ソ缺スル二十六葉有半ハ均シク聚珍版ヲ以テ宋刻ヲ補フ。毎行二十二三四字ニシテ聚珍版ノ等シカラ不(ザ)ルハ則チ二十二字ニ整ヘ、故ニ前後葉ノ銜接スル處、偶シテ移易(移し替え)理合スルモノ有リ。
乙亥仲冬海鹽張元濟申明ス。
〈現代語訳〉
太平御覧は宋の一大著作である。それが引く經史圖書は凡(およ)そ一千六百九十種。その中で今に傳わらないものは、十のうち七八にもなる。古籍から収集したとも謂い、また類書を出自としているとも謂う。之を要約すると徴引するところは賅博で、多くの前言往行(前人の言葉と行い)を記録していて洵(まこと)に珍重すべきものとすることが出来る。今行なわれているものに、明代の活字本が有り、錫邑(現・無錫市)刻本が有る。それらの出自となったところの周堂(万暦二年=1574、銅活字印本『太平御覧』)序は謂う。その先祖が曾(かつ)て故(古)本を得、黄正色(1501-1576)の序には則ち、薛登甲が善本を校定した所に據って繕寫して刊刻に付したと謂う。然るに胡應麟(1551-1602)は其の姓名が顚倒していることを代々の「魯魚學者」の病であると譏(そし)るのであろうか。明の文淵閣の書目は、一百三十册の一部と一百册の一部とを存しているが、均しく殘缺である。其の後、蘇(江蘇省の)人である朱文游・周錫瓚・黄丕烈・汪士鐘などの諸家の間を転々とした。最後に湖州の陸心源が僅かに三百六十餘巻となったものを所得することとなったが、今は已に東瀛(日本のこと)に流出して、岩崎氏靜嘉堂の所有となってしまったのである。先にこれは、阮文達・何元錫が各(おのおの)黄氏が所藏している文淵閣殘本を借りて諸の篋衍(書物を入れた箱)を謄校(写して較べる)した。嘉慶年間、常熟の張若雲は何氏本に據って、また歙の鮑崇城は阮氏本に據って順次梓行(出版)した。張氏の刊行した版木は幾らも残っておらず、書が星鳳(美しいもの)のように傳えられているのは稀であって、唯だ鮑氏刻本だけである。
戊辰(1928)の歳、私は日本へ赴いて書を訪ね、先ず靜嘉堂文庫に至って陸氏から得た本を觀ると、其の文淵閣印は燦然としていて目に溢れ、琳琅(美しい詩文などの例え)に滿ちていた。そして自分の国で書物を求めるように益々収得して、これを欣羨(歓び)とせずにはおられなかった。嗣いで復た帝室圖書寮・京都東福寺に於いて宋蜀刻本を見ることができた。各(それぞれ)殘佚が有あるとは雖っても、然し陸氏から得たものと視(くら)べ贏(まさ)っているとする。因ってそれを拝借して影印した。その主なものとして、慨然允諾、凡(およ)そ目録十五巻と正書九百四十五巻を得た。又靜嘉堂文庫に於いて補巻した第四十二から六十一まで、第一百十七から一百二十五までの此の二十九巻は、均しく半葉十三行であって、蜀刻と同じである。惟だ板心に刻工の姓名が無く、且つ毎行悉(ことごと)く二十二字であり、蜀刻とは盈縮(伸縮)が有って同じでないのは、つまりこの出自が建寧刊本ではないかと疑う。蜀本の巻首に小引して謂うには、建寧に刊行したもものは舛(ますま)す誤が甚(はなは)だしく多く、李廷允は跋で亦た三萬八千餘字を釐正(改正)したと言っている。今、この二刻本を鮑本と校勘すると、各(それぞれ)脱誤が有るとは雖っても、然し阮文達は序で鮑刻について「古書の文義が奥深いことは後世とは、同時でないことは判然としている。淺學の者はこれを見て誤と為して之を改め、知らない所を改めるのは反(かえ)って誤となるのである。或いは其の間に、實に宋本に脱誤が有る場合は但だ一字でも改動して、その結果、宋本の眞実を無くしてしまい、重ねて後世にこれを見ることが出来ないようにしてしまった」と明言している。此に據って言うとすれば、是の宋本には即ち脱誤が有っても、未だ嘗(かつ)て其の聲價(価)を損うことなく、且つ未だ必ずしも脱誤と爲すのが眞実であるとはしない。
今再び數例を舉げさせていただき、それによって宋刻が今の本に勝っていることを明らかにする。
職官部の金紫光禄大夫門、宋刻が引く『干寶晉記』『三國典略』の二箇条を鮑本は則ち『左傳成上』を引いて曰うところの「衞侯使孫良夫來聘且尋盟公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉也其位在三公下卿孫子之於衞也位爲上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也」の九十八字の下に接げて「入落授金紫光禄大夫」云云〈見巻第二百四十三第五葉〉とある。前後渺(目→耳:かすか)に相渉しないところは張本と同であり、但だ注の上下に脱文が有るのではと疑う。
兵部機略門の引く『後漢書』第十六箇条の「岑彭將兵三萬餘人」云云という凡そ一百三十七字〈巻第二百八十四第五葉を見よ〉を鮑氏・張氏の二本では全て脱落している。
妖異部の精門に引く『易』『禮記』『唐書』『管子』『列異傅』、また『捜神記』の二箇条の適成(ちょうど)一葉となる部分〈巻第八百八十六第四葉を見よ〉を、鮑氏・張氏の二本は全て缺いている。
獸部の馬門に引く『周禮』夏官上「馬及行則以任齊其行若有馬訟則聽之禁原蠶者」、並びに注に又引く『論語』『周書』『韓詩外傳』『尚書大傳』『太公六韜』『禮斗威儀』『春秋考異郵』『春秋説題辭』の凡そ十箇条、及び「淮南子曰八九七十二」九字〈巻第八百九十三第六葉を見よ〉を鮑氏の本は全て脱落し、且つ「淮南子」という三字を易(か)え、『家語』張本と同じにした上に、更に十餘字少なくなっている。
即ち此の數事でこのことを觀ると彌(いよいよ)宋本は信じられるものだと思う。
日本の文久元年、當(まさ)に我國の咸豐十一年、喜多邨直寛(喜多村直寛)は宋代写本を影印によって聚珍版の印行を用(おこな)った。其れが鮑氏の本より優れているところは、則ち板心に刻工の姓名を記している所が、均しく蜀本と一致する。しかも上文に舉げた四事については一つの脱誤も無く、宋刻の外には此の本を斷推する。是を取って、以て影本二十六巻の闕書を覆寫により、又活版を用いて補う。詞句の訛謬は自(おの)ずから免れない所ではあるが、然しこれを以て鮑氏・張氏の二本を校合する。
道部の尸解門でそれは且(ま)た「太微經曰諸尸解者按四極眞科云一百四十年乃得神中眞官於是始得飛華蓋乘輦龍登太極遊九宮也」の四十二字を缺いている〈巻第六百六十四第八葉を見よ〉。
方術部占星門の末節、「元衡亦遷吉甫」の下では、又「先一年以元衡生月卒元衡後一年以吉甫」の十七字が脱落している〈巻第七百三十三第四葉を見よ〉。
巫門の離騒に曰う、「欲從靈氛之吉占兮」の節では、又注の十八字が脱落している〈巻第七百三十五第四葉を見よ〉。
惟(おも)うに祝門の『韓詩外傳』に曰う、「齊桓公至海丘」の節、「盍復祝乎」の下の「封人曰使吾君好學而不惡問賢者在側諫者得入桓公曰善哉祝乎」という二十七字、「此言乃夫前二言之上也臣聞」の下の「子得罪於父母可因姑姊妹而謝也父乃赦之臣得罪於君可因便僻之左右而謝也君乃赦之昔」という三十八字〈巻第七百三十六第三葉を見よ〉、「史記曰楚大發兵如齊」の節の注に有る二十七字〈巻第七百三十六第四葉を見よ〉は、張氏本には存って、一方鮑氏本では猶お脱落している。
疾病部の總敍疾病門に引く『禮記』『左傳』『春秋』「穀梁傳」「公羊傳」『國語』『論語』『史記』『漢書』に有る注の二十三條を鮑氏本は全て脱落し、張氏本は僅かに其のうち二つを残している〈巻第七百三十八第一二三葉を見よ〉。
是れは則ち此の建本・蜀本の二本には逮(およ)ばないものの、それでも猶お吾が國現今の本の上に出るものである。蜀本が原缺している巻第二十一と、第六百五十六から六百六十五まで、第七百二十四から七百三十八までは皆全巻、又目録及び巻第四、第三十八、第一百一十、第一百三十、第一百四十、第一百六十六、第四百六十四、第五百三、第五百七十一、第六百九十、第七百五十七、第九百五十二の凡そ缺けている二十六葉半については均しく聚珍版を以て宋刻を補ってある。毎行二十二三四字と聚珍版とは等しくないところは則ち二十二字に整え、故に前後葉が銜接(接続)している處で、偶(たまたま)移易(移し替え)して理合(辻褄を合わせる)しているところが有る。