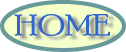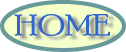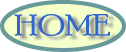�u���i�{�v�Ɓu����{�v
Yahoo!�f����ɂ�����u���i�{�vvs�u����{�v�_��
Yahoo!�f���u�הn�䍑�_�����D���Ȑl�W�܂�I!�v��ŁA��ɌÓc���x����zarakoku���Ƃ̊ԂŌ��킳�ꂽ�u���i�{�v�Ɓu����{�v�Ɋւ���c�_�̂����A���̓��e�����炱�̗������L�[���[�h�Ƃ��Č����������̂̈ꗗ�ł���B�����̑���̓��e��\�����邱�Ƃ��T�������߁A�c�_�̗��ꂪ���ݎ��ɂ������������邩���m��Ȃ����A�E���グ���j�������Ȃǂ�ۑ����Ă��������ł��Ӌ`������̂Ǝv���كT�C�g��1�ł�lj����邱�Ƃɂ����B�i2025/2/5�j
�����i�{
2006/7/18 23:41:00
���b�Z�[�W:#46333
�����X���炵�܂��I
���������A���́u���i�{�v�̖����u�i�E��v�̃P�[�X�ɂ�����܂��ˁB
�����{
���{�ɂ���Ắu����{�v�ƂȂ��Ă���̂�����܂��B�u���v�Ɓu��v�͒ʂ��邱�Ƃ�����܂��̂Ŗ��͂Ȃ��̂ł��傤���A�u�i�E��v�͍l���������܂��ˁB
�w�����x�u�]�[�`�v�̊�t�Ò��ł́u���v�ŕЂÂ��Ă��܂��ˁB
to#46326 by iiiioyajiii
Re: �����i�{
2006/7/19 0:09:00
���b�Z�[�W:#46336
��
����Ȏ��͑�ςł�
�w���{�x�w���i�{�x�w����{�x�w���i�{�x
���`��Ԍ����鎖���������߂��܂�
��
����ȊȒP�Ɍ���Ȃ��ł��������ȁI
��t�Â̒����Љ�Ă����܂��B
�y�����{���i�L�쑾�㎚�Ҍ�犿������{��z(�k�v�~���Ė{�E��v�����S���d���E�m���{��\�j�ɂ��B�k�v�i�S���{�E�S�Ӗ{��\�l�j�ɂ��Ɓu�L�쑾��v���u�L����v�ɍ��)�B
�ߓǂ���A�u���m���{�j���i������j�샋���m�L���n���B���j����{���L��v�ł��傤���B
to#46334 by geaf7019
Re: �����i�{
2006/7/19 0:16:00
���b�Z�[�W:#46337
���m�肦������ł́u�i�E��v�̌������������̂́A���́u���i�{�v�Ɓu�הn�i���v�����Ȃ�ł����
���ƁA���̋^�����w�E����Ă���̂́u������v�u�����i�v�ł��ˁB
����ʂ�����������ł�����܂����A���ꂪ�ő��Ȃ��Ƃł͐����Ȃ������̂��̂ł��邱�Ƃ��\���Ă��܂���
��ʂ́A�u�ނׂȂ邩�ȁv�Ƃ����ꍇ�������͓̂��R�ł����A�u�Ȃ�ł��`�H�v�Ƃ����P�[�X�����܂���܂��B
�u��Òq�ڋ�v�Ɓu��Ð��ڋ�v(���Êt�{)�Ƃ��ł��ˁB
�u�הn�i�v�u�i�o�v�̏ꍇ�́A���̊��ЂƂ̍Z�������Ƃ��ĊԈႢ�Ȃ��ƍl���܂��B
to#46335 by iiiioyajiii
Re: ���i�{
2006/7/21 23:33:00
���b�Z�[�W:#46570
�w�����䗗�x�u����S���\�O�@��������@�{�v�Ɂw�����x�́u���i�{�v������������Ă��܂����̂ł����Ă����܂��B
�w�����x�E�E�E�y�����{���i�L���㎚�Ҍ�犿������{��z(�u���v�͐m���{�A�[�����ǔł́u�쑾�v�ƌ�����)
�w�䗗�x�E�E�E�y�����{���i�L�쑾�i���Ҍ�犿�����i�{�Q�z
��t�Â̒��Ƃ��ċL����Ă��镶�Ȃ̂ł����A�Óc���Ɣ���Y��Y���Ƃ̊ԂŘ_��������܂����B���҂Ƃ��A����̏��{�Ɂu����{�v�Ƃ��邱�Ƃɂ��Ă̂��Ƃ肾�����̂ł����A�w�����䗗�x�Ɉ�����Ă���w�����x���Y�������ׂĂ݂�ƁA��t�Â̒��́u���i�{�v�Ɓu����{�v�ɂ��Ē��L���Ă���̂ł͂Ȃ��A�u���i�{�v�Ɓu���i�{�v�ɂ��Ă̒��ł��������Ƃ�������܂��B�܂�u���������v�Ƃ������Ȃ̂ł��B
�����āA����̏��{���Ɂu����{�v�Ƃ�����̂�����E�E�E�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��悤�ł��B����ł����̕����́u���i�{�v�������킯�ł��B
������ɁA����ɂ��L���ǂ܂�Ă���S�Ӗ{�w�����x(�k�v�E�i�S���{)�ɂ́u����{�v�ƌ����邱�Ƃ���A����͑v��A�����ɓ������ėp����ꂽ�w�����x�e�L�X�g�ɂ����āA�͂��߂āu����{�v�Ƃ����\�L���o���������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B
����͂܂������A�S�Ӗ{�w�O���u�x�Ɂu�הn�㍑�v�Ƃ���A����ɐ旧�����Ɂu�הn�i���v�Ƃ��鎖���W�Ɓg�O����h�ɂ��܂��B
to#46542 by zarakoku
Re: 鰒����鰎u���㊿���Ȃǂ����Ă���H
2006/7/22 0:05:00
���b�Z�[�W:#46574
���@��������A鰒���́A鰎u�����łȂ��㊿���Ȃǂ����p���Ă��܂���
����Ȃ��Ƃ̓U������Ɍ����Ȃ��Ƃ��捏���m�I�������������Ă���̂́A鰒��́w鰎u�x�����ď������Ǝv�����H�Ƃ������Ƃł��B
��鰎u�Ɂu�הn�㚠�v�Ə�����Ă��Ă��A鰒���́A����́u�הn�i���v�̊ԈႢ�ł���ƁA���f����
�Ȃ�Łu�ԈႢ�ł���ƁA���f���v����ł����H�w�㊿���x�̋L����D�悳���悤�Ƃ���Ȃ�A�y���㊿�������הn�i�Җ�z�Ə������͂��ł���H
�U������ɂ��A鰒��́w�㊿���x�����Ă���킯�ł���ˁB�L�q�ΏۂƂȂ鎞��́w�㊿���x�̕����Â����A�ږ�Ă��������ꂽ�̂́g�㊿��h�ł�����ˁB
�ł��킴�킴�y��鰎u�����z�Ɓw鰎u�x�Ɍ��y���Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�`���̓s�u���r�́v�ɂ��Đ�������ɂ́w鰎u�x�̕������������E�E�E�ƍl��������ɑ��Ȃ�܂���B
�u���r�́v�̐����Ƃ��āu�הn�i�v��p�����������̂Ȃ�w�㊿���x���������ł��傤�B�܂��w鰎u�x�������̂Ȃ�u�הn��v�Ə������ł��傤�B�������A�����́y��鰎u�����הn�i�Җ�z�B
�U������́A#46077�ŁA
���w鰎u�x�ɂ́u�הn��v�Ƃ��������ǂ����H�͕s���ł�
�Ə����Ă��܂��B�����܂Ō����Ȃ���A�u�הn�i�v�Ə����Ă��������Ƃ������܂Ŋ�Ȃɋ��ۂ���̂́A�Ȃɂ䂦�Ȃ�ł��傤�H�s�v�c�łȂ�܂���B
���u���i�{�v�̎��ɂ��A����ɂ́A����Ɠ����悤�Ɂu�i�v�́u�i�v�̊ԈႢ�Ƃ�����̂������āA��t�Âɔᔻ���ꂽ�̂ł���
�c�O�Ȃ���A���̂悤�ȗ����͐��藧���Ȃ��悤�ł���B�ڂ����́A#46570�����ǂ݉������B
to#46545 by zarakoku
���u��i�K�c�v
2006/7/22 22:48:00
���b�Z�[�W:#46644
�����������������肪�Ƃ��������܂��B�Óc���́w��i�G�K�c�x�Ə����Ă����܂����̂ŁA����Ō�������Əo�Ă��܂���B�w��i�K�c�x�Ō������܂����Ƃ���A���낢��o�Ă��āA��������ƂɈ𖠎��ɒ��ׂĂ݂܂����B
�w�@���x�u�o�Ўu�v�ɂ́w��i�G�K�c�x�w��i�K�c�x���������܂��̂ŁA�O�҂ł��ԈႢ�ł͂Ȃ��̂ł��傤���E�E�E�B
���āA���́w冎u�x�Ɍ�����A
�y�b���V����i�K���̔V�`���������H���V��t������̎��猾�������\������z
�́A�����L�����w�j�L�x�u���z�`�v�ɂ������܂��B
�y���B�H�Ďߖ��]���ȗ������ו��̏A���̖疔��i�K�c���������H���V��t������̎��猾�������\�����Җ�z
�����ł́w冎u�x�Ƃ͈���āw��i�K�c�x�Ə�����������Ă��܂��B
�܂����Љ���������w�ʓT�x�̋L���́y�������K�]�E�E�E�z�Ǝn�܂�܂����A���́u�����v���u�i�v�̂��Ƃł��傤�ˁB
�܂��A�S�Ӗ{�w�j�L�x�̂��̉ӏ������Ă��ċ������̂ł����A�Ȃ�Ɓu��i�K�c�v���u鰚�K�c�v�ƂȂ��Ă��܂��I
�w��i�K�c�x�́w�k������x��w�|�����ځx�ɂ�������A�w�@���x�u�o�Ўu�v�ɂ��ڂ�قǓ���ł͖��̒ʂ��������̂悤�ł�����A��������炩�̗��R�ł킴�킴�u鰚�K�c�v�Ɓg�̈ӂɁh���������邱�Ƃ͍l�����܂���B
����͊ԈႢ�Ȃ��u�i�v���u��v�ƌ�ʂ������炩�ȗ�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
��́u���i�{�v�̌��Ƃ��킹�āA�ǂ����v�㊧���̃e�L�X�g�ƂȂ������̂̒��ɁA�u�i�v���u��v�ƌ�ʂ������̂��܂܂�Ă������Ƃ�����̌��Ŗ��炩�ɂȂ����ƍl���܂��B
�܂��A�u�i�͓V�q��l���w������A�הn�i�Ȃ�\�L�͐�ɂ��蓾�Ȃ��v�Ƃ����Óc���̎咣���A�����̂Ȃ����Ƃ������ɂȂ����Ǝv���܂��B
to#46592 by tenchuukun
Re: ������M�p���Ă��Ȃ��H
2006/7/24 22:52:00
���b�Z�[�W:#46796
�����炩�̎v�z�I�ȗv���̂��߂��H�A�j���̑I����_���Ɂu���Ӑ��v�������鎞��
�����A�Óc���̂��Ƃł���B�u���i�{�v�w��i�K�c�x�w�e�֑��M�x�̎g�����Ȃ�āA�u���Ӑ��v���̂��̂ł���B
��hyena no papa����{���̂悤�ɁA�u��ȌÓc�U���v�����̂��݂�ƁA�����琳�m�Ș_����W�J����Ă�
�u���m�Ș_����W�J�v���Ă���̂Ɂu��ȌÓc�U���v���Ă͕̂s�v�c�Ȑ\���l�ł��ˁ`�B��Ȃ̂́A�u���m�Ș_���v���u��v�Ɗ�����A�U������̊��o�̕��Ȃ�ł����E�E�E�B
to#46654 by zarakoku
Re: ���v���o�����I
2006/8/6 22:37:00
���b�Z�[�W:#48335
��������Y��Y�ł���
��+���A��u�ŏo�T���o���܂�����
���s��w���{���w�l���x��\�Z�W�u�הn�i���ɂ��āv�ł��ˁB
���̔���_���ɂ��ẮA�Óc�����w�הn�㍑�̘_���x�ɂ����āA�P�Q�T�ł���P�W�W�ł܂ʼn��X�Ɣ��_�������Ă��܂��B��́u���i�{�v�̘b�́A���̒��ŏo�Ă��܂��B
���ɂ����������������m��܂��A���̕��̎Q�l�ɂ��Ȃ낤���Ɗ����Ă��Љ�����܂����B
to#48267 by tenchuukun
Re: ���������A�����炱���B
2006/8/10 23:15:00
���b�Z�[�W:#48804
�������悩�����B�p�p����ɂ͊��ł����������Ȃ����Ǝv������ł���
���S�����A�ɂ݂���܂�m(_ _)m
���l���u���`�v�Ƃ�������u�`�l���v�Ƃ����v���Ă��Ȃ������̂ŁA����͋M�d�ȕ��������Ă��炢�܂���
���́u���v���ł���A�u��卑�����v�ɓ��Ă͂߂���ǂ��Ȃ�ł��傤�H���Ȃ�g�����h�L���悤�ȋC�����܂����E�E�E�B�܁A����͎G�k�Ƃ��Ă��������������B
�����������N�t�������Ă��A���Ђ��ă��c�́A�m��Ȃ����Ƃ��o�Ă��܂��ˁB������ꂪ���͂Ȃ�ł���
�k�V����Ǝ��Ƃł́A��b�w�͂��i�Ⴂ(�֑��Ȃ���A�k��hy)���Ə��m���Ă���܂����A�a�̂悤�ɃR�c�R�c�ƕ����Ă䂭�ƁA���\�ȏE�����̂����邱�Ƃ������ł���ˁB
�u���i�Ə���v�u��i�K�c��鰚�K�c�v�u���i�{�Ƒ���{�v�Ƃ��E�E�E�B
�����Ƃ��Z�����ł��傤���A���肷���̐܂�͂��������̂قǂ�낵���I
to#48702 by tantian
Re: �㊿���̍ŌÂ̊��{���P�Q���I�H
2006/9/19 23:24:00
���b�Z�[�W:#53100
�����R�͊ȒP�ł�
����A�~�����ق��������ł���I
��䗞@�́A�`�z�����`�����������ږ�Ă��A�F�A�����ꏊ�̓������ŁA�u����`�����הn�i���H�v���ƍl�����̂ł���
����Ȃ��Ƃ��w�㊿���x�̂ǂ�����M�����ł��傤���H�u�`�z���v�ɂ��Ắy�`���V�ɓ�E�z�Ə����Ă���܂����A�����́u�`���v��A��`���́u�הn�i���v�ɂ��Ă̈ʒu�̋L�q�͂���܂���B�ǂ�����u�F�A�����ꏊ�̓������v�Ȃ�ė������o�Ă����ł��傤�H
�������āA�u���i�{�Ƒ���{�v�̏ꍇ�̂悤�ɓ���ɂ͊��Ɂu����i�̊ԈႢ�_�v�N���Ă����̂ł�����A�ʖ{�̏��������̉\�����ے�o���Ȃ��Ȃ����̂ł�
����A�ȑO�ɂ����������܂��������X�����������悤�ł��ˁB�Óc�������́u���i�{�Ƒ���{�v���u���������v�Ő������悤�Ƃ��Ă��܂����A�Ȃ�Łu���i�{�v���u����{�v�ɏ��������ɂ�Ȃ��̂ł����H
�w�הn�㍑�̘_���x�P�V�R�ňȍ~������x�A���ǂ݉������B�Óc���́A
�|�|�|�|�|
�u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ�
�|�|�|�|�|
�Ə����Ă��܂����A�Óc�����g�������P�V�R�łŁu��t�Ò��v�������āu�O�L����ϖ�v�Ə����Ă���悤�ɁA����͌��Ɉ��ދ{�a�̘b�Ȃ̂ł�(�u��v�͌�)�B�Ȃ�œ���̐l���A���Ƃ͊W�Ȃ��u�V�_���J��{�a�v�̈Ӗ��ɏ��������˂Ȃ�Ȃ��̂ł��H�������ʂ�܂��E�E�E�B
�������āA���̍ŌÂ̊��{���ǂ�����P�Q���I�Ȃ̂ł���B�ǂ�����A�ʖ{�������p���ł������̂��A�Ƃ��āA�����悤�ɂقڐM�����邵���Ȃ��̂ł͂���܂��H
�������B����Ȃ��Ɖ]������A�ʖ{�͋L���������p���ł�������A���̕��ʂ͐M�p�ł���E�E�E�Ƃ������_�ɂȂ�A�삵����ʂ̑��݂Ƃ��������ɔ����܂��B
�w�O���u�x�́g���{�ԁh�̌�ʂ͖�l�烖���ł���I��ʂɊ��s����A���ꂪ�܂���������Ă����R�s�[�Q�ł���͂��́g���{�ԁh�ł����A���ꂾ���̌�ʂ������Ă���̂ł��B���̎�������ڂ�w���Ȃ��ł��������B
�����u����v�̍������ĉ��ł����H��
���`�̓s�̍����́A�ȑO��isaq force�������ꂽ�悤�ɁA����̋L�ڂ��o�����Ă��܂����ˁB�m���u���}�C�v������܂�����
���́uisaq force�������ꂽ�v���̂��āA�����Љ�����̂ł����E�E�E�B
�S����ʂł��B�G�̌�ʂȂ�āA���낼�날��܂��B
���`�l�`�ƌ㊿���ȍ~�́A�u�`�̓s�̍����v�̋L�ڂ́A����ȍ~�����Ȃ��̂ł���
�Ӗ����悭������܂���ˁB�w�@���x�ɂ��Ɓw鰎u�x�ɂ́u�הn�i�v�Ƃ���E�E�E�Ə����Ă���܂��B���x���J��Ԃ��܂��B����́A�������z���Ă����w鰎u�x�Ɂu�הn�i�v�Ƃ���������ɑ��Ȃ�܂���B
�����́w鰎u�x�Ɂu�הn��v�Ƃ����āA�����鰒����u�הn�i�v�Ə������߂��Ƃ����̂Ȃ�A���̍����I�Ȑ��������肢���܂��B
to#52991 by zarakoku
Re: �㊿��́u����`�����הn�i���v
2006/9/22 23:10:00
���b�Z�[�W:#53399
���㊿���̘`�`�̏��߂ő������āu����`�����הn�i���v�Ə������A�ƌ������́A�㊿��́u����`�����הn�i���v�ł���A�ƌ������ł���
����Ȃ�A�㊿��́u�הn�i���v�ł���ˁH�ȑO�A�U������͌㊿����u�הn�㍑�v���ĉ]���܂���ł��������H
���`�z�����`�����������ږ�Ă��F�u����`�����הn�i���v�ł���A�Ɖ����邵������܂���
�Ȃ�Łu�����邵������܂���v�Ȃ�ł����H���������u�`�z�����v�A�����́u�`(�ʓy)�����v�A�הn�i���ɋ�����u��`���v�A�F���O���Ⴄ�ł���H�Ȃ�ł������傭����ɂ����ł����H
������Ɂu�i�v���u��v�̊ԈႢ���A�Ƃ��ď����������l�������āA���ꂪ��t�Âɂ���ĂƂ��߂�ꂽ�̂ł���H
�������A�u���i�{�v�Ɓu���i�{�v�̌�̘b�ł��B
������ɂ��u�i�v�Ɓu��v�̌�T��������l�����݂����̂ł���
�u���v�Ɓu���v��
����T��������l�����݂����̂ł���
���Óc����́A�O���u�̒��̂P�O�O�ʂ́u����i�v���قڑS�����ׂ��āA�u����i�v�̎ʂ��ԈႢ�A�ƍl�����鏊���قڂȂ��A�����m�F���ꂽ�̂ł���
����ˁA�Óc�������x���咣����Ă��܂����A��ςȊԈႢ�Ȃ�ł���B�Ȃ�ł��H
�Óc���́w�O���u�x���́u�i�ƚ�v�̌�ʂ̃P�[�X�ׂ��킯�ł���ˁH
�Ȃ�Łw�O���u�x���Ȃ�ł����H�w�O���u�x��������ʂ�������l�Ƃ��ƌn�Ƃ�����������킯���Ⴀ��܂����B
��`���l���Ă݂ĉ������B
���ʖ{���o������ɂ́A���̒��Ɂu����i�v���ԈႤ�l�����������m��Ȃ��ƍl���āA���̏ꍇ�ɂ́u����i�v���ԈႦ���Ƃ��낪����͂����A�Ƃ��āA�u����i�v�ׂ��A���̌��ʁA�ԈႤ�l�͂��Ȃ�����
���ۂ͂�����ł��B��
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/tai_ga_tadashii.html
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/giichihougi.html
���Ɂu鰚�K�c�v���ĂȂƎv���܂��H����u��i�K�c�v�ɑ��Ȃ�܂����ˁH������u���������v�Ő��������ł��傤���H
�u���������v���Ɖ��߂���Ƃ����̂Ȃ�A���́u���������v���l�́A�Ȃɂ䂦�u�i�v���u��v�Ə����������̂��Ǝv���܂����H
to#53370 by zarakoku
Re: �㊿��́u����`�����הn�i���v
2006/9/22 23:10:00
���b�Z�[�W:#53399
���㊿���̘`�`�̏��߂ő������āu����`�����הn�i���v�Ə������A�ƌ������́A�㊿��́u����`�����הn�i���v�ł���A�ƌ������ł���
����Ȃ�A�㊿��́u�הn�i���v�ł���ˁH�ȑO�A�U������͌㊿����u�הn�㍑�v���ĉ]���܂���ł��������H
���`�z�����`�����������ږ�Ă��F�u����`�����הn�i���v�ł���A�Ɖ����邵������܂���
�Ȃ�Łu�����邵������܂���v�Ȃ�ł����H���������u�`�z�����v�A�����́u�`(�ʓy)�����v�A�הn�i���ɋ�����u��`���v�A�F���O���Ⴄ�ł���H�Ȃ�ł������傭����ɂ����ł����H
������Ɂu�i�v���u��v�̊ԈႢ���A�Ƃ��ď����������l�������āA���ꂪ��t�Âɂ���ĂƂ��߂�ꂽ�̂ł���H
�������A�u���i�{�v�Ɓu���i�{�v�̌�̘b�ł��B
������ɂ��u�i�v�Ɓu��v�̌�T��������l�����݂����̂ł���
�u���v�Ɓu���v��
����T��������l�����݂����̂ł���
���Óc����́A�O���u�̒��̂P�O�O�ʂ́u����i�v���قڑS�����ׂ��āA�u����i�v�̎ʂ��ԈႢ�A�ƍl�����鏊���قڂȂ��A�����m�F���ꂽ�̂ł���
����ˁA�Óc�������x���咣����Ă��܂����A��ςȊԈႢ�Ȃ�ł���B�Ȃ�ł��H
�Óc���́w�O���u�x���́u�i�ƚ�v�̌�ʂ̃P�[�X�ׂ��킯�ł���ˁH
�Ȃ�Łw�O���u�x���Ȃ�ł����H�w�O���u�x��������ʂ�������l�Ƃ��ƌn�Ƃ�����������킯���Ⴀ��܂����B
��`���l���Ă݂ĉ������B
���ʖ{���o������ɂ́A���̒��Ɂu����i�v���ԈႤ�l�����������m��Ȃ��ƍl���āA���̏ꍇ�ɂ́u����i�v���ԈႦ���Ƃ��낪����͂����A�Ƃ��āA�u����i�v�ׂ��A���̌��ʁA�ԈႤ�l�͂��Ȃ�����
���ۂ͂�����ł��B��
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/tai_ga_tadashii.html
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/giichihougi.html
���Ɂu鰚�K�c�v���ĂȂƎv���܂��H����u��i�K�c�v�ɑ��Ȃ�܂����ˁH������u���������v�Ő��������ł��傤���H
�u���������v���Ɖ��߂���Ƃ����̂Ȃ�A���́u���������v���l�́A�Ȃɂ䂦�u�i�v���u��v�Ə����������̂��Ǝv���܂����H
to#53370 by zarakoku
Re: �㊿��́u����`�����הn�i���v
2006/9/28 21:59:00
���b�Z�[�W:#54182
���T���I��䗞@���A���̂悤�ɔF�����Ă��������Ă���
�����Ԃ́A䗞@�́u�הn�i���v���㊿��ɑ��݂����悤�ɔF�����L�ڂ��Ă���ǂ�
�܂��u�F���v�ł����H����͂������\�ł��B�U������̉]���u�F���v�́w�㊿���x�ɂ́A���������Ă���E�E�E�Ƃ����ȏ�̈Ӗ��͂Ȃ��̂ł�����A����Ȃ��ƌJ��Ԃ���Ă��O�ւ͐i�݂܂���B
�������`�z�����`�����������ږ�Ă��F�u����`�����הn�i���v�ł���A�Ɖ����邵������܂���
�����Ȃ�Łu�����邵������܂���v�Ȃ�ł����H���������u�`�z�����v�A�����́u�`(�ʓy)�����v�A�הn�i���ɋ�����u��`���v�A�F���O���Ⴄ�ł���H�Ȃ�ł������傭����ɂ����ł����H
��䗞@���A�u�������傭����v�Ɂu����`�����הn�i���v�Ə���������ł�
�`�z�����Ă̂́A�u�`���V�ɓ�E��v�ł���B�܂�`���̈ꕔ�B�`���̈ꕔ�ł���`�z���̉����A�Ȃ�Łu��`���v�Ȃ�ł����H
�������ł����H�@�Óc����́A�u���i�{�v������́u���������{�v�Ɂu����{�v�Ə����������Ă���������t�Â��Ƃ��߂��A�ƌ����悤�ɏ����Ă��܂���
����͌Óc�����Ԉ���Ă���̂ł��B#53100�ł����q�˂��܂������A���̓_�ɂ��Ă̔��_�͂Ȃ������悤�ł��ˁB���Ɉ��ދ{�a�̖��O���A�Ȃ�Łu�V�_���J��{�a�v�̈Ӗ��ɏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H
���������E�E�E�Ƌ�̂Ȃ�A���̍����I�Ȑ��������肢���܂��B
�������Ɂu鰚�K�c�v���ĂȂƎv���܂��H����u��i�K�c�v�ɑ��Ȃ�܂����ˁH������u���������v�Ő��������ł��傤���H�u���������v���Ɖ��߂���Ƃ����̂Ȃ�A���́u���������v���l�́A�Ȃɂ䂦�u�i�v���u��v�Ə����������̂��Ǝv���܂����H
���܂�hyena no papa����̂��Љ�̃T�C�g�������Ē����܂������A�O���u�ɂ͖��W�Șb�ł���B����ł̓_���ł���H
�������Ȃ̂́A�O���u�̎ʖ{�������p���ꂽ�ԂɁA�u����i�v���ԈႦ��ʖ{�҂������Ƃ�����A���݂̒ʍs�{�O���u�́u����i�v�Ɏʂ��Ԉ�����ꏊ������͂����A�ƌ����̂ŁA���ׂ����Ȃ������A�ƌ����b�ł�
��������A�����瑼�̕����ł̊ԈႢ��H���������Ă��A�O���u�ɂ͊W�͂���܂����
���܂��Ă�A����ɂ́A�u���i�{�v�Ɓu���i�{�v�̘b�̂悤�ɁA�u����i�v���Ӑ}�I�ɊԈႢ���Ɣ��f����l�������ʂł�����A�ʂ̕����ŊԈႦ�Ă��鎖�͗L�蓾�܂����A����ƁA�O���u�ŊԈႤ���ǂ����́A�W������܂����
���̌��ɂ��ẮA#53399�ŏ����܂����̂ʼn��߂ă��X�������邩�Ǝv���܂����A�Ȃ��w�O���u�x�Ɍ��肷��̂��H�悭�l���Ă݂ĉ������B
���̕��������ʂ���Ƃ��ɔ��������ʂ��A�w�O���u�x�ł͔������Ȃ��I�Ƃ����g���R�h�͉��ł����H
�Óc���́g�_���h�Ƃ��̕s�v�c�ȕ������悭����Ă��܂��B
���Ⴆ�A�Î��L�Ƒ勾�ňႢ����������
�����H�U������́A���Ď����g�Ⴆ�b�h�������o������A�t���܂���ł�����ˁH�ł�����A�ɗ̓U������ɂ́g�Ⴆ�b�h�����Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂����B�U�����g�Ⴆ�b�h���t����Ƌ�̂Ȃ�A���ꂩ��ǂ�ǂ�o���܂��B
�����{���I������Ă���͂���
�����l���w�Î��L�x�w�勾�x�w���{���I�x�����ʂ�����A�����������悤�Ɍ�ʂ���\���͂���܂��B
�܂��ʂ̐l�����̎O�������ʂ�����A�ʂ̕����𑵂��Č�ʂ���\���͂���܂��B
�����Ȏ���́A�����Ȑl���w�Î��L�x�����ʂ���ꍇ�A���ł����ʂ��w�Î��L�x��ł͑����Ă��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃ��l�����܂����H
to#53875 by zarakoku
Re: �㊿��́u����`�����הn�i���v
2006/10/3 22:25:00
���b�Z�[�W:#55079
�������́A��{�I�ɂ́A���̎��_�Œ��҂ɂƂ��Ĕ����������L�^�咣���悤�Ƃ�����̂��A�ƌ������ł���B���̎��𗝉����Ă���O�i�ނ̂ł�
�ւ��H����Łu�O�i�v���ʂ��A�u�^���V�q�R�v���吨����Ƃ��H
���������A䗞@�́u����`�����הn�i���v�Ǝv���Ă���̂ł�
�����A�㊿��́u�הn�i���������v�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ�����ł��B���x�����q�˂��Ă���̂ł����A䗞@�w�㊿���x�Ɂu�הn�i���v�ƌ�����̂́A�`�̌܉��̎���̓`�������f���ꂽ�Ƃ��l���Ȃ̂ł���ˁH
����Ȃ�A�w�v���x�ɂ���炵���\���������Ă�����ׂ����ƍl���܂����E�E�E�B�w�v���x�̂ǂ����Ɂu��`���v�Ȃ�ď����Ă���܂����˂��H
��������͌Óc�����Ԉ���Ă���̂ł��B#53100�ł����q�˂��܂������A���̓_�ɂ��Ă̔��_�͂Ȃ������悤�ł��ˁB���Ɉ��ދ{�a�̖��O���A�Ȃ�Łu�V�_���J��{�a�v�̈Ӗ��ɏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H�@���������E�E�E�Ƌ�̂Ȃ�A���̍����I�Ȑ��������肢���܂��B
�������ł����H�@�Óc����̗����́Atenchuukun����������ł������悤�ł�����
����H�u�V�n�N��搶�v���u���i�{�v�ɂ��ČÓc���Ɠ�������������Ă����ł����H�����Y��Ă��܂����̂ł����˂��H�L���ō\���܂���̂ŁA�u�V�n�N��搶�v���ǂ̂悤�ɌÓc���Ɠ����l�����q�ׂ�ꂽ�̂��A�����Ă��������܂��H
�������́A�u�הn�㍑�̘_���v�̂P�V�R�ł����Ē���������̂ł�
����Ȃ��͓̂ǂ�ł̎���ł��B����܂ł������Ă����ł���H�Ȃɂ䂦�V�_���J��{�a�̖��O�ɏ����������̂��H���āE�E�E�B�����V�̘b�������ł���H
�������̌��ɂ��ẮA#53399�ŏ����܂����̂ʼn��߂ă��X�������邩�Ǝv���܂����A�Ȃ��w�O���u�x�Ɍ��肷��̂��H�悭�l���Ă݂ĉ������B���̕��������ʂ���Ƃ��ɔ��������ʂ��A�w�O���u�x�ł͔������Ȃ��I�Ƃ����g���R�h�͉��ł����H�Óc���́g�_���h�Ƃ��̕s�v�c�ȕ������悭����Ă��܂��B
���n�������b�ł��B�Óc����łȂ��Ă��A�u���ׂĂ̕����ɂ͊ԈႢ���Ȃ��v�Ȃǂƌ��������́A���R�L�蓾�܂����
�ŁA���{�w�O���u�x�ɂ́u�ԈႢ���Ȃ��v���ĉ]���B���ꂱ���A
���n�������b�ł�
��������A�����̎O���u�̎ʖ{��ō��������p���ꂽ�l�����̒��ɁA�u��v�Ɓu�i�v��ԈႦ��l�͂قڂ��Ȃ��A�ƌ�����̂ł�
�O�ɂ������܂������A�܂������܂��B�w�O���u�x�����ʂ���Ƃ��ɂ͊ԈႦ�Ȃ��E�E�E�Ƃ����̂͂Ȃɂ䂦�ł����H
���������l���w�Î��L�x�w�勾�x�w���{���I�x�����ʂ�����A�����������悤�Ɍ�ʂ���\���͂���܂��B�܂��ʂ̐l�����̎O�������ʂ�����A�ʂ̕����𑵂��Č�ʂ���\���͂���܂��B�����Ȏ���́A�����Ȑl���w�Î��L�x�����ʂ���ꍇ�A���ł����ʂ��w�Î��L�x��ł͑����Ă��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃ��l�����܂����H
��hyena no papa����ʂ�����̂́Azarakoku����ʂ���͂��Ȃ̂ł����H
�U������A���̕�����ǂ��Ă��܂���I����x�A�ǂݒ����Ă��������B���������ʂ��A�U�����������E�E�E�Ȃ�ĉ]���Ă��܂����B�悭�ǂ�ł��������B
to#54713 by zarakoku
Re: ���@�ƙl�߁H
2007/1/8 1:30:00
���b�Z�[�W:#65746
��䗞@�́A鰎u�́u�����̂����̂��הn�㍑���v�ǂ����ɍS��炸�A�T���I�̂܂ł̏��𑍍����āA�u����`�����הn�i���v�ƔF�����L�ڂ����̂ł���
�u�T���I�̂܂ł̏��v���u�הn�i���v�Ȃ�A�R���I���u�הn�i���v�ł��傤�ɁE�E�E�B�g���{�����h�Ƃ���l���ɕ߂��Ȃ���E�E�E�B
���u��v�Ɓu�i�v�̊ԈႢ�_�̗��s�ɂ��
����Ȃ��̂���܂����B�u���i�{�v�̘b�ł����H
���u�הn�i�v��I���������̂���������
�g�����h���Ȃɂ��A�u�הn��v�Ȃ�Ă̂��P���������Ȃ�Ă���܂�����́A�v��܂łɂ́E�E�E�B
���ʂɁA���@�Ȃǂł͂Ȃ��A�j���̒��Ҏ��g�̍l���ɂ��I���ɉ߂��܂���
�g�I���h�ɂ́g���@�h����������Ȃ���ł����H����Ƃ��A�T�C�R���U���āu�����o������g�i�h�ɂ��悤�v�Ȃ�ď������E�E�E�킯����܂����˂��B�g���@�h������������g�I���h������ł���ˁB
�����̋L�ڂ����O���u�����ނ����ł������A�Ɗm�肵�Ă���̂Ȃ�
���̋L�ڂ����O���u��������������ł����H���������Ƃ���܂��E�E�E�B
���Q��ނ̊��{�ŋL�ڂ̈Ⴂ������A�Е����Ԉ���Ă��邩�H�������Ԉ���Ă��邩�H�ł��傤
������O�c�̃N���b�J�[�B
���������A�������ԈႢ���A�Ƃ��āA�������悤�ƈӐ}����l�ɂ́A���̂��ꂪ�ԈႢ�ł���̂��H�A�ǂ����Ăǂ̂悤�ɂ��ĊԈႢ�����������̂��H�A�ԈႢ�łȂ��\����S���ے�o����̂��H�Ȃǂ��A���m�ɂ��Ē����K�v������܂���
���ɖ��m�ɘ_�����Ă��܂��B�Óc���̍l���P����l�X���B���������Ȃ������̘b�ł��B
�������ł��ˁB�Óc��������R�������K��������悤�ł��B�܂��A�Óc����́A�u�ԈႢ�Ɛ���v����镶���ł������A�Ǝv���܂�
����A�����Љ�Ă��������B
to#65585 by zarakoku
Re: ����́u��v�Ɓu�i�v�̊ԈႢ�_�̗��s
2007/1/13 0:42:00
���b�Z�[�W:#66640
�����u�T���I�̂܂ł̏��v���u�הn�i���v�Ȃ�A�R���I���u�הn�i���v�ł��傤�ɁE�E�E�B�g���{�����h�Ƃ���l���ɕ߂��Ȃ���E�E�E
���u�T���I�̂܂ł̏��𑍍����āv�ƌ����������ł�����A�R���I���u�הn�i���v�ł��������H�͔���܂���
�w�㊿���x�`�`�̖`���Ɍ�����u�v�u�y�Q�S�v�u�S�؍��v�͉����I�̌ď̂ł����H�T���I�ł����H�w�㊿���x������A�㊿��܂ł̎��������Ă�����ĂȂ����߂��Ȃ��̂ł����H
�܂��A�T���I�͘`�̌܉��̎���ł����A���̎��_�Łw鰎u�x�̍��ɂ͂����炳��Ă��Ȃ������u�הn�i���v�Ƃ������̂������ɒm��ꂽ�Ƃ��鍪���͂Ȃ�ł����H
�������u��v�Ɓu�i�v�̊ԈႢ�_�̗��s�ɂ��
��������Ȃ��̂���܂����B�u���i�{�v�̘b�ł����H
�������ł��B����ɁA�u��v�Ɓu�i�v�̊ԈႢ�b���g���Ă���l������A�����m�F�ł����̂ł�
�m�F�Ȃ�Ă���Ă��܂����B���̘b�͂��܂����B�����V�̂��錢�i�{���Ȃɂ䂦�u��(��)��{�v�Ə������߂��˂Ȃ�Ȃ��̂ł��H�Óc�����w�הn�㍑�̘_���x�P�V�U�łʼn]���Ă���u����{���V�_���J��{�a�v�ƁA�h�b�O���[�X�Ƃǂ�Ȋ֘A������̂ł��傤�H
�Óc���̉��߂ɖ����������ɁA�����Љ���w�����䗗�x�́q�u���i�{�v����E�w�����䗗�x�u�������v�r�̗Ⴉ�猩�Ă��A�i�ƚ�̍����������`�v���ɂ����Ĕ��������ƌ�������A���Ɋ����Ă��܂��B
�h�b�O���[�X�ƓV�_���J��{�a�͊W����܂���B
��
�������A�u�ہv��u�ҁv�́A�u�i�v���́u��v�ɔ������߂��̂ł͂���܂��H�@
�@������A�u���}�C�v�ƌ��������̌ď̂́A�u�הn��v���痈�����̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��l�����A�������݂����u�ז��́v�Ƃ����������Ƃ̐�����}�邽�߂ɁA���낢��ȕ������I�ꂽ�\���͂���܂��H
��
���́u�ہv��u�ҁv���o�Ă���V�[�����v���o���Ă��������B�F�u�הn�i���v�̒��Ƃ��Č�������̂ł��B�u�הn�㍑�v�̒��Ƃ��ďo�Ă�����̂͂���܂���B���́u�ہv��u�ҁv�ɗނ����ʂ́A�����ς́w�O���u�Z���L�x�̒��ɂ������܂��B�ߑ压����K�v�͂Ȃ��ł��傤�B
���݂ɂ����̕\�L�̌�����j���ɂ��ẮA���̂g�o�̂ǂ����ɏ����Ă���A�ɍ삳������܈��p���Ă��܂�����A�U������������ɂȂ�����������ł��傤�B�F�A�u�הn�i���v�Ɍ����钍�Ȃ̂ł��B
�������������A�������ԈႢ���A�Ƃ��āA�������悤�ƈӐ}����l�ɂ́A���̂��ꂪ�ԈႢ�ł���̂��H�A�ǂ����Ăǂ̂悤�ɂ��ĊԈႢ�����������̂��H�A�ԈႢ�łȂ��\����S���ے�o����̂��H�Ȃǂ��A���m�ɂ��Ē����K�v������܂���
�������ɖ��m�ɘ_�����Ă��܂�
�����m�ɘ_����ꂽ�L��������܂���B�T����ł�����
�U�����u���m�Ș_�v���u�T�v�Ƃ������鎖���o���Ȃ������ł��B
���́u�i�v�Ɓu��v�̌�ʘ_�́A�X�S�N�ȒP�Șb�Ȃ̂ł��B�u�הn�㍑�v�Ȃ�\�L���A�v��܂őS�������Ȃ����ŁA�قƂ�ǁu����i�̌�v�Ƃ����Z���͐������܂��B
�}�������E�������[�̃z�N���ł���B
to#66272 by zarakoku
Re: ����́u��v�Ɓu�i�v�̊ԈႢ�_�̗��s
2007/1/18 22:58:00
���b�Z�[�W:#67357
���@�u�Óc���̉��߂ɖ���������v�Ƃ����̂́A�����ł����H
�ǂ�łȂ���ł����H
���m�F�Ȃ�Ă���Ă��܂����B���̘b�͂��܂����B�����V�̂��錢�i�{���Ȃɂ䂦�u��(��)��{�v�Ə������߂��˂Ȃ�Ȃ��̂ł��H�Óc�����w�הn�㍑�̘_���x�P�V�U�łʼn]���Ă���u����{���V�_���J��{�a�v�ƁA�h�b�O���[�X�Ƃǂ�Ȋ֘A������̂ł��傤�H�@�Óc���̉��߂ɖ����������ɁA�����Љ���w�����䗗�x�́q�u���i�{�v����E�w�����䗗�x�u�������v�r�̗Ⴉ�猩�Ă��A�i�ƚ�̍����������`�v���ɂ����Ĕ��������ƌ�������A���Ɋ����Ă��܂��B�h�b�O���[�X�ƓV�_���J��{�a�͊W����܂���
�Ə����܂����ł���H�V�_���J��{�a�ƃh�b�O���[�X�ƂȂ�̊W�������ł����H
���u�i�v���A���́u�C�v�ƌ��������́u�ہv��u�ҁv�̕����Ɍ�ʂ����̂ł����H
����Ȃ��Ǝ��͌����Ă��܂��E�E�E�B�u�i�v���u�ہv��u�ҁv�̕����Ɍ�ʂ����Ȃ�Č��������Ƃ͈�x������܂���B�U������̊��Ⴂ�ł��傤�B
�����́A�����ς́A�u��v���Z�����Ă��Ȃ��̂ł����H
�Ȃ�ׂ��Ίw�K���Ă����̂��`�B�����ς͊��{���u(�ꕔ�W���{)�����Z�����Ă��Ȃ��̂ł��B���{�Ɍ����Ȃ��u�i�v�ɂ��Č��y����͂��A����܂���B
�����j���́A�L�ړ����̓ǎ҂ɔ���Ղ��\����I�����Ă��邾���ł�����A����܂ł́u�Z���v�̑Ώۂɂ��Ȃ�Ȃ������̂ł���H
��x���I������Ȃ������u�הn��v���ĉ��Ȃ̂ł����H
to#67191 by zarakoku
Re: �u���j�����r��`�v��ᔻ
2007/2/12 22:46:00
���b�Z�[�W:#68835
�����u�i�v�̔��������u�㊿���v���Ȃ�Ă����̂��g�j�����ԁh�ł���Ƃ������������̂���������
���u�הn�i���v�̌ď̂́A�㊿�������߂Ăł���H
�u�i�̔������v�̘b�ł���B�j���Ƃ��Ă̏��o�͊m���Ɂw�㊿���x�ł��B�u���������㊿���v���Ȃ�Ă̂��I�J�V�C�ƌ����Ă��ł��B�����Ŋ��ɂR���I�́w鰎u�x�ɂ́u�הn��Ƃ������v�ƌ��O�ɑO�Ă���킯�ł�����ˁB
���������Ɓw鰎u�x�������Ă�����̂܂Łw�㊿���x�̗����ɏ]�����Ƃ��邱�Ƃ���������
���ܘ_���p�̑S�����u�㊿�����̂܂܁v�ƌ����̂ł͂���܂���
�Ӗ����킩���B
���u�㊿���̗����H�ɏ]�������߁v�ƌ����Ă���܂�
������A������I�J�V�C�ƌ����Ă��܂��A���́E�E�E�B
������ȍ~�̗�����W���⑾���䗗�Ȃǂ́A���R�A鰎u���㊿�������Ă���̂ł�����A鰎u���㊿���̋L�ڂ̍��ق̂��镔���́A���҂̔��f�ɂ���āA����Ƃ����鰎u�������A����Ƃ���͌㊿���������Ă���悤�Ɍ����܂�
���ꂪ�Ȃu�הn�i�v�Ƃ����\�L�ƊW�����ł����H�w鰎u�x���Q�ƁE���p���āu�i�v��p������̂���ł���B�u��v��p���Ă���̂́A�u���v�܂ł���܂���B
����t�Ấu�����{���i�L���㎚�Ҍ��v�Ƃ����悤�ɁA����Ɂu�i�v���u��v�Ƃ���҂��L��A�����،����Ă��܂�
���́u���v���u���i�v�ł��낤���Ƃ͊��ɐ������܂����B����A�Óc���̐����́u���i�{�v���A�V�_���J��u����{�v�ɏ����������Ƃ������̂ł�����ˁH�Ȃ�Ńh�b�O���[�X�����錚����V�_���J��u����{�v�Ɖ��߂ɂ�Ȃ��̂ł����H���̗��R��������Ă��������B
���u鰚�K�c�v�����̗�ł�
�u鰚�K�c�v�Ƃ����\�L������̂��̂Ȃ�ł����H�茳�̕S�Ӗ{�w�j�L�x�́u�v�c���Łv�ł���B
�����u���}�^�C�v�u���q�^�C�v�u���}�C�v�Ȃǂ̌ď̂������Ă����E�E�E�Ƃ����̂���ʂ�r�������Ȑ�
�����낢��Ȍď̂����������͎j�����Ԃł�
�ď̂ł͂���܂���ˁB�\�L�ł��B�g�ď́h�Ƃ͌����ɑ��݂����Ăі��̂��ƁB���̕\�L�������ɂ��������̂��ǂ�����_���Ă���̂ł��B�U������͖��ᔻ�ɏ����Ă��邱�Ƃ����̂܂��݂��Ă����Ƒ����Ă��ł���ˁH�j�����߂̑�������Ԉ���Ă��܂��B
���ނ��뒘�҂̗����┻�f�ɂ���ď��������Ă��鎖���A�r�����悤�Ƃ���p�������ł�
�u���҂̗����┻�f�ɂ���ď��������Ă���v�̂��u��v�B�I���W�i���͈��������܂���B
to# by
Re: �u�V�n�N��搶�v�I����ł�
2007/2/16 22:23:00
���b�Z�[�W:#69097
�����̂��A���肪�Ƃ��������܂�m(_ _)m
���@�k���掏
�����E�q�ƕ_蝐��{
�͊m�F���Ă����̂ł����A
���kꎛI�[�����L
�������Ƃ��Ă��܂����B�摜���ڂ₯�Ă����̂ŁA���������悤�ł�(^^;)
�������B�D�z�{�ʛ��Ӗ����ꑂ�v�l����
�����u�i�v�̎������ɂȂ������ԓI�Ȃ�ł���
�͂��A�܂��ɂ��̂悤�ŁE�E�E�B
��
���������َ��̂��������Ƃ���ɂ͎��Ⴊ���Ȃ��ł���
�u�i�v�́u��v�Ə������Ƃ����邪�t�͂Ȃ�
�Ƃ������ۂ��Ȃ�Ɨ������邩�c
��
�m���ɁA
�u�הn��v�͏����Ƃ̍Z���ŁA�u鰚�K�c�v�͎��ۂ̏����ŁA�u������v�͌Z��̖��O����A�܂��u����{�v�́w�����䗗�x�̋L������u�i����v�ւ̌�ʂ��^�����ɂȂ�܂��ˁB
�܂��A��{�f�[�^�x�[�X�Łu��v�����������̂ł����A����͂܂������ɂ���ɂ��́u��v�u�فv�����������炸�A������Ɍ�����u���i�v�u����v�u����v�̃P�[�X�ɂ��Ă͍l�@���y�Ȃ��Ƃ���ł��B
��������Ɠ���ł���
�Óc�����R�O�N�O�ɁA���̃f�[�^�x�[�X�́u��v��m���Ă�����ǂ��������낤���H�ƁA�t�g�v���Ă��܂��܂����B
to#69063 by tenchuukun
Re: ����j���̌㊿���D���`
2007/2/18 22:58:00
���b�Z�[�W:#69175
�������㊿���ȊO�̏����Ƃ́A����Ɍ��̓���j���̂��Ƃł���A���̒��̗������@���Ɩk�j���n�܂�ł����A��������A鰎u�ƌ㊿�����Q�Ƃ��Ă��邪�㊿���̕������D�悵�Ă���̂ł�
�����悭�܂����C�ł���Ȃ��Ƃ������܂��˂��I�w�����x�Ɓw�k�j�x�͊ԈႢ�Ȃ��w鰎u�x���Q�Ƃ��Ă��܂���ˁB�L���͂������ł���H�w�k�j�x�́u鰎u�H�E�E�E�v�Ƃ͏����Ă���܂��A�قڈ��p�Ƃ�����ł��傤�B���A�w�@���x�́u鰎u�v�Ɩ��L���āu�הn�i�v�Ə����Ă���̂ł��B�ǂ����u�㊿���̕������D�悵�Ă���̂ł��v�ɂȂ��ł����H
���Óc�����P���̂X�O�ł̕\�ɋ������Ă��܂���
���̕\����u�㊿���D���`�v���������ƌ�����ƁH���̕\�ł́w�O���u�x�w�㊿���x�w�����x�w�k�j�x�w�@���x�Ɣ�r���Ă���܂����A(a)�`(e)�܂łɕt���Č��Ă݂܂��傤�B
(a)�w�k�j�x�w�@���x�́w鰎u�x�������āu�הn�i�v�Ƃ���B�w�����x�́u�V�n�i�v�͗�̍s���L�����ł��邩��A�w鰎u�x�ɋ��������̂ł��邱�Ɩ��炩�B
(b)�w�@���x�u�y�Q�S���y�ёѕ��S�����邱�ƁE�E�E�v�Ƃ��邩��A�w�㊿���x�u�y�Q�S�v�Ɓw�O���u�x�u�ѕ��S�v�̐ܒ��L���B
(c)�w�����x�u���̑��A�������j�����v�́w�㊿���x�̋L���ɋ߂����A�w�����x�̂��̋L���̒��O�u����\�v�́w�O���u�x�ɂ͌����邪�w�㊿���x�ɂ͌����Ȃ��̂łǂ����D�悵�Ĉ��������͌����Ȃ��B�w�O���u�x�̕�����D�悵�Ĉ������L���������邱�Ƃ��o����B
(d)�u���E���̊ԁv�u�����a���v�ɂ��ẮA�w�@���x�͊m���ɂ��̕����́w�㊿���x�̋L���������Ă���B�������A�w�����x�́u�����a���v�́A�S���������w�䗗鰎u�x�ɂ�������̂ŁA�w�����x�̂��̕������w�㊿���x�ɂ�����Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(e)�u����������N�v�u����i�����N�v�B����͌㊿��̋L���ł��邩��A�w�O���u�x�ɏڏq�����ׂ����̂ł͂Ȃ��B����ėD��̔�r�̑ΏۂƂ��Ă͓K�ł͂Ȃ��B
�������ł����H�������T���ڂŁu�㊿���D���`�v�Ȃ�Č����Ȃ��̂ł��B
������̎j�Ƃ�O�������ɂƂ��āA�`�ɂ��ẮA�O���u�ƌ㊿���Ƃł́A�㊿���͎O���u���Q�Ƃ��Ă�����Ӊ����ċ����֒��\�������ɂ͓��e�ύX�ɂȂ�L�ڂ����Ă��܂��Ă���̂ɁA�㊿���̕����A�`�z������̋L�ڂ����邱�Ƃ�A�\���ɋ�̓I�Ȃ��̂����邽�߁H�ɁA�㊿�����u�ʐ��v�I�Ȉʒu���߂��̂ł͂Ȃ����H�A�Ƃ������Ƃł�
���x���\���グ�Ă���悤�ɁA����Ȃ�w�@���x�́w�㊿���x����u�הn�i���v�������͂��ł���ˁH�Ȃ�Łw鰎u�x�����������ł��傤�H
�������āA���̒ʐ��́A�ʖ{�ɂ��e��������A鰎u�ɂ��u�u�הn�i���v�Ə���������ʖ{�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����H�Ǝv���܂�
����ł́A���ɂ�������u�i�v�u��v�̈ٓ��̐������t���܂���B�u�@��v�u�@�i�v�A�w鰚�K�c�x�w��i�K�c�x�A�u����{�v�u���i�{�v�A�u����v�u���i�v�u����v�̈ٓ��́A�u�㊿���D���`�v�Ƃ͖��W�ȂƂ���Ŕ������Ă��܂�����ˁB
�u�u�הn�i���v�Ə���������ʖ{�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����v�Ƃ܂őz��ł���̂Ȃ�A��L�̊e��̏o�����猩�āA��ʂ������{�����������ƍl���邱�Ƃ��o����͂��ł����E�E�E�B
to#69154 by zarakoku
Re: ����j���̌㊿���D���`
2007/2/22 23:53:00
���b�Z�[�W:#69337
������j�����㊿���̋L�ڂP���Ă��鎖�ɂȂ�̂ł�����A����j���̌㊿���D���`�̖T�ƌ����܂�
�U������́g�D��h�̈Ӗ��A�������ł����H�ǂ����g�D��h�Ȃ�ł��傤�H
������j�����A鰎u�����A鰎u���֑�\�������菑���������肵���㊿���ɋ����Ă��鎖���A�͂����肵�Ă��܂���
���ɏ������Ƃ���ł��B�w�����x�́w鰎u�x�ɑ���ˑ��x���w�㊿���x��荂���B���̍s���L������Ƃ��Ă�����͖��炩�B
������ɂ́A�u���i�{�v���u����{�v�Ə��������u�����{�v�����鎖���w�E����Ă���̂ł�����
����͉��x���������܂����B�u���i�{�v���u���i�{�v�ƊԈ���Ă����̂ł��B�Ȃ�Łu���v���u�V�_�v�ɏ����������ɂ�Ȃ��̂ł����H
���䗗鰎u���A鰎u���p�Ȃ̂ɁA�㊿�������������̋L�ڂ������Ă���A�Ƃ���������
�������������͂���܂���B
���܂�A�ʐ��Ɉˑ���������ʖ{�́A�ʖ{�{���̋Ɩ������������̂��A�ƌ����\�������鎖�ł�
���́g���㛍�{�h�͂ǂ��ɍs������ł����H�P�O���I���܂ł͊m���ɑ��݂��Ă�����ł���ˁB�u�i�v�Ə����ʖ{���E�E�E�B
to#69255 by zarakoku
Re: ����j���̌㊿���D���`
2007/2/25 22:44:00
���b�Z�[�W:#69525
����������ɂ́A�u���i�{�v���u����{�v�Ə��������u�����{�v�����鎖���w�E����Ă���̂ł�����
��������͉��x���������܂����B�u���i�{�v���u���i�{�v�ƊԈ���Ă����̂ł��B�Ȃ�Łu���v���u�V�_�v�ɏ����������ɂ�Ȃ��̂ł����H
�������猾���Ă��A�b������Ă���悤�ł���B���̘b�́A�Óc����̑�S���̂P�V�R�ł̏I���ɏ�����Ă����t�Â̒��̘b�ł�
�������̘b�ł���B���N���炢�O�ɂȂ�܂��B#46570�����ǂ݉������B�Óc�����A�u���i�v���u����v�Ə������߂����R�Ƃ�����̂́u�V�_���J��{�a�v�́u����v�ł���A�ł���ˁB�����P�V�U�łɏ����Ă���܂��B�ł����A�Óc�����g���P�V�R�łŁu���i�{�O�L�����V�v�ƈ��p���Ă���悤�ɁA����͌��Ɋւ��(�����)�����̘b�Ȃ̂ł��B������u�V�_�v�Ɍ����t��Ă��邱�Ƃ��ĎO�w�E���Ă����̂ł��B�Ȃ�Łu���v�Ɓu�V�_�v���W�L���ł������āE�E�E�B
�������䗗鰎u���A鰎u���p�Ȃ̂ɁA�㊿�������������̋L�ڂ������Ă���A�Ƃ���������
�����������������͂���܂���
�������ƌ䗗鰎u���u�������a���v�Ə����Ă���̂́A�����ł���
�����ł���B�ł��u�����䗗�o�j�}���j�ځv�ɂ́w�����x�͌����܂���A�U������̉]���悤�Ɂu�㊿�������������̋L�ڂ������Ă���v�Ƃ����͎̂����ɔ����܂��B
���䗗�����p�����ʖ{�ɂ͏��߂���u�������a���v��u�i�v�Ə�����Ă����̂��H
���������ł��傤�B
�������Ă��鎖�́A�Ŗ{���쎞�ɁA�䗗�̂����H�����u�ے�v���ꂽ�A�ƌ������Ƃł�
�w�䗗�x�����������ƁH��Ɏ����u�\�L�Q�v�̘b�����܂�����ˁH�w�䗗�x�̕\�L�̓O���[�v���Ȃ��Ă���̂ł��B����A���{�w鰎u�x�̕\�L�́g�ǓƁh�ł��B
���̈Ӗ�����Ƃ���͈�����Ȃ��ƍl���܂��B�����A���{�ɗp����ꂽ�w鰎u�x�͐V�o�̂��̂ŁA����܂ŏ����ɗp�����Ă����w鰎u�x�Ƃ͌n�����قɂ�����̂ł��낤�E�E�E�Ƃ������Ƃł��B
�ŁA���̐V�o�́w鰎u�x(�O���u)�̏o�����������ł���ˁB���ꂪ�A�@���ȑO�̎p���c�������́g�Ö{�h�ł���Ȃ�A����ɂ��̊��{�����������{�ɍł��߂����ƂɂȂ�܂��B
���̂悤�ȉ\�����l���邱�Ƃ͓��R������邩�Ǝv���܂����A�����̉\���𗠂Â���g�����h���Ȃ��̂ł��B
�]���āA�U������̂悤�ɁA���{�������ł��悭�����{�̎p���c�����̂ł���E�E�E�Ƃ����������낤�Ƃ���̂Ȃ�A���̏o���ɂ��Ă̒T�������˂Ȃ�Ȃ��ł���B����Ȃ��Ɂg���j���h�ȂǂƌJ��Ԃ��Ă��A����͂���ڂɉ߂��܂���B�����̎咣�͘_�����\�����Ă��܂����A�U������̎咣�͂�����`������Ɏ����Ă��Ȃ��ƍl���܂��B
to#69492 by zarakoku
Re: �܂��䗗�̋L�ڂŁu�����̒��v��ے�H
2007/3/2 23:53:00
���b�Z�[�W:#69745
�����ʂ́A���ޏ��̌䗗���A���Ȕ��f�Łu��v�́u�i�v�̊ԈႢ���A�Ƃ��āA�u���i�{�v�Ə����������̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��A�l����̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
����͂Ȃ��ł��傤�B�����āA����ɂ́u����{�v���u���i�{�v���Ȃ��u���i�{�v������E�E�E�Ƃ������Ȃ̂ł�����A����������̂Ȃ�u���i�{�v�Ƃ���͂��ł���ˁH
����������ɁA����ɂ��L���ǂ܂�Ă���S�Ӗ{�w�����x(�k�v�E�i�S���{)�ɂ́u����{�v�ƌ����邱�Ƃ���A����͑v��A�����ɓ������ėp����ꂽ�w�����x�e�L�X�g�ɂ����āA�͂��߂āu����{�v�Ƃ����\�L���o���������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B����͂܂������A�S�Ӗ{�w�O���u�x�Ɂu�הn�㍑�v�Ƃ���A����ɐ旧�����Ɂu�הn�i���v�Ƃ��鎖���W�Ɓg�O����h�ɂ��܂�
�������҂��A�ʖ{�́u�i�v���u��v�ɊԈႦ���A�Ƃł������̂ł����H�@�����́A�ʖ{�ɂ́u��v�Ƃ������A����ے肳���̂ł����H
�������A��L�������ǂ݂���������Ε�����Ǝv���܂��B�����ɂ��ĉ]���ꍇ�́u�e�L�X�g�v�Ƃ����̂͒�{�Ƃ����Ӗ��ł�����A�u����{�v�Ƃ���ʖ{���������̂͊m�����낤�Ǝv���܂���B�����A���̎ʖ{�̏o�����������́u�����`�v���v���낤�Ɛ��肵�Ă���킯�ł��B
������ɂ́A�u���v�Ɓu���v���ԈႦ��l���A����Ȃɑ��������̂ł����H
�N�������Ȃ�ĉ]���Ă܂��E�E�E�B�U������͓���̕����Ԃ̌�ʂ��p�ɂɌ�����Ƃł��l���Ă��ł��傤���˂��H�܁A�u��ƎO�v�͂��Ȃ�p�o���܂����A����ł����ׂẮu��ƎO�v�𒊏o���Ē��ׂ���A���I�ɂ͑����Ⴂ�ł��傤�B����́u��v�Ƃ��u�O�v�Ƃ��]���������̂̏o�������ɑ����B�Óc���̑�P���ł����킹�ĂP�R�V�T����Ə�����Ă��܂��B���̏�u��ƎO�v�͔Ŗ̖��ł╶���̂�����ȂǂŌ�ʂ���₷�����Ƃ��e�Ղɍl�����܂��B�ł�����A���̃P�[�X�͑����������Ă��܂��B
�u���Ƒ��v�ł͂���܂��A�u���Ƒ�v�̈ٓ��ɂ��Ă͒����Z�w�O���u�Z���L�x�ɂ��Q�ዓ���Ă���܂��B
�u���O�\�v���t��O�s���A�v�{�́u���v�Ɠa�{�́u��v�B
�������t��܍s���A�v�{�́u��v�Ɠa�{�́u���v�B
��������v�{����Ƃ��āA�a�{�ɂ���ĉ��߂Ă���܂��B�܂�A��������u�S�Ӗ{�v��ł́A���ɏC�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
���u���v�Ɓu���v�̊ԈႢ�����Ȃ�u���i�L�쑾�i���ҁv�Ɓu�i�v��t���Ȃ��Ă��A�u���L�쑾���ҁv�ł��\���ł���H
����͎��ɂ����Ƃ��Ȏw�E�ł��ˁB���ꂩ��Z���L�����鎞�ɂ́A���̓_�ɗ��ӂ��Ă����܂��傤�B�ȂV�������������邩���m��܂���B
�Ђ���Ƃ���ƁA�u�i�ƚ�̌�v����t�Â̓����ɂ܂ők�邩���m��܂���E�E�E�B
�����́A�d����̎����̕����ƁA�������ꂽ����̗�����PC������܂������A�����̒�������d�����PC�������Ȃ��Ȃ�܂��āA���炭���Ԏ������Ȃ�x���̂ł͂Ȃ����H�Ǝv���܂��B�\���������܂���
�܁A�ڂ��ڂ����܂��傤�B��������ӂ�Ɏ��Ԃ��g����킯�ł�����܂���E�E�E�B
to#69705 by zarakoku
Re: �̓�q�́u����{�v�H
2007/3/6 23:12:00
���b�Z�[�W:#69909
���������A�̓�q���u�V�_���J��{�a�v���u����{�v�Ƃ��A�܂�����Ƃ͕ʂɊ����ł́u����v�Ɓu����v�����ʂ��ėp����ꂽ�A�ƌ����̂ł�����A����́u�����{�v�ɁA�u����{�v�̊ԈႢ���A�Ɖ�����l�������\���͂���̂ł�
�Óc���͑�l���A�P�V�T�`�P�V�U�łŎ��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B
�|�|�|�|�|
���̂悤�Ɍ����Ă���A���́u���i�{�����{�v�Ƃ���������s�Ȃ����u���̏��{�v�̎����I���i�����炩�ƂȂ낤�B�u���i�{�v�Ƃ������ʂ���قƂ��A(�Ƃ��ɁA�u�i�v�́u�{�v���w�����ƂƂȂ������߁A��ォ��͂��̗����͏d���ƌ�����悤�ɂȂ����B�܂��u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ��B)������u���{�v�Ɓu����v���Ă���̂ł���B
�|�|�|�|�|
�Óc�����g���A�P�V�R�łɈ������悤�ɁA���́u���i�{�v�ɑ����āu�����V�v�Ə�����Ă���܂���ˁB�u��v�́u���v�ł��B�Ȃ�Łu�ɂ��킵���Ȃ��v��ł��傤���˂��H�V�_���J��{�a�̕����A��قǁu�ɂ��킵���Ȃ��v�Ǝv���܂����E�E�E�B
����Ɓu�d���v�ł����A�u�s�i�{�v�u���i�{�v�u�O�i�{�v�u�_�i�{�v�ƁA���ۂɂ���܂��B�d��������A�ʂ̎��ɏ����������Ƃ������̗�ł������ł��傤���H
�Óc���̔����ɂ͍������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
to#69871 by zarakoku
Re: �u�i�v�́u�{�v���w������d���H
2007/3/8 23:59:00
���b�Z�[�W:#70067
�����Óc���͑�l���A�P�V�T�`�P�V�U�łŎ��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�|�|�|�|�|���̂悤�Ɍ����Ă���A���́u���i�{�����{�v�Ƃ���������s�Ȃ����u���̏��{�v�̎����I���i�����炩�ƂȂ낤�B�u���i�{�v�Ƃ������ʂ���قƂ��A(�Ƃ��ɁA�u�i�v�́u�{�v���w�����ƂƂȂ������߁A��ォ��͂��̗����͏d���ƌ�����悤�ɂȂ����B�܂��u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ��B)������u���{�v�Ɓu����v���Ă���̂ł���B�|�|�|�|�|�Óc�����g���A�P�V�R�łɈ������悤�ɁA���́u���i�{�v�ɑ����āu�����V�v�Ə�����Ă���܂���ˁB�u��v�́u���v�ł��B�Ȃ�Łu�ɂ��킵���Ȃ��v��ł��傤���˂��H�V�_���J��{�a�̕����A��قǁu�ɂ��킵���Ȃ��v�Ǝv���܂����E�E�E
���Óc����́A����̍����{���u���i�{�v���u���{�v�ɕς������R���A�����{�̗���ɂȂ��āA���肵�Ă����邾���Ȃ̂ł�
�ǂ����g�����{�̗���h�Ȃ�ł����H�Ȃ�Łg�����{�̗���h�̗���ɗ��ƁA���Ƃ͖��W�ȓV�_���J��{�a�̘b�ɂȂ��ł����H������ĎO���q�˂��Ă����ł����ˁ`�B
�������hyena no papa����́A��������̂ł�����A���R�u�����킵���Ȃ��v�Ɣ��邾���ł���H
�́H�y���}��їL���i�{�O�L�����V�z�ł���B
�w�����p�V�x�ɂ́u�����{�S�b�v�Ƃ���A�w�֒��L�x�ɂ́u�����V�A���n�V�A�����V�A�V���V�A�����V�v�Ƃ���܂��B�܂�A�������ȃ��P�ł��B���̉��}��тɂ���Ƃ����u���i�{�v���Ȃ�œV�_���J��u����{�v�Ə����������ł����H
���u�i�{�v���u��{�v�ɏ���������ꂽ���R�̐���A�ł�����A���͂���܂���
�܂�́A�Óc���̐���ɂ͍������Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
���܂��A���Ɂu�`�i�{�v�����鎖�͍\���܂���B���Ɂu�u�`�i�{�v����R���邱�Ƃ�m���Ă���l�Ȃ�A�u�i�{�v���u��{�v�ɗ]�菑�������܂����
����܂��Óc���̌����Ă邱�Ƃ��������ł��邱�Ƃ̏ł��ˁB
�����A���̌��i�{�E����{�ɂ�����u�i�ƚ�v�ɂ��āA��ʂł��邱�Ƃ�ے肷�鍪���́A�Óc���ɂ͂Ȃ��g�����h�Ƃ������Ƃł��B
to#70010 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/3/11 0:20:00
���b�Z�[�W:#70221
���������A���̌��i�{�E����{�ɂ�����u�i�ƚ�v�ɂ��āA��ʂł��邱�Ƃ�ے肷�鍪���́A�Óc���ɂ͂Ȃ��g�����h�Ƃ������Ƃł�
���Óc����́A��t�Â̒��ɁA����̍����{�Ɂu���i�{�v���u���{�v�Ƃ����Ă�����̂���A�Ƃ���Ă��邩��A�u����{�v�̈Ӗ����l���āA���̂���ȋL�ڂ��������̂��H���l���Ă��邾���ł���H
������A�Ȃ�Łg��ʂ̉\���h���l���Ȃ��̂��H�Ƃ������Ƃł���B�u���́v�ƍl�����̂Ȃ�A�u���邢�͌�ʂ��H�v�Ƃ��l����ł���H�ł��Óc���́u���i�{�v�Ƃ͂Ȃ�̊W���Ȃ��u����{�v�ɏ����������E�E�E�Ƃ������߂��o���Ă���킯�ł��B
���莁���u���̗�v�Ƃ��Ă������u���i�{�`����{�v���A�Óc���́u���肵�Ă���̂ł���v(��S���P�V�U�łP�s)�Ɖ]���܂��B�����ŌÓc���́g��ʂ̉\���h�ɂ��Ă͂Ȃ��G��Ă͂��܂���B�t�ɁA�u��v�Ɖ��߂��u����v�u������҂̍����v�ƒf���Ă��܂�(���P�V�V��)�B
�U������͉]���܂�����ˁH�Óc���͌����đS�Ă̌�ʂ̉\����ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��ƁE�E�E�B�ł��A�����ł͂Ȃ���ʂ̉\���̌������邱�ƂȂ��A���W�ȗ�������o���āg����_�h�ɏI�n���Ă��܂��B
����ł��Óc���́A��ʂ̉\�����F�߂Ă����ł����H
�������āA�����䗗�́u���i�{�v�ł͈Ӗ��͒ʂ�Ȃ��̂ł���H
�Ӗ��̒ʂ�Ȃ����Ƃ�������Ă���̂Ȃ�A�����g��ʁh�̉\���������ł��傤�B��ʂ͈Ӗ����ʂ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂���܂����A�Ӗ����ʂ�Ȃ��Ȃ�u����v�͍l���ɂ����ł��傤�B
�������ɓV�_���J��Ƃ����̂��A�Ӗ����ʂ��܂����ˁH
��������Ahyena no papa����́u���v���u���v�ɊԈႢ���������Ă�����̂ł���H
�u�A�v�̏ꏊ�̈Ⴂ�ł�����A�\�����链���ʂł��B
�������䗗�́A�ǂ����Ӑ}�I�������������s���Ă��܂�����A�M���u���Ȃ��̂ł���
�ւ��H����Ɓw�䗗�x�ł́A�w�����x�̒����u����{�v���u���i�{�v�Ɓg�����������h�����ƁH�Ӗ��̒ʂ��Ȃ��Ȃ�g�����������h�H
�Ӗ����ʂ���悤�Ɂg���������h��Ɖ]���̂Ȃ番����܂����A�Ӗ����ʂ��Ȃ��悤�Ɂg���������h���Ƃ����̂́A������ƍl���ɂ����ł��ˁ`�B�U������ɂ͍l�������ł����H���́A�Ӗ����ʂ��Ȃ��Ȃ�g���������h�Ƃ����̂́E�E�E�H
to#70155 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/3/15 23:49:00
���b�Z�[�W:#70464
�����x�������܂������A�Óc����́A��ʂ̉\�����A�ʂɔے肳��Ă��܂����
�ł��A���ۂɂ͂��̗��(�K�v�\���ȍ������Ȃ�)�����Ă͂��Ȃ��̂��Ⴀ��܂��H
�����������āA�����䗗�́u���i�{�v�ł͈Ӗ��͒ʂ�Ȃ��̂ł���H
�����Ӗ��̒ʂ�Ȃ����Ƃ�������Ă���̂Ȃ�A�����g��ʁh�̉\���������ł��傤�B��ʂ͈Ӗ����ʂ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂���܂����A�Ӗ����ʂ�Ȃ��Ȃ�u����v�͍l���ɂ����ł��傤�B�������ɓV�_���J��Ƃ����̂��A�Ӗ����ʂ��܂����ˁH
������Ȃ�A�����䗗���u�������v�����u����{�v�̋L�ڂ����Ȃ̂ł͂���܂��H
���̂��Ƃł��傤�H�u�������v�����u����{�v�̋L�ڂ��Ă̂́E�E�E�H�w�䗗�x�́u���i�{�v�ł���ˁB
���u���v���u���v�̊ԈႤ��́A�Ȃ������̂ł͂Ȃ��̂ł����H
���̂Ƃ���m��܂���B�w�����x�̗�ȊO�ɂ́E�E�E�B
���������䗗�́A�ǂ����Ӑ}�I�������������s���Ă��܂�����A�M���u���Ȃ��̂ł���
�����ւ��H����Ɓw�䗗�x�ł́A�w�����x�̒����u����{�v���u���i�{�v�Ɓg�����������h�����ƁH�Ӗ��̒ʂ��Ȃ��Ȃ�g�����������h�H�Ӗ����ʂ���悤�Ɂg���������h��Ɖ]���̂Ȃ番����܂����A�Ӗ����ʂ��Ȃ��悤�Ɂg���������h���Ƃ����̂́A������ƍl���ɂ����ł��ˁ`�B�U������ɂ͍l�������ł����H���́A�Ӗ����ʂ��Ȃ��Ȃ�g���������h�Ƃ����̂́E�E�E�H
���t�Ấu�����{�v�̈��p���A���������������䗗�ɕ��������ꂽ��ǂ��ł����H
�b����炳�Ȃ��ł��������ȁB�U������͌�ʂł͂Ȃ��A�����������ƍl�����ł���H�u���i�{������{�v�ɂ���A�w�䗗�x�́u���i�{�v�ɂ���B�����������Ƃ����̂Ȃ�A�Ӗ����ʂ�悤�ɏ���������͂��ł���H�Ӗ����ʂ�Ȃ��Ȃ鏑��������������āA�U������͍l�������ł����H�Ƃ������q�˂ł���B
to#70379 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/3/18 0:28:00
���b�Z�[�W:#70582
�����b����炳�Ȃ��ł��������ȁB�U������͌�ʂł͂Ȃ��A�����������ƍl�����ł���H�u���i�{������{�v�ɂ���A�w�䗗�x�́u���i�{�v�ɂ���B�����������Ƃ����̂Ȃ�A�Ӗ����ʂ�悤�ɏ���������͂��ł���H�Ӗ����ʂ�Ȃ��Ȃ鏑��������������āA�U������͍l�������ł����H�Ƃ������q�˂ł���
�����́u���i�{�v�̈Ӗ��͔���܂����
����A�U�������̈Ӗ���m���Ă��邩�ǂ������Ă����Ȃ��āA�u���i�{�v�ɂ���u����{�v�ɂ���A�����������Ƃ͍l����̂ɁA��ʂƂ͂Ȃ��l���Ȃ��̂��H�ƌ����^��Ȃ�ł��B
�Óc���́u����{�v���u�V�_���J��{�a�v�̈Ӗ��ŁA�u���i�{�v�ł̓I�J�V�C���炻�������������E�E�E�Ǝ咣����Ă���ł���H�������A����͋؈Ⴂ�̐����ł�����ˁB�u���v�̘b�ł�����B�ł�����A��͂�Óc���ɂ����������̗��R�͕�����Ȃ��B
�ł��u��ʁv�Ƃ͍l���Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃł���ˁH����͂Ȃɂ䂦���낤���H�Ǝv����ł��B����قǂ܂łɁu��ʁv�Ƃ̍l���������̂́E�E�E�B�Óc���́A��ʂ̉\����S�Ĕے肷��킯����Ȃ���ł���ˁH����A�����ł��u��ʁv�̉\�����ꉞ�l���Ă݂�ׂ��������̂ł́H
�ł��A��������Ȃ��Łu���v�Ƃ͖��W�ȁu�V�_�v�̘b�������Ă��Đ������悤�Ƃ����B����͒ʂ�܂���B
to#70552 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/3/24 0:04:00
���b�Z�[�W:#70872
���������́u���i�{�v�̈Ӗ��͔���܂����
��������A�U�������̈Ӗ���m���Ă��邩�ǂ������Ă����Ȃ��āA�u���i�{�v�ɂ���u����{�v�ɂ���A�����������Ƃ͍l����̂ɁA��ʂƂ͂Ȃ��l���Ȃ��̂��H�ƌ����^��Ȃ�ł�
����t�Â��A�u�����{�v�Ɂu���{�v�Ə��������̂�����A�Ƃ��A����́u����{�v�̎����Ƃ��āu����ɂ͑���{�͂Ȃ��v�Ə����Ă���̂ł�����A���̒i�K�ł́A�X�g�[���[�ɖ��͂���܂���
������Óc���́u���i�{������{�v�ւ̏����������Ɛ�������킯�ł���ˁH�ł��A�����������ƍl����ɂ͍����ɖR�����B�ł�����A�u��ʂƂ͂Ȃ��l���Ȃ��̂��H�v�Ƃ����^������̂ł��B
�����́u���{�v���A�����䗗���u���i�{�v�Ə���������A���ɂȂ��������ł�
�������A�u���i�{�v�Ƃ����̂́A�����T���o���Ă������̂ł�����A�Óc���̏��_�ɂ͉e������܂����ˁH����Y��Y�����A�u�i�ƚ�̌�ʗ�v�Ƃ��Ă��́u���i�{�A����{�v�����������ɏo�����B����ւ̔��_�Ƃ��ČÓc���́u����{�ւ̏��������ł���v�Ƃ����B�܂�A��ʂ�ے肵���̂ł��B
�ŁA���������̗��R�Ƃ��Ă������̂��A��L�́u����{���V�_���J��{�a�v�B����͗��R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���x�����������Ƃ���ł��B�܂�A���莁�́u��ʐ��v��ے肷��ɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���܂�A�u�����{�̌�����������v�̈Ӗ����A��t�Â̎w�E�ɍ��킹�āA�������āi�����āj�����������Ȃ̂ł�
��t�Â��u��������������v�Ɖ]���Ă����ł����H�u���v�Ƃ��������Ă���܂����B�u���v���Ȃ�Łu���������v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��ł����H���������肢���܂��B
�����ǁA�܂��Ahyena no papa����̌Óc��掂��A����o���Ă���悤�Ȃ̂ł�
�����̂��鐳���Ȕᔻ�ł��B������g�Óc��掁h�ȂǂƂ����̂́A�U������̎��ւ́g��掁h�Ǝ~�߂��Ă���ނȂ��ł��傤�B
���u���v�Ƃ͖��W�ȁu�V�_�v�̘b�ƌq����Ӑ}���������̂́A��t�ÂȂ̂ł��B�u����{�v�ƌ������t���o�����̂ł�����
�u���t���o�����v��Ȃ��āA�u�����{�v�ɏ����Ă����ł���B
��������Ahyena no papa����͊�t�ÂɁu�ʂ�܂���v�ƕ���������Ă��鎖�ɂȂ�̂ł���
��t�Â��u�V�_���J�鑾��{�v�Ȃ�ĉ]�����̂ł����H������]�����̂͌Óc���ł��傤���E�E�E�B
to# by
Re: �u�ԈႢ���v�Ƃ͂X���ȏ㌾���Ȃ�
2007/3/25 23:05:00
���b�Z�[�W:#70965
���O���u�́u�i�v�̑S�ᒲ�������łX�����́u����֏ȁv�̎��������ł̎g�p��
���́u�X�����v���Ă̂́A���̃T�C�g�ɏЉ�����̂̂����A�ǂ�ǂ�Ȃ�ł��傤���H
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/sangokushi_no_dai.html
�����̏�A���{�̕����I�ɂ͑S�āu��v�ł���
�@�B�I�ɃR�s�[�������̂�����A���R�B���{�Ԃňٓ��̐�����\���́u0.5%�v���x�B���{�ԂŁu��v�Ɉٓ��������Ȃ��Ƃ��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�����̋��Ε���O��⓯���㕶�������Ƃ��āu��v�Ɓu�i�v�͎��Ă��Ȃ���
���Ă��Ȃ��Ƃ���ʂ��ꂤ��B
���u�ԈႢ���v�Ƃ͂X�����͂邩�ɉz���Č����Ȃ��̂ł�
�ł��A�ԈႢ�͂���B���ꂪ�����B�u��i�K�c��鰚�K�c�v�u�@�i�Ɣ@��v�u���i�{�Ƒ���{�v�u���i�ƍ���ƍ���v�B
��������H�U������͂��́u�הn�i���v�Ƃ����ď̂��A�T���I�A�`�̌܉��̎���ɂ����炳�ꂽ���̂��ƍl���Ă��Ȃ������ł����H������u䗞@�̗E�ݑ��v�ɂȂ�����ł����H
�������A�S�`�T���I�͂����̂ł����A�R���I�ȑO�́A�O���̂悤�Ɂu���������v�Ȃǂ̗��R�łX���ȏ�̊m���Łu�הn�i���v�̋L�ڂ��ے肳��܂�����
�u�ے肳��v�܂���B�U������́A#70821�ŁA�u��i�v�́u���������l�I�Ɂu�Ăv�Ə�����Ă��邶�Ⴀ��܂��I�H�l�I�Ȃ��̂Ȃ�A�ʂɑ��̐l���g�����ɂ͍\���ł��傤�ɁE�E�E�B������A���ςƂ��Ă��u�i�v�Ƃ����������g���Ă���B
���Óc����́u�הn��v�́u�הn�`�v���ɂ���āA�u�הn�㍑�v�́u�`���v�Ƃ��̂܂܌Ă��悤�ɂȂ����̂��ȁH�Ƒz�����Ă��邾���ł�
�܂��܂��ȂӖ����悭������܂���ˁ`�B�u�הn�㍑�v���u�`���v�Ƃ��̂܂܌Ă�邱�ƂɂȂ����H����A�z�������̋ɓ�E�ɂ���u�`���v��A����i�����N�́u�`���v�͈�̉��Ȃ̂ł����H
to#70894 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/3/27 22:42:00
���b�Z�[�W:#71021
��������t�Â��A�u�����{�v�Ɂu���{�v�Ə��������̂�����A�Ƃ��A����́u����{�v�̎����Ƃ��āu����ɂ͑���{�͂Ȃ��v�Ə����Ă���̂ł�����A���̒i�K�ł́A�X�g�[���[�ɖ��͂���܂���
����������Óc���́u���i�{������{�v�ւ̏����������Ɛ�������킯�ł���ˁH
���Ⴂ�܂��ˁB�u�����{�v�Ɂu���i�{�����{�v�Ƃ������̂�����A�Ɛ��������̂͊�t�Âł��B�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł�
�u�Ⴂ�܂��ˁv�B��S���P�V�T�ŁA
�|�|�|�|�|
���̂悤�Ɍ����Ă���A�u���i�{������{�v�Ƃ���������s�Ȃ����u���̏��{�v�̎j�����m�����炩�ɂȂ낤�B�u���i�{�v�Ƃ������ʂ���قƂ��A(�Ƃ��ɁA�u�i�v�́u�{�v���w�����ƂƂȂ������߁A��ォ��͂��̗����͏d���ƌ�����悤�ɂȂ����B�܂��u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ��B)������u����{�v�Ɓu����v���Ă���̂ł���B
�|�|�|�|�|
����ł��u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v���H�����Ɓu����v�ƌ����Ă邶�Ⴀ��܂��I
�����ł��A�����������ƍl����ɂ͍����ɖR�����B�ł�����A�u��ʂƂ͂Ȃ��l���Ȃ��̂��H�v�Ƃ����^������̂ł�
����t�Ấu��ʂ��v�Ƃ͌��߂Ă��Ȃ��悤�ł��B
�u����v�Ƃ����߂Ă͂��܂���B
���u�����{�v�����炩�̍l���ŋL�ڂ����A�ƌ����悤�ɍl�����̂ł͗L��܂��H
����Ȃ��Ƃ͌����Ă��܂���B�y�����{���i�L�쑾�㎚�Ҍ�犿������{��z�ł��B�u���炩�̍l���ŋL�ڂ����A�ƌ����悤�ɍl�����v�Ȃ�Ăǂ����炻���������߂��o�Ă����ł����H��O�݂��������Ƃ���ł��B
������t�Â��u��������������v�Ɖ]���Ă����ł����H�u���v�Ƃ��������Ă���܂����B�u���v���Ȃ�Łu���������v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��ł����H���������肢���܂�
���u���v�ł�����A�ʂɁu��ʂ������v�Ƃ͌����Ă��Ȃ��̂ł�
�u����v���Ƃ������Ă��܂����ˁH
�����R���́u�����v�̉\�����܂ނ̂ł��B���̈���A�Ӑ}�I���������ł���
��q�̒ʂ�A�Óc���́u����v�Ƃ��Ă��܂��B�Ȃ�Łu��ʂ̉\���v���l���Ȃ������̂��H
�P�V�V�ł�������p���܂��傤�B
�|�|�|�|�|
���������Ă��̗�́A�g�w�O���u�x�ȊO�ł͂��邯��ǂ��A�u����i�v�̗����ʂ̍��낪���݂����h�Ƃ��������̎���Ƃ��āA���莁�ɂ���Ē�o���ꂽ�̂ł��邪�A���̎��́A�g�����́u�i�v���y�X�������̒m���������Ɓu��v�Ɖ��߂��h�Ƃ������Ⴞ�����̂ł���B
�|�|�|�|�|
�ǂ��ł����H��t�Â��u���v�Ƃ��������Ă��Ȃ��Ƃ�����Óc���́u����v�u����v�u���߂��v�ƌ��_���Ă��܂���ˁB
�ēx�����܂��B����ł��A
���Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł�
�Ȃ�ł����H
���Ɂg�u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ��h�Ȃ�Ă̂��I�J�V�C�B�u���i�{�v�̒���Ɂu�����V�v�ƌ����Ă���̂ɁA�Ȃ�Łg�ɂ��킵���Ȃ��h��ł��傤���H
�����肳��̘b�́A���́u�����{�v�́u��ʂ̉\���̎w�E�v�ɗ��܂���̂ł�
�d�v�Ȏw�E�ł��B������Óc���͍����ɂȂ�Ȃ��������Ȃāu����v�Ƃ����B���莁�ƌÓc���A�ǂ���̌������ɗ������邩�H��������ɂȂ�܂��H
to#70983 by zarakoku
Re: ���_�@
2007/3/28 23:58:00
���b�Z�[�W:#71052
��ɂ���Ƀ��X��t���܂��B
�����ł��A�ԈႢ�͂���B���ꂪ�����B�u��i�K�c��鰚�K�c�v�u�@�i�Ɣ@��v�u���i�{�Ƒ���{�v�u���i�ƍ���ƍ���v
�������́A�����̎���̘b�Ȃ̂ł��傤���H
�����������B
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/tai_ga_tadashii.html
���ȑO�ɂ��������u�Â��_�@�v�ł͂Ȃ��̂ł����H
�ǂ������Ӗ��ł��傤���H
�����������A�S�`�T���I�͂����̂ł����A�R���I�ȑO�́A�O���̂悤�Ɂu���������v�Ȃǂ̗��R�łX���ȏ�̊m���Łu�הn�i���v�̋L�ڂ��ے肳��܂�����
�����u�ے肳��v�܂���B�U������́A#70821�ŁA�u��i�v�́u���������l�I�Ɂu�Ăv�Ə�����Ă��邶�Ⴀ��܂��I�H�l�I�Ȃ��̂Ȃ�A�ʂɑ��̐l���g�����ɂ͍\���ł��傤�ɁE�E�E�B������A���ςƂ��Ă��u�i�v�Ƃ����������g���Ă���
����͂薳���Ȃ̂ł͂���܂��H�������͂邩�ɍ����g���̍��������A�V�q���u��i�v�ƌĂ�ł���̂ɁA����l�̒����Δ̍����Ɂu�i�v��t���邱�Ƃ́A�܂��l�����܂���
�܂��A�V�q���u��i�v�ƌĂ�ł���E�E�E�Ƃ����̂́A�Óc���̉��߂ɉ߂��܂���B�����ł͂���܂���B�ł�����A�u�̂Ɂv�ȂǂƎ��i�ނ��Ƃ͓���ł��傤�B
���ꂩ��A�u����l�̒����Δ̍����Ɂu�i�v��t���邱�Ƃ́A�܂��l�����܂���v�Ƃ����̂Ȃ�A���́u����l�v�̒����A���������V�q���u�i�v�Ə̂����̂ɁA���g�̖{�����œV�q�̂��Ƃ��u�i�v�ƈꌾ�������Ă��Ȃ��̂́A�u�܂��l�����܂���v�B
�{�������m����u�V�q�v�u���v�u��v�u�c��v�u�É��v�ɂ��Ă̂�����������܂����B�u�i�v�����ꑽ�����t���Ƃ����؋��͂Ȃ���ł���B
���܁A�w�e�{��ꝕٌ��x���דǂ�i�߂Ă���Ƃ���ł����A���́w�e�{��ꝁx�́u���v�͖ʔ��������������Ă���܂��B�u�c�v�u�V�v�u�N�v�Ƃ����������A���̍s���̕���������i�����L���Ă���̂ł��B�Ђ���Ƃ���ƁA���������̂͜�ꑽ���g���������h�ƌ�����̂����m��܂���B�܂��A�w�����䗗�x�����ł��A�u�c�v�u�@�v�u���v�u��v�u�c�v�u���v�u���v�u�v�v�Ȃǂ̕����́A�����ł����Ă��A��X�g���s�h���ď�����Ă���܂��B����́A�������Ă̕\�L�@�Ȃ̂ł��傤�ˁB
���́w�e�{��ꝁx�����Ɂu�i�v�̕���������܂��B��S�t��t��P�s�Q�����ڂł��B�c�O�Ȃ���A��i�������鏑�����Ƃ͂Ȃ��Ă���܂���B�܁A�v��̂��Ƃł�����A鰑�̎Q�l�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���E�E�E�B
�������Óc����́u�הn��v�́u�הn�`�v���ɂ���āA�u�הn�㍑�v�́u�`���v�Ƃ��̂܂܌Ă��悤�ɂȂ����̂��ȁH�Ƒz�����Ă��邾���ł�
�����܂��܂��ȂӖ����悭������܂���ˁ`�B�u�הn�㍑�v���u�`���v�Ƃ��̂܂܌Ă�邱�ƂɂȂ����H����A�z�������̋ɓ�E�ɂ���u�`���v��A����i�����N�́u�`���v�͈�̉��Ȃ̂ł����H
������̍��́A�{���́u�ϓz���v�ł���H
�@
�u����̍��́v�u�`�z���v�ł�(�w�㊿���x�u��I�v�u�`�`�v�A�͍G�w�㊿�I�x)�B
���u�`���v���ǂ����H�͖��m�ł͂���܂���
�u�`�z���v���u�`���v�Ƃ͌����Ă���܂����B�u�z�������̋ɓ�E�ɂ���v�u�`���v�ł���B�w�㊿���x�u�`�`�v�������Ȃ�ł���H
���܂��A�`�����������́A�u���v�̒ʂ�ł���Ή��l����\���������ɂȂ�A�����ʂ�A���̒��Łu�`�v���\�����̂ł��傤
���ʒʂ�u�`�����������v��ǂނƁA�u�����v�́u�`�����v�ł��B�u���l����\�v���������ǂ���������܂��A�ނ�́u�`�����v�łȂ����Ƃ͊m���ł��B�u�`�����v�����l������킯����܂���E�E�E�B
��������A�܂��A�`�̍\�������̕��̌��Ђ������c���Ă���̂ł͂���܂��H
���������̉��������ŁA�u�`�̍\�������̕��̌��Ђ������c���Ă���v�Ȃ�ēǂݎ���ł����H����̓X�S�C�ł��ˁ`�B�m�肷��ɂ���ے肷��ɂ��덪��������܂���A���Ƃ��\���グ�悤������܂���B
to#71050 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/4/1 22:11:00
���b�Z�[�W:#71195
�������Ⴂ�܂��ˁB�u�����{�v�Ɂu���i�{�����{�v�Ƃ������̂�����A�Ɛ��������̂͊�t�Âł��B�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł�
�����u�Ⴂ�܂��ˁv�B��S���P�V�T�ŁA�|�|�|�|�|���̂悤�Ɍ����Ă���A�u���i�{������{�v�Ƃ���������s�Ȃ����u���̏��{�v�̎j�����m�����炩�ɂȂ낤�B�u���i�{�v�Ƃ������ʂ���قƂ��A(�Ƃ��ɁA�u�i�v�́u�{�v���w�����ƂƂȂ������߁A��ォ��͂��̗����͏d���ƌ�����悤�ɂȂ����B�܂��u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ��B)������u����{�v�Ɓu����v���Ă���̂ł���B�|�|�|�|�|����ł��u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v���H�����Ɓu����v�ƌ����Ă邶�Ⴀ��܂��I
����t�Â��u���v�Ǝw�E�����u���i�{������{�v�̕ω��́A�u�����{�v�ɕω����������̂ł�����A������u�����{�̉���v�ƌ����Ă��A����������������܂����
�܂��u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ƃ����̂��ԈႢ�ł��邱�Ƃ͔F�߂܂���ˁH�U�����g��
��������u�����{�̉���v�ƌ����Ă��A����������������܂����
�Ɣ������Ă���킯�ł�����B
���ꂩ��A��t�Ấu���v�Ƃ��������Ă��Ȃ����̂��u�����{�̉���v
�Ɖ��߂���̂͂��܂�ɐg����ł��B�u�끁����v�Ȃ�ł����H
�������āA�Óc����́A����̈Ӗ��◝�R���l�@�������ꂽ�̂ł���H
���ꂩ����A�U������̐�̔����u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v����F�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
����t�Â��u���v�ƌ��������̂��u��ʂ��v�ƌ��ߕt������肳��́A�����u��ʁv�ł��鍪��������ꂽ�̂ł����H
����Ȃ��Ƃ������O�ɁA�u���v�Ƃ��������Ă��Ȃ��̂��u����v�Ƃ����Óc����A�u����v�ƌ����Ă���Óc���̔�������F���āu�l�@���ꂽ�����ł��v�ƌ���ꂽ�U�����g�̂��Ƃ�U��Ԃ�ׂ����Ⴀ��܂��H
to#71084 by zarakoku
Re: ���_�@
2007/4/2 22:12:00
���b�Z�[�W:#71243
�������瓯���㊿�����ł����Ă��A���eA���ԈႢ������A���eB���ԈႢ���A�Ȃ�ĊÂ��_�@�͒ʂ�܂����
����H�������Ȃ��Ƃ����܂���ˁB�Óc���́w�O���u�x���́u�i�ƚ�v��S���������ꂽ�B�ŁA�u�הn��v�u���o�v�ȊO�͊ԈႦ���Ă͂��Ȃ��E�E�E�A������u�הn��v�u���o�v���ԈႢ����Ȃ��ł��낤�B�Ⴂ�܂����H����������������X���A����ȃU������̍l���ւ̔��_�������͂��ł����E�E�E�B
�����ꂾ���łȂ��A�u��i�K�c��鰚�K�c�v�u�@�i�Ɣ@��v�u���i�{�Ƒ���{�v�u���i�ƍ���ƍ���v���A�{���ɊԈႢ�Ȃ̂��H�́A�m�F���Ȃ���Δ���܂���
�ǂ����A���m�F�������B���̌��ʂ����҂��Ă���܂��B
���u���i�{�Ƒ���{�v�͊��ɋc�_�����悤�ɁA�ԈႢ�ł͂Ȃ��u�l���Ĕ��f������ł̋L�ځv�ł���\��������܂�
�ǂ̂悤�ȁg���f�h�Ȃ̂ł����H
to#71151 by 71151
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/4/5 0:25:00
���b�Z�[�W:#71347
���Ӂ[��A�����܂����t�K���ɘ_�ɉ��߂��āA�_��悤�Ƃ���Ă���̂ł��ˁB���i�͒���Ȃ��悤�ł���
����Ȃ��Ƃ����O�ɁA�������̔������Óc���̏�����Ă��邱�ƂƐH������Ă��邱�Ƃ�f���ɔF�߂�ׂ����Ⴀ��܂��H
����t�ẤA�u��������{��v�ƒNjL���Ă���A�������u��L�v�ł���Ί���Ɂu����{�v�̂���b�ȂǑS���K�v���Ȃ��̂ł�����A��t�Â��u���{�v���Ӗ��̂��鏑���������A�ƍl���Ă��鎖�ɂȂ�̂ł���
�Ȃイ���߂������ł��傤���H����܂��g��c�����h�̌��{�B�u����Ɂv���āA���̒����͉��ɕ�����ꂽ���̂Ȃ�ł����H�w�����x�ł��傤���E�E�E�B�w�����x�u�]�[�B�v�́y���[�������i�{�z�̒����Ȃ�ł���B���́u���i�{�v�����̏��{�Ɂu����{�v�Ƃ��Ă�����̂����邪�E�E�E�Ƃ����b�ł��B�Ȃ�ŁA
������Ɂu����{�v�̂���b�ȂǑS���K�v���Ȃ��̂ł�����
�Ȃ�čl���ɂȂ�̂��H
�킩��܂��H
��������t�Â��u���v�ƌ��������̂��u��ʂ��v�ƌ��ߕt������肳��́A�����u��ʁv�ł��鍪��������ꂽ�̂ł����H
��������Ȃ��Ƃ������O�ɁA�u���v�Ƃ��������Ă��Ȃ��̂��u����v�Ƃ����Óc����A�u����v�ƌ����Ă���Óc���̔�������F���āu�l�@���ꂽ�����ł��v�ƌ���ꂽ�U�����g�̂��Ƃ�U��Ԃ�ׂ����Ⴀ��܂��H
���ł́A���肳��́u��ʁv�̐����͂��Ă����Ȃ������̂ł���
���̂ł��ˁ`�B���������u���U�v���q�ׂĂ��邱�Ƃւ̎��o�͖�����ł����H�Óc���̘b�ł���A��F���ĉ�����Ƃ�����Ȃ��E�E�E�Ƃ����̂́A�ő��Óc���ɑ���g���́h�Ƃ������邩���m��܂����B
���莁�̎咣�ɂ��Ă͂������ł����������B�茳�ɂ͋��s��w���{���u�l���v��P�U�W�̃R�s�[������܂������Љ���o���܂����A�m���w�הn�䍑��{�_���W�V�x�ɂ����^����Ă����Ǝv���܂��̂ŁA�������̑��ł��m���߉������B�����͓w�͂��K�v�ł��傤�B
���܂��A�u����v�Ɉꐶ�����ɍS���Ă����܂����A�O���̒ʂ�ł�����Ahyena no papa����́A�������́u���t�K�ɘ_���ߘ_��v�̐��i��U��Ԃ�ׂ����Ⴀ��܂��H
�u����v�Ɉꐶ�����ɍS���Ă����܂����E�E�E���āA�O���܂ł��U������͎��g�́g��F�h�ɂ��Ă͔F�߂悤�Ƃ��Ȃ��̂ł��ˁH
�Óc���̖{�����N�ɓǂ�ł��Ȃ��B�ǂ�ł���F����B�����Ă����Ȃ����̂��������悤�Ɏ咣���A�����Ă��邱�Ƃ������Ă��Ȃ��悤�Ɏ咣����E�E�E�B
�����Óc����������A�U������̂��̗L�l�͖��f�疜�Ɗ�����ł��傤�B
to#71238 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/4/8 0:21:00
���b�Z�[�W:#71605
��_�����A��Ƀ��X���Ă����܂��B
�����̏��{�ɂ���̂́u���{�v�ł��B�u����{�v�ł͂���܂���B
����A�����ł����ˁ`�B�u�S�Ӗ{�v�w�����x(�k�v�i�S���{)�ł͂����ł����B�Óc������S���ŏ�����Ă����̂��A���́u�S�Ӗ{�v����̈��p�ł����B
���̎茳�ɂ́u�m���{��\�j�v�w�����x�Ƃ����̂������āA����͖k�v�~���N�Ԃ̊��{�Ȃ̂ł����A�u�S�Ӗ{�v�̌i�S��萔�\�N��s���܂��B����ɂ́u����{�v�Ƃ���܂��B
�u����{�v�łȂ���Ε��ӂ��ʂ�Ȃ��Ǝv���܂����A�܁A���̂��Ƃ�]��M�p���Ă��Ȃ��U������̂��Ƃł�����A�f���Ɏ~�߂Ă��������邩�ǂ����E�E�E�B
to#71590 by zarakoku
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/4/13 22:48:00
���b�Z�[�W:#71914
�������Ӂ[��A�����܂����t�K���ɘ_�ɉ��߂��āA�_��悤�Ƃ���Ă���̂ł��ˁB���i�͒���Ȃ��悤�ł���
��������Ȃ��Ƃ����O�ɁA�������̔������Óc���̏�����Ă��邱�ƂƐH������Ă��邱�Ƃ�f���ɔF�߂�ׂ����Ⴀ��܂��H
���܂��A�ςȘb���`���悤�Ƃ��Ă���̂ł����H
�@���́A�ʂɌÓc�����P�O�O�����S�ɓ������Ƃ������Ă���A�ȂǂƂ͎v���Ă��܂����B���t��\�����Ⴆ�A�������e�͕ς��ł��傤���A�L���ŏ����A�����v���Ⴂ���L�蓾��ł��傤
�u�L���ŏ����A�����v���Ⴂ���L�蓾��ł��傤�v���āg�v���Ⴂ�h��F�߂Ă��ł����H
���u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ƃ����̂��ԈႢ�ł��邱�Ƃ͔F�߂܂���ˁH
�ɂ��Ăł����E�E�E�B����Ȃ�u�ςȘb���`���悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ����̂͂������Șb�ł��B
���Œ�Ahyena no papa����̂悤�ɕ����̌��t�K�����o���āA�ȉ����Ĕ�掂��悤�ȂǂƂ͎v���Ă��܂���
�������������w�E���ꂽ�����́g���t�K�h���⏬������E�E�E�B�U������́u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ƌ����B����́A�Óc���̔����Ƃ͐H������Ă��܂���ˁB�������ŋL�ڕł���e���c�����Ă��Ȃ���A�Óc���̔����ƈႤ���Ƃ��]���B
�u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ƃ����̂́A�U������̌�F�ł���ˁH
���u�H������Ă��邱�Ƃ�f���ɔF�߂�ׂ����Ⴀ��܂��H�v�ƌ�����ƁA�����ɂ�hyena no papa���S�Ă�����ŁA�f���łȂ��l��@�����`�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂���
���ۂɁA�N���ǂ�ł��H������Ă���ł���H�Óc���́u�l�@���ꂽ�����v�Ȃ�ł����H�Ⴄ��ł���H�u����v�Ɖ]��ꂽ�ł���H
��������t�ẤA�u��������{��v�ƒNjL���Ă���A�������u��L�v�ł���Ί���Ɂu����{�v�̂���b�ȂǑS���K�v���Ȃ��̂ł�����A��t�Â��u���{�v���Ӗ��̂��鏑���������A�ƍl���Ă��鎖�ɂȂ�̂ł���
�����̏��{�ɂ���̂́u���{�v�ł��B�u����{�v�ł͂���܂���
���̌��ɂ��ẮA���ɍŌÂ̊��{�������Đ������܂����B
��������A��t�ẤA�P�Ȃ�뎚�ł͂Ȃ��A�u����{�v�ƌ����Ӗ��̂��鏑���������A�Ɨ������Ă���̂ł�
�u���v�ł��B�Óc������S���P�V�S�łŏ�����Ă���Ƃ���A��t�Â��u�����������v�ƍl���Ă��镔���ɂ��Ắu�����������v�Ɓu���v�̎���p���Ă��܂��B�u���v�́u��Ȃ�v�ŁA����ȏ�̂��̂ł͂���܂���B
���܂��A����܂��H�@�܂��A���t���Ɍ떂������܂����H
�]���Ă����Ȃ����Ƃ��]���Ă���悤�Ɏ咣����̂́u�떂�����v�ł��B
��
�����̂ł��ˁ`�B���������u���U�v���q�ׂĂ��邱�Ƃւ̎��o�͖�����ł����H�Óc���̘b�ł���A��F���ĉ�����Ƃ�����Ȃ��E�E�E�Ƃ����̂́A�ő��Óc���ɑ���g���́h�Ƃ������邩���m��܂����B
���u����v�Ɉꐶ�����ɍS���Ă����܂����E�E�E���āA�O���܂ł��U������͎��g�́g��F�h�ɂ��Ă͔F�߂悤�Ƃ��Ȃ��̂ł��ˁH�@�Óc���̖{�����N�ɓǂ�ł��Ȃ��B�ǂ�ł���F����B�����Ă����Ȃ����̂��������悤�Ɏ咣���A�����Ă��邱�Ƃ������Ă��Ȃ��悤�Ɏ咣����E�E�E�B�����Óc����������A�U������̂��̗L�l�͖��f�疜�Ɗ�����ł��傤
��
��hyena no papa����́A�����䂤���Ȍ��������A���Ȃ̂ł��ˁB�����炭�܂����l���̐l�́A�܂������v���̂ł��傤�ˁB
�@�����A���S���Ă���̂ł���
�g�������h�ł͂Ȃ��A�Óc���ɗ����Ę_�킵�Ă���U�����A�Óc���̏��_���Ԉ���ďЉ�Ă��鎖�ւ̔��Ȃ͂Ȃ��̂ł����H�Ƃ������q�˂Ȃ̂ł��B
�ēx�����܂��B�u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ƃ����̂��ԈႢ�ł��邱�Ƃ͔F�߂܂���ˁH
to#71590 by zarakoku
Re: �C�����������R
2007/4/16 21:48:00
���b�Z�[�W:#
�������\���グ�āA�����ۂ������ĂƂ��Ă��C���������ł�
�U������݂����Ȃ̂��g�����Ă������h���Ă�����ł��傤�ˁ`�B�Óc�����u����v�Ɖ]���Ă���̂ɁA�u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ə���������āA�����P�悤�Ƃ����Ȃ��E�E�E�B
�Óc���̗�������Ȃ���A�Óc���̖{���炫����Ɠǂ�ł��Ȃ��B���ꂶ��A�Óc�������f�ł��傤�B
�U�����Óc���ƈ�����ӌ��������Ƃ́A����Ō��\�Ȃ��ƂȂ�ł����A�Óc���̏��_������ďЉ��ȂǂƂ����̂́A��������Ƃ��Ǝv���̂ł����ˁE�E�E�B
to#72194 by pikupopodemi
Re: ����́u�����{�v�̋L�ڗ��R
2007/4/16 22:21:00
���b�Z�[�W:#72198
�܂��t���Ń��X�������グ�܂��B
�������u�H������Ă��邱�Ƃ�f���ɔF�߂�ׂ����Ⴀ��܂��H�v�ƌ�����ƁA�����ɂ�hyena no papa���S�Ă�����ŁA�f���łȂ��l��@�����`�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂���
�������ۂɁA�N���ǂ�ł��H������Ă���ł���H�Óc���́u�l�@���ꂽ�����v�Ȃ�ł����H�Ⴄ��ł���H�u����v�Ɖ]��ꂽ�ł���H
���Óc����́A���肳��́A����̍����{�́u��v�Ɓu�i�v�̌�T���ɑ��āA��t�Â��A�P���Ȍ�T�Ƃ͍̂炸�Ɂu��������{��v�Ƃ��ĈӖ����鏑��������
�܂����̎��_�ŃE�\�ł��ˁB��t�Â��u�Ӗ����鏑�������v�������ƁA�ǂ��ɏ����Ă���܂����H�����͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�y�t�ÞH�����{���i�L���㎚�Ҍ�犿������{�z
���̒Z�����ʂ���A�ǂ��ǂ߂u�Ӗ����鏑�������v�Ɠǂ݂Ƃ���ł��傤���H�y��������{�z�́y���z�ƍl�������R�ł����āA�u���������v�̗��R�ł͂���܂����B�y���z���u���������v�Ɖ��߂����͖̂O���܂ł��Óc���B
����t�Â̘b�̐��������������ł�
�Óc�����g�A��t�Â̏����Ă��邱�Ƃ����̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�|�|�|�|�|
���̊�t�ẤA����(����)�̖{�ɁA���́u���i�{�v���u���{�v�Ƃ��Ă�����̂����邱�Ƃ��w�E������A����͂���܂肾�A�Ɣ��f�����B
�|�|�|�|�|
�����ČÓc���́A��t�Â��g���߂��h��������Ă��܂��ˁB�u�����A���ނ�̂݁v�ƁB�����āA�Óc���͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�|�|�|�|�|
���̂悤�Ɍ����Ă���A���́u���i�{�����{�v�Ƃ���������s�Ȃ����u���̏��{�v�̎j�����i�����炩�ƂȂ낤�B
�|�|�|�|�|
��������ł����H�u���i�{�����{�v���u����v�Ɖ]���Ă���̂́A��t�Âł͂Ȃ��A�Óc���Ȃ̂ł��B����ł��A�u�l�@���ꂽ�����v�Ȃ�ł����H��t�Â��]���Ă��Ȃ����Ƃ��Óc���͂����Ɓu����v�Ɖ]���Ă��邶��Ȃ��ł����B
�����u���v�ł��B�Óc������S���P�V�S�łŏ�����Ă���Ƃ���A��t�Â��u�����������v�ƍl���Ă��镔���ɂ��Ắu�����������v�Ɓu���v�̎���p���Ă��܂��B�u���v�́u��Ȃ�v�ŁA����ȏ�̂��̂ł͂���܂���
�������A��t�ẤA�����{�̒P���ȕ����̌�T�ł͂Ȃ��A�����{�̈Ӗ��̂��鏑�������A���u���v�ƌ����Ă���̂ł�
��ɏЉ���Z�����͂̂ǂ�����u���������v�Ɠǂ݂Ƃ���ł����H�n�b�L���Ɛ������Ă��������B
�����g�������h�ł͂Ȃ��A�Óc���ɗ����Ę_�킵�Ă���U�����A�Óc���̏��_���Ԉ���ďЉ�Ă��鎖�ւ̔��Ȃ͂Ȃ��̂ł����H�Ƃ������q�˂Ȃ̂ł��B�ēx�����܂��B�u�Óc����́A����{�̈Ӗ����l�@���ꂽ�����ł��v�Ƃ����̂��ԈႢ�ł��邱�Ƃ͔F�߂܂���ˁH
�������\���グ�āA���O�[���ď����C���������ł�
�U������́A�����܂ޑ��̓��e��(���ɋE��������)�ɑ��Ă���ł͂Ȃ��A�Óc���ɑ��Ă��g�s�����h���ƌ������Ȃ��ł��傤���H
���̖����o�̕����A��قǁu�����C���������ł��v�B
to#72191 by zarakoku
Re: �`���̓s�͒}��
2008/4/25 0:17:00
���b�Z�[�W:#95299
�������ł����H���́u����̈��́u���ł��ԈႢ�_�v�v���Ă̂́E�E�E
���u�i�o�v���u�i���O�N�v���A���`�v�㕶����ʖ{�������p�������{�Ɂu���o�v��u�i����N�v�̋L�ڂ����邵�A�`�̓s�́u�n�i�v���A����ȍ~�ɂ��낢��Ȍď̂����������A
http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/tyosaku13/yamai232.html
�́A(4),�@���i�{�Ƒ���{�ɂ��ā@�̋c�_�ł��A�w�E������
�ʂɁu���Ƃڂ��v�ł����ł��Ȃ��āA�����̌��ۂɂ��ẮA�ȑO���疾���Ȏ������Љ�Ă��Ă���Ǝv���܂����E�E�E�B
�u�הn�i�v�Ɓu�הn��v���ɋ�����A���{�ȑO�Ɂw鰎u�x�����p�E�Q�Ƃ��������Ɂu�הn��v�̗Ⴊ�g�F���h�ł��邱�ƁB
����́A�u�הn��v�̕\�L���A���{�����̏����O�ɐ������ƍl���邱�Ƃɂ���āA���ɊȖ��ɗ����ł��܂��B
���^�����u�n�i�v�Ə������̂��A���炭�u�הn�i�v�̐ߗ����ƍl���܂����A����ɂ��Ă��A���^���̌����w鰎u�x�Ɂu�הn�i�v�Ƃ���A�܂��u�i�o�v�Ƃ��������Ƃ̖����ȏ؋��ƂȂ�܂��B
���ɊȒP�Ș_���Ȃ�ł��B������u�I���W�i���͎הn�ゾ�v�ƍl���邩��A���܂��܂Ȏ��Ԃ�z�肵�Ȃ��Ɛ����ł��Ȃ��Ȃ�E�E�E�Ƃ������Ƃł��B
����֓`���ɁA�����I������`�������݂��邱�Ƃ����m�ł���A��z�ł͂Ȃ��̂ł�����A�Z�@�I���͂���܂����
����Ȃ�A�w�ˉ��x�́u[����]�فv�uꇔg�v���w鰗��x�Ƃ����u�����I������`�������݂���v�Ƃ͍l�����܂��H
�ǂ����Ɂu�Љ�I�M�p�͂Ȃ��Ȃ�v�悤�Ȏ��Ԃ����݂����ł��傤���H
��贌��b�́A�����㊿����m���Ă���A�ނ͕������Ӑ}���Ă��܂����B������u�����l�v�̍������������ɕ��������̂͒|������ŁA��������Ɏ���Ă���̂�hyena no papa����ł�
�w�����x�w�㊿���x�ɏo�Ă���u��[����]�l�v�ƁA贌��b�����������w鰗��x�ɂ݂���y[����]�ٓ�[����]�l���z�́u��[����]�l�v�̕������A�g�������̂��h�Ƃ��������͕K�v�Ȃ���ł����H
�Ⴆ�w鰗��x�ɂ��u���m�C�O[����]�فv�Ȃ�ĕ���������ΘA�z������ł��傤���A����ȕ\�L�͂Ȃ��A�����y[����]�ٓ�[����]�l���z�Ȃ�ł�����ˁE�E�E�B
���̓���g�����h�����Óc���̓ǂݕ����́A�|�����̓ǂ݂��u���݂₷���v�Ƃ������Ƃł��B
�����̃n���O���̕����ǂ݂̍������K�v�ł��邾��
�����A�U������́y[����]�ٓ�[����]�l���z�̒��́u��[����]�l�v���A�g�s���h�̕����Ɍ����Ă��ł��傤�˂��H
���́u�����فv�ȍ~�̕����A鰗��̕��Ƃ�����A����͉��̉����������A�ƌ������Ƃɂ����̂ł����H
�́H����Ȃ��Ƃ��ǂ����Ď��ɕ������ł����H��洂����̕������������R���E�E�E�B�s�v�c�Ȃ��Ƃ���B
�����w�ˉ��x�{���ɂ́A��[����]�l�ȂǏo�Ă��܂��E�E�E�B�u���m�C�O�v�̓�[����]�l�̋L������A�ǂ����āu�O�؏��v�́u[����]�فv���u��[����]�l�̂��Ƃ��ƍl������ł����H��߂���悤�Ɏv���܂����E�E�E
�������㊿���́u�������l�v�L�ڂ�m���Ă���͂���贌��b���A�u�����فv�́u�����v�ɑ��āu�������l�v�ƌ������߂������Ă��邩���
�ق�܂��E�E�E�B贌��b���u�������l�v�ƌ������߂������Ă��邩��E�E�E���āA�ǂ����ĕ������ł����H
�U������͕ʁX�̐l�̍l���������荇���Ă��܂��H
���u�������l�v�ƌ������߂������Ă���
�̂́A�Óc���B
to#95281 by zarakoku
Re: �ԈႢ���Ƃ���̂��ȒP�Ȃ͓̂�����
2008/5/2 23:38:00
���b�Z�[�W:#95721
����������A�Ó����������̂ł���
�������A�ԈႢ�������̂ł͂Ȃ�����Ȃ�̎���L�����A�ƌ����\�����i������j�������Ă��邩��
�Ȃ�ł����H���́u����Ȃ�̎���v���āE�E�E�H�v�㊧�s�����܂ł̊ԁA��O�Ȃ��u�הn��v�́u��v���u�i�v�Ə����������Ƃ����u����v�ł����E�E�E�H���̂悤�ȑz������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ����G���Ɛ\���グ�Ă��܂��B
�����ܑ゠����܂ł́u�i�v�ł������ƍl����A���Ƃ��ȒP�ɐ������o���܂��B�u��v�ւ̌�ʂ͂���ȍ~�ɐ������̂��E�E�E�ƁB
���̍l������������Ƃł���H
���u���ł��ԈႢ�̉\��������v�ƌ����_����˂��l�߂�Ahyena no papa�������Ǝv����j����hyena no papa����̈ӌ����A�S�āu�ԈႢ�̉\��������v�̂ł�����A������ے肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A�u���v�ɂȂ��Ă��܂��A�ƌ����b
����ς�A�Ӗ����悭������܂���ˁ`�i�`�Q�`�G�j
�����{�́u�הn��v�Ȃ�ł���ˁH�U������̍l���́E�E�E�B�ŁA�j�������Ƃ��Ắu�הn��v�ƈ��p�E�Q�Ƃ��������͊F���B�Ȃ�A�u�הn�i�v�Ə����������́A�F�u�܂������v�ł���H���ꂼ�u���ł��ԈႢ�v���Ⴀ��܂��H
�����̎��_�ł̕M�҂̔F���Ƃ��Ă͔F�߂邪�A����̏��̒��ŁA������_�Ƃ��ăx�^�[�Ȃ��̂�I�����āA����ɋ����ė��_����A�ƌ������l���ł���H
�����ɁA�����́u�הn�i�v�Ƃ����\�L�͐˂��Ă��܂���ˁH���{���g���h�Ƃ����ł�����E�E�E�B�u�x�^�[�Ȃ��̂�I���v���āA���{�ȊO�ɉ����I�����܂������H���{�Ƒ�������\�L�������̂ŁE�E�E�B
���̗p���Ȃ��������̂��A���Əꍇ�ɋ����Ă͐������\��������A�ƌ������ł�
�Óc��������Ȃ��Ƃ������Ă����̓I��������Љ�����B
�������A�����炭�A�㊿���ȍ~�ɂ͘`�̓s�̍��́A���ۂɁu�הn�i�v��u���r�́v��u�ז��ҁv��u�הn�́v�ȂǂƂ����ď̂ł������ł��낤�A�ƌ������ŁA������A����ɂ́u��v�Ɓu�i�v�̊ԈႢ�_������������A�u�הn��v�́u�הn�i�v�̊ԈႢ�������̂��낤�A�ƌ����l�����X���i��������A�j���Ȃǂł́A�u�הn��v�Ə������҂����Ȃ��Ȃ��Ă����̂��낤�A�ƌ������ł�
���ꂪ�A�g���G�ȁh�������ƌ�����ł��B�N��l�u�הn��v�Ə������҂����Ȃ��Ȃ��Ă����̂��낤���Ă̂́A����ۂł��ˁB�F����A�ڂ̑O�́w鰎u�x�ɂ́u�הn��v�Ə����Ă�������ł���ˁH����Ȃ̂ɁA��O�Ȃ��u�הn�i�v�Ə����������B�����̂Ȃ�����ł��B
���{�܂ł̊ԂɁu�הn��v�Ƃ����\�L���������Ƃ����g�ؐl�h�Ȃǂ��Ȃ���ł���B
�����u�i�v�Ɓu��v�́u�����v�ȂǂȂ������I����Ƃ����̂Ȃ�A���̎j�������������Ă�������
����(4),�@���i�{�Ƒ���{�ɂ��āA���Q��
�|�|�|�|�|
���́u�הn��v�ƈ��p�E�Q�Ƃ��镶�����Ȃ��̂��H���̎�������́A�U������̂����悤�ȁu�����v�ȂǁA�Ȃ������I�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������_�ɂ������邱�Ƃ��o���܂���
�|�|�|�|�|
�̘b�ł���B
�u�i�v�Ɓu��v����ʂ��ꂤ���͎����g���g�o�ŋ����Ă��܂��B�����ł͂Ȃ��āA���������Ă���̂́A���́u�הn��v�ƈ��p�E�Q�Ƃ��镶�����Ȃ��̂��H�Ƃ������Ƃł��B
�u�הn��v�u�הn�i�v�́g�����h������܂����H�ǂ����ɁE�E�E�B
to#95536 by zarakoku
���ς�炸�̔ڋ��ȋc�_�e�N�j�b�N�H
2008/10/24 23:39:00
���b�Z�[�W:#108462
�ǂ����H
������ŁA�u���قƌ�ʂ̈Ⴂ�v�͂ǂ��Ȃ����̂ł����H�B����ɂ͓����Ȃ��ŁA�܂����]����ł����H
�u���فv�́u��ʁv�ł����E�E�E�B���x�����Ε������ł����H�I���W�i���͈�B�I���W�i���ƈႤ���̂͌�ʁB
���͂��͂��A�u���i�{�Ƒ���{�ɂ��āv�������ł���
����H�u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�͂ǂ��Ȃ����̂ł����H�B����ɂ͓����Ȃ��ŁA�܂����]����ł����H�B�i���ς�炸�̔ڋ��ȋc�_�e�N�j�b�N�H�B�j
�ŁA�u�הn��v�Ȃ�ĕ\�L�͑��݂��܂��E�E�E�ɂ��Ă̂��Ԏ��͂ǂ��Ȃ�܂����H
�U������͓���Ɂu�הn��v�Ə������ʖ{�����ۂɂ������Ƃ������Ƃ��u�K�v�ɂ��ď\���Ș_�v�Ŏ����Ē��������B�T�ł͂����܂����B
����������́u��v�Ɓu�i�v�̍�����u��T�_�v�̗�Ƃ����悤�ȋL��������܂�
���̂ł��ˁ`�B���{�������ł��ĂȂ��悤�ł��ˁB�w��i�K�c�x�Ƃ����悭�m��ꂽ�������w鰚�K�c�x�ƌ���Ă���B
�܂����U����������ꂪ��ʂł͂Ȃ��Ƃ͌����܂����ˁH���j�̒��ɂ����p����邭�炢�悭�m��ꂽ�w��i�K�c�x���m���Ɍ�ʂ���Ă���B
�m���Ɂu�i�v�ł���ׂ��Ƃ�����u��v�ƌ���Ă���m�ł��鎖�Ⴞ�Ƃ������Ƃł��B
�u��v���u�i�v�ƌ�ʂ��ꂽ���̂ł͂���܂����B�������A���̉\����ے肷����̂ł͂���܂��A���ۂ̊��Џ�Ɍ�����̂́u�הn��v�ł���̂��H�u�הn�i�v�ł���̂��H�u���o�v�ł���̂��H�u�i�o�v�ł���̂��H
����當����̏��������čl���Ă݂ĉ������B�u�と�i�v�Ɓu�i����v�Ƃǂ���ɍ����W�R�����F�߂��邩�H
��҂ł���H
����ɑ��锽�_�͉��ł����H�j���I�������ȂĔ��_���Ă݂ĉ������B
�����m�Ɂu�뎚���v�ƒf�薕���o������̂͒m��܂���
�I���W�i���͈�ł���H�Ⴄ��ł����H
�u�S���҂̑�ȏ،��̋L�^�v���āA����̓U������̐˂���g���j���h��̕\�L�ł���ˁH�Ȃ�ł���Ȃ��̂����Ƃ����낤�ɃU�����u��v�ƌ�����ł����H
���ꂪ�u�S���҂̑�ȏ،��̋L�^�v�ƌ�����̂Ȃ�A�����́u�i�v�،������A�u�S���҂̑�ȏ،��̋L�^�v�̂͂��ł����E�E�E�B���́u�S���ҁv���u�i�v�������I�Ƃ����E�E�E�B
to#107939 by zarakoku
Re: ���ς�炸�̔ڋ��ȋc�_�e�N�j�b�N�H
2008/11/22 23:06:00
���b�Z�[�W:#109765
������ł́u��v�Ɓu�i�v�̍��������������ɂ��āA�w�u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�̂ł����H�x�A�ƌ���ꂽ�̂ŁA�w�͂��͂��A�u���i�{�Ƒ���{�ɂ��āv�������ł���x�A�Ƃ��������Ă��܂��B
���u���v���t���Ă���̂��������ꂽ�̂ł����H�B������A�u�הn��v�Ɓu�הn�i�v���m�肵����ŁA���i�{�Ƒ���{�ɂ��āu���v�������A�Ƃ��������Ă���̂ł�
������A����́u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�̍������ǂ����čm��ł���̂��H���������肾������ł����E�E�E�B����ɂ͂��́u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�����������āA���ꂪ�����ɂ���č��������\�L�������Ă���E�E�E�Ƃ����̂Ȃ�A���̎j���������ĖႦ���������̂��Ƃł��B
�����ł͂Ȃ��āA�u���i�{�Ƒ���{�ɂ��āv�������ł���Ɠ������B�����������̂́u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�̍����B
�����͂����Ɠ����Ă���ł͂���܂���
�ǂ��łł����H�u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�ɂ��Ăł���B����̍����ł���B�ǂ��œ����܂����H
�����ŁA�u�הn��v�Ȃ�ĕ\�L�͑��݂��܂��E�E�E�ɂ��Ă̂��Ԏ��͂ǂ��Ȃ�܂����H
���O���Łu�߂����v�����̒��́A�u�����āv�̌�ɁA���Ԏ��������Ă���܂���
���u�הn��v�́A�u�ז��ҁv�̑��݂�
�ł����H�������q�˂����̂́u�הn��v�Ɓu�הn�i�v�̍����Ȃ�ł����E�E�E�B����ɉ�����E�E�E�B
���Ԏ������Ă��Ȃ��U�������
�������t�������āE�E�E�ł��B
�����U������͓���Ɂu�הn��v�Ə������ʖ{�����ۂɂ������Ƃ������Ƃ��u�K�v�ɂ��ď\���Ș_�v�Ŏ����Ē��������B�T�ł͂����܂����
�������A���߂���A鰎u���{���i�ꎚ�ꎚ�ʂ����j�ʎ���`�ɋ����ďo�������̂ł��鎖�����
���́u�ʎ���`�v�Ȃ���̂��A���E���ꂪ�u�K�v�ɂ��ď\���Ș_�v�Ŗ��炩�ɂ�����ł����H���Љ�����B
���t�ɂ��ǂ����u���_�v�ł��鎖�������Ă���܂�����
�܂�A�����͂Ȃ��E�E�E�ł��ˁB
���K�v�\���̘b�ɂ͂������܂���̂ŁA���f��\���グ�܂�
�قق��A�����̕��́u�ʎ���`�v�Ƃ��������Ă���Θ_�͖Ɛӂ���A�l�ɂ́u�K�v�ɂ��ď\���Ș_�v��v������H
�����ɑ�ÁB�l�ɂ͌������E�E�E�B�������A���x���w�E����ĕ��ʂȂ�C���t�����Ȃ�ł����ˁ`�A���̃_�u���X�^���_�[�h�ȂE�E�E�B
to#108539 by zarakoku
��T�Ƃ́H
2008/11/22 23:59:00
���b�Z�[�W:#109771
�������̂ł��ˁ`�B���{�������ł��ĂȂ��悤�ł��ˁB�w��i�K�c�x�Ƃ����悭�m��ꂽ�������w鰚�K�c�x�ƌ���Ă���B�܂����U����������ꂪ��ʂł͂Ȃ��Ƃ͌����܂����ˁH
�������A�������Ԃ��悭�m��܂���̂ŁA�f��͏o���܂��A��T�̉\���͂���ł���H
�Ȃ�ł����A���́u��T�v���Ă̂́E�E�E�H�u��ʁv�ł͂Ȃ��ƁH
���w鰚�K�c�x�ƌ������������j�㑶�݂��Ȃ��A�Ƃ͂����ɂ͒f��o���܂���
������َ��B�w��i�K�c�x���w鰚�K�c�x�ƌ�ʂ����̂��I�ƍl���Ăǂ��ɖ���������܂����H�u��E�i�v�̌�ʂ͑��ɂ�����܂��B
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/tai_ga_tadashii.html
�u��v�u�i�v�u��v�͌�ʂ��ꂽ�\���������ł��B�����͎j�������ł��B
������A��ʂ��ꂽ�\��������̂ł��傤
�u����v�Ǝv���͉̂��́H
�����i�{��{�Ƃ����l�́A�u�i����v���������ɂȂ�̂ł���H
��������A�u�הn�i���הn��v�ł��ˁB
�����I���W�i���͈�ł���H�Ⴄ��ł����H
������A�Ƃ͌��܂�Ȃ��ꍇ�����邵
�ǂ������ꍇ�ł����H
���I���W�i���������Ă��܂��Ă���ꍇ������
�u�����Ă��܂��āv���I���W�i���͈�B
�����������������e����l�����݂����A�ƌ������j�I����������
�Ȃ�ł����H���́u���e����l�v���Ă̂́E�E�E�B
��������A�ʂɌ��j�����P�O�O���ے�Ȃǂ��Ă��܂����B�Q�l�����Ȃǂƌ������肵�ė��܂�������A���l�͏����͂��鎖�͔F�߂Ă���̂ł���
����u��v�̏ؐl�͂��܂���A�u�i�v���������́w鰎u�x�̎p�ł���ƍl����̂������Ȃ�ł��B
�ŁA���_�́u�ז��ҁv�Ƃ��u�ʐ��v�Ƃ��u�ʎ���`�v�Ƃ��E�E�E�B
���ړI�j�������������Ă��������܂����H����Ɂu�הn��v�Ƃ������̂��I�ƌ����E�E�E�B
to#108541 by zarakoku
�҂͑͂̊ԈႢ���R���̂Q
2008/11/26 0:03:00
���b�Z�[�W:#109932
������Ȃ�u���i�{�v�Ə������l�����u�n�����v�ƌ����o�����˂܂����
���H�ǂ����Ăł����H�h�b�O���[�X���݂ł�����A�u���i�{�v�ʼn�����肠��܂��E�E�E�B
��������A�u��ʂ��{���{������v�A�ƌ������悤�ȁu�����v�����������Ă�\���́A�s���̈����j�����Ԃ��A�����ɂƂ��ēs���̂悢���̂ɂ���ւ��邽�߂́u�k�فv
�ǂ����āu�k�فv�Ȃ�ł����˂��H�����ς蕪����܂��E�E�E�B�����������Ƃ��ďЉ�Ă���̂��u�k�فv�H�����ł��Ȃ����̂������ł��邩�̂悤�ɑ����̂��u�k�فv�ł́H
����͂�Ahyena no papa����̎v�z�̍���ɂ͒����l�̎��̎v�z���L�����A�ƌ������ł���
�������B��ʂ͂ǂ��ɂł�����܂��B������w��������x�́u���{�v���V������ŕ��Ă��܂�����ˁH�w�����x�ł͂V���Q�Q���ł����B
����͌��ݒm���Ă���w��������x�Ƒ��Ⴕ������������Ƃ̂��Ƃł��B���ꂪ�ʖ{�Ƃ������̂̎��ԂȂ�ł��B�@�����Γǂ�ł݂ĉ������B
�����Ԏ��ɂȂ��Ă��܂���B�u�j�������v���Ă̂́A�v�㊧�{�Ƃ����u�j�������v�B����܂ł̂��鎞�_�ł̌�ʂł���Ɛ�Ԃ��ꂽ��A�U������͂ǂ����_�����ł����H�u�j������������v�Ƃ�������ڂł������܂����H
�������A���݊m�肳�ꂽ�j�������͍����Ɏg���܂�
������A���́u���݊m��v���Ă̂͑v��̊��{�B
���܂��A�u����܂ł̂��鎞�_�ł̌�ʂł���v�ƌ����̂Ȃ�A�I���W�i���Ȃǂ����邩�H�A�u��ʁv�ł��鎖��K�v�\���ɐ������������̂ł���
�ق�ˁA�������ł͂��́u���݊m�肳�ꂽ�j���v�����{�E�E�E�Ƃ������_���������i�߂Ȃ�����Ȃ��ł����B�������k�点�Ă���̂́u�ʐ��v�Ƃ��u�ʎ���`�v�Ƃ���������ځB
���̕��͍����������Ă��܂���A����܂ł̏����B�U������͂ǂ�ȍ����������Ă��܂����H
�����g�}�������E�������[�ɂ̓z�N��������B����Đ��܂ꂽ�Ƃ�����L�����E�E�E�E
���}�������������E�͖��O�ʂ����m��܂��A�S���S������܂���B�����ӂ�
����͂�A���̔�g��������Ȃ��̂��H����Ƃ�������Ƃ܂����̂��H���{�ɂ́u��v�Ƃ���B����āA�����{�ɂ��u��v�Ƃ������E�E�E�Ƃ������Ƃł��B
�u�ʐ��v�u�ʎ���`�v�E�E�E�B����Ȃ��͍̂����ɂȂ�܂���B
���j�������́A�����́A�V���I�㔼�̒}���ɁH�u���}�C�v�Ƃ����n�����������A�Ƃ��ď����Ă��鎖�ɂ�
�܂�́A��ʂ͔F�߂Ȃ����Ă��Ƃł��ˁH�u���ł��������_�v�ł��B
�S�U�O�O�ӏ��̈ٓ��͉��Ȃ̂ł����H�u���F������v���Ă����������Ȃ̂ł����H
鰂͘`�Ɂu���F������v����������ł����H
to#108655 by zarakoku
Re: �u���e�̐����Љ�v����
2009/4/10 23:17:00
���b�Z�[�W:#118025
������Ȃ�Ahyena no papa����́w���������A�Óc������u���j���̍������͎n�߂���ے�I�v�ł�����x�ɑ���ے�I���X��������Ȃ���悩����
�����̞B���ȕ\���͒I�ɂ����āE�E�E�B
�������u�قڔj�]���v����ł����H��̓I�ɘb���Ă��������B��
���Óc����́A
��http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/tyosaku13/yamai21.html
���ŁA
���̂ˁA����͑v���{�̂�������a�{�ōl���Ă���E�E�E�Ƃ������Ƃł���B
�|�|�|�|�|
�����������Ă����k�v�{�E��v�{���A�S���ɂ킽���đΏƂ��A�L�^���Ă��邱�Ƃ�
���Ȃ킿�A�����ς��g�����{�͑��{�i���{�j�ɂ܂����Ă���h�Ƃ����Ƃ��A���R�A�Ћ��{�����́u�ΏƍZ�ٓ��v�ɑ��݂���̂ł���B
�|�|�|�|�|
�ł���H���́A�ǂ��ɃU������̌����悤�ȁA
�|�|�|�|�|
����̑v�㊧�{���A��̎ʖ{��������]�ʔō����ꂽ�A�ƌ����u�f��b�v�͂قڔj�]���Ă���
�|�|�|�|�|
���Ă��Ƃ������Ă���܂����H
�悭�ǂ݂������Ă��������B
���k�v�{����Ŏ���ꂽ�̂Ȃ�A���̎c���ʖ{����{�Ɏg��ꂽ�\������������
�u�\���������v���Ă̂̓U������̑z���ł���H���Â��鍪���́H
���u���i�{�Ƒ���{�ɂ��āv��u鰚�v�̘b��Y���ꂽ�H�B
�́H���������������Ȃ�ŖY����ł����H�h�b�O���[�X�Ɓw鰚�K�c�x�ł��B
�h�b�O���[�X�ɂ��Ă̓U������̃}�g���Ȕ��_�͂Ƃ��Ƃ�����܂���ł�����ˁH
�w鰚�K�c�x�́u�S�Ӗ{�v�w�j�L�x�u���z��`�v�Ɍ�������̂ł��B�w��i�K�c�x�����������͊������A���������T�����Ă܂Ƃ߂܂����B
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/5739/gidaihougi.html
���̓�Ƃ��܂��A�b��ɂ��܂����H
�����u���o���i�o�̌�T�ł��锤���v�ƛL�v�������f�����E�E�E�����̂Ȃ���z�B��
������A�j�����Ԃ��̂���
������A����͓���́w鰎u�x�ɂ͎הn��Ƃ������I�Ƃ������_����ł����āE�E�E�B
������A�㊿�����@���̋L�^�B�A���A�V���I�㔼�́u�ז��ҁv�ɂȂ���
�P�Ȃ��ʂł��B
�����j���̈ꔭ�Œ��v
鰒��������w鰎u�x�ɂ́u�הn�i�v�Ƃ������I�Ƃ���������Ȃ��؋��B
to#117921 by zarakoku
Re: �u���e�̐����Љ�v����
2009/4/16 22:57:00
���b�Z�[�W:#118325
��������O
�͂�H�����u������O�v�Ȃ�ł��傤���˂��H�ǂ݂悤�ɂ���Ắu�U������̃}�g���Ȕ��_�͂Ƃ��Ƃ�����܂���ł�����ˁH�v��������O�E�E�E�Ƃ��B
�����̘_�_�́A�Óc������ꂽ�A����Ɂu����i���ԈႦ���̂��낤�v�Ƃ���j�Ƃ��������A�̖��ł������̂�����
��t�Âł���H�w�הn�㍑�̘_���x�P�V�T�őO��B
�����̘b�ƊW�̂Ȃ��A�whyena no papa����́u�h�b�O���[�X�v�ƌ�����Ȗ��O��t�����b�x�A�ȂǁA�n�߂���i�n���ɂ��āj����ɂ��Ă��Ȃ�����
�����P�V�S�őO��B
�Óc���͂������ʂł͂Ȃ��A���肾���Ă��܂���ˁB���̘b�͂Q�N�O�ɂ��U������Ƃ��Ƃ肵�܂����B
�|�|�|�|�|
���́u���v���u���i�v�ł��낤���Ƃ͊��ɐ������܂����B����A�Óc���̐����́u���i�{�v���A�V�_���J��u����{�v�ɏ����������Ƃ������̂ł�����ˁH�Ȃ�Ńh�b�O���[�X�����錚����V�_���J��u����{�v�Ɖ��߂ɂ�Ȃ��̂ł����H���̗��R��������Ă��������B
�|�|�|�|�|
����ɑ���U������̕Ԏ��B
�|�|�|�|�|
�������Ȃ̂ł����H
�@��t�Ấu�����{���i�L���㎚�Ҍ��v�́A�ԈႢ���A�Ƃ�����̂ł����H�@�u���v���u��v�Ə��������A�u�i�v���u��v�Ə��������āA��t�ÂɁu���v�ƌ����Ă���l������̂ł���H
�|�|�|�|�|
�Óc���̂P�V�U�ł�ǂ�ʼn������B�Óc���͑�l���A�P�V�T�`�P�V�U�łŎ��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B
�|�|�|�|�|
���̂悤�Ɍ����Ă���A���́u���i�{�����{�v�Ƃ���������s�Ȃ����u���̏��{�v�̎����I���i�����炩�ƂȂ낤�B�u���i�{�v�Ƃ������ʂ���قƂ��A(�Ƃ��ɁA�u�i�v�́u�{�v���w�����ƂƂȂ������߁A��ォ��͂��̗����͏d���ƌ�����悤�ɂȂ����B�܂��u���v�����{�a���ɂɂ��킵���Ȃ��B)������u���{�v�Ɓu����v���Ă���̂ł���B
�|�|�|�|�|
�Óc�����g���A�P�V�R�łɈ������悤�ɁA���́u���i�{�v�ɑ����āu�����V�v�Ə�����Ă���܂���ˁB�u��v�́u���v�ł��B�Ȃ�Łu�ɂ��킵���Ȃ��v��ł��傤���˂��H�V�_���J��{�a�̕����A��قǁu�ɂ��킵���Ȃ��v�Ǝv���܂����E�E�E�B
�v���o���Ă��������܂������H
�����w鰚�K�c�x�́u�S�Ӗ{�v�w�j�L�x�u���z��`�v�Ɍ�������̂ł��B�w��i�K�c�x�����������͊������A���������T�����Ă܂Ƃ߂܂����B�E�E�E���̓�Ƃ��܂��A�b��ɂ��܂����H��
���ǂ����ǂ����B
�����̘b�́A��������hyena no papa����̕�����u����i���ԈႦ����v�Ƃ��Ē��ꂽ�̂�����A
�����́u����ɚ���i���ԈႢ�_���������v���̍����ɂȂ��Ă����̂ł�����
������A��ʂ���������ł��傤���I�������Ă��ł��H�Óc���́u���i�{�v�u����{�v�͌�ʂł͂Ȃ��A���肾�ƌ����Ă��ł���B��ʂ������獢��̂͌Óc���̕��E�E�E�B
���L�v�����A�הn�㚠���V�n�i���Ə����������̂Ɠ����悤��
�Óc���̗���ɗ��ĂA����́w�㊿���x��`�ɂ���ĉ��߂��̂ł��B�w�㊿���x�ɂ��i�o�͏o�Ă��܂���B
���u���o���i�o�̊ԈႢ���A�Ɣ��f�����v���ɂȂ邾��
������Ȃ�Łu�i�o�����o�v�̃P�[�X�͍l���Ȃ���ł����H�ڂ̑O�́w鰎u�x�Ɂu���o�v�Ƃ���̂ɏ����̕Ҏ҂́A�w�����x�Ƃ����A�܂������g���j���h�ɂ���āA���X�Ɂw�i�o�x�Ə������߂���ł���ˁH�Ȃ��ł����H
����Ԋ�{�i�X�O�`�X�X�D�T���̐M�����j�ɂȂ�O���u�L��
����ǂ́u�X�O�v�Ƃ��������܂ŏo��(~_~;)�ǂ�����Z�o�������̂Ȃ̂��H
���P�O���̈ʂ̐M���������Ȃ����j���ޏ����ɐ����āA�O���u�L�ڂ�ے肷��A�ƌ����A�x���⍼�\�t�̘_�@
���j���̕Ҏ҂��A�݂ȏ������߂��Ƃ������ۂ͂ǂ����������ł����H�������A���݂��Ȃ��u�i�o�v�Ƃ����\�L�܂őn�삵�āE�E�E�B
�������ɓs���������L�ڎ����́A�S�āu�ԈႢ���v�Ƃ���A�E�����ғ��L�̍��\�I�_�@
�ǂ����u�����ɓs���������v��ł����H�܂��u�E�����ғ��L�v�ł�����܂����B��B���̐l���הn�i�ƍl����l�͑����B
�����j�Ƃ�鰒��炪�A�w鰎u�x�ɂ́u�הn�i�v�Ƃ����������A�Ɛ��蔻�f�����L�ڂł��邾���̎�
�ǂ����Ă���鰒���͎v������ł����H�w鰎u�x��ڂ̑O�ɂ��Ă���̂ɁH
�����j�Ƃ̎g���u�H�v�u�]�v�u���v�̋L�ړ��e���A�P�O���ʂ̐M���������Ȃ����́A���ɉ��x���m�F������
������Ɂu�P�O���ʂ̐M���������Ȃ��v�ƌ����Ă��ł��傤���˂��H����ȕ��Ƃ������Ǝ��̂��A���{�̕\�L����X���z���Ă������̂Ɠ���ł���E�E�E�Ƃ������_����ɗ���������Ă����ł����E�E�E�B
to#118050 by zarakoku
�u���s�v����
2009/5/30 21:22:00
���b�Z�[�W:#121145
���u���i�{�Ƒ���{�v�̘b
�P�Łu���s�v�Ƃ́A����@���ɁH
to#120369 by zarakoku